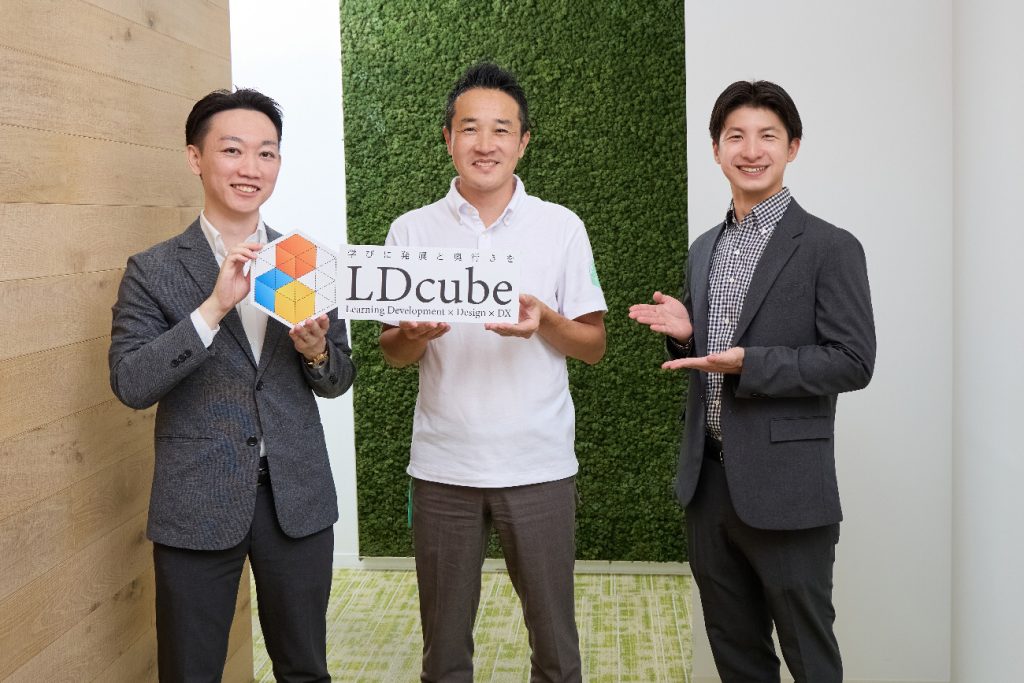LMSやeラーニングを提供するだけではない
研修・人材育成領域の知見が大きな強み
――まずは事業内容やサービスの特徴について紹介してください。
新井 弊社は大きく4つの柱でサービスを展開しています。1つ目は「社内トレーナー養成支援」です。行動科学に基づいて個人の行動スタイルから個人の強みを明らかにする診断ツール『LIFO』をはじめ、社内研修で活用できる各種プログラムを提供し、社内トレーナーの育成や研修の内製化のお手伝いをします。
2つ目は「CrossKnowledge(クロスナレッジ)」です。フランスに本社を置くCrossKnowledge社と提携し、グローバル31カ国語に対応したLMSをはじめ、著名なMBA教授が監修した教育コンテンツを提供しています。
3つ目は、6カ月で楽しく学べる体験型ビジネススクール「Biz-Ex(ビジックス)」。こちらは経営シミュレーションeラーニングとオンラインコーチングを組み合わせたもので、社長の立場で会社全体の経営を疑似体験しながら、マーケット分析力・経営分析力・戦略的思考力などを開発するサービスです。昨年、第9回 HRテクノロジー大賞(編注:日本のHRテクノロジー、人事ビッグデータ(アナリティクス)の優れた取り組みやサービスを表彰。HRプロ運営のProFuture代表 寺澤が審査委員を務める)のラーニングサービス部門優秀賞に選ばれました。
そして4つ目はAIを活用したデジタル学習プラットフォーム「UMU(ユーム)」。先ほどの「CrossKnowledge」がどちらかというと人事の方々にご活用いただく教育プログラムなのに対して、「UMU」は営業強化や技術伝承など現場教育に効果のあるサービスとなっています。
――昨今多くのLMSやeラーニングが開発・提供され、競争が年々激しくなっていますが、御社はどのような点で差別化を図っていますか?
新井 eラーニングやLMSを提供されている企業さんは、エンジニアをたくさん抱えて、コンテンツ作りやシステム構築に主眼を置いたビジネスを展開されているケースが少なくありません。しかし弊社は、ビジネスコンサルタント(BCon)の子会社として設立された経緯から、研修・人材育成領域のノウハウや知見を豊富に持ち合わせています。つまりコンテンツありきではなく、コンテンツを活用しながら、いかに効果的な学習や人材育成に繫げていくか。そんなご提案をできるのが強みであり、最大の差別化ポイントと言えるでしょう。
――LMSやeラーニングの市場は現在どのような状況ですか? またその中での御社の立ち位置についても聞かせてください。
新井 例えばeラーニングを提供されている上場企業さんの販売状況などを確認すると、前年比120~130%といったデータが見られます。デジタル化やAIの活用といった波は、学びの領域にもどんどん押し寄せており、トレンドとして今後さらに伸びていくでしょう。そういう意味で競争が激しくなっていくことは間違いありません。その中での弊社の立ち位置ですが、設立して2年弱ということもあり、まだまだ追いかける立場です。とはいえ「社内トレーナー養成支援」といったサービスは競合も少なく、まずはそういった独自のポジショニングで存在感を発揮していけたらと考えています。
――あえてターゲットを挙げるとするなら、今後どのような企業へのアプローチを強化していきたいですか?
新井 HRプロのアンケート調査を活用している中で、「研修でお使いのリソースは何ですか?」と質問したところ、最も多かった回答は「外部講師」や「eラーニング」ではなく、「社内講師」でした。これは我々にとって意外な結果でした。というのも、我々はこれまでBConという研修提供会社の中で活動していたため、基本的に「外部講師」のニーズがあるお客様にアプローチしてきました。ところが我々が認識していなかっただけで、実は多くの企業が「社内講師」を活用していたと。「社内講師」で研修を行なっている企業様はそもそも外部の研修提供会社には相談しないので、これまでは気づきませんでした。
こうした「社内講師」で研修を行なっている企業様の場合は、「外部講師」のニーズはなくても、「研修効果をもっと高めたい」「研修をうまく組み立てたい」などのニーズはお持ちでしょうから、我々としても今後はそこを一つの重要なマーケットとして捉え、良き相談相手・伴走者になっていきたいと考えております。
SEO対策を中心としたマルチチャネルで
集客できる体制を強化していきたい
――マーケティングの重要性はどのように捉えていますか?
新井 実はBCon時代には本格的なマーケティングは実施しておらず、社内トレーナーを養成するプログラムがあることやLMSを提供していることなど積極的に外部に発信していませんでした。そのため営業担当者がお客様にご紹介しない限り、認知が広がらないという課題がありました。そこでBConから分社する際は、きちんと売れる体制を作っていくために「マーケティングをやり直す」というコンセプトを掲げて、動き出しました。
マーケティング活動は、認知を広げていくという意味でも、またリードを獲得し、売上に繋げていくという意味でも、最初の入り口となりますので、弊社にとっては最重要タスクの一つと位置付けています。
――現在マーケティングの体制はどのようになっていますか?
新井 設立当初はマーケティング専任者はおらず、私ともう1人が兼務で担い、私がコンテンツの原案を作りながら、それをサイト上に実装するような形でスタートさせました。当時は言ってみれば0.5人+0.5人=1人マーケティングのような状態でしたね。そこから2024年11月に専任として立松が加わり、さらに2025年4月には専任がもう1人加わり、現在は専任2人+0.5人+0.5人という体制で運用しています。
――マーケティングに関する具体的な活動内容についても教えてください。
新井 2023年4月の設立当時はウェブサイトもなく、リード情報もゼロで、メルマガを送る相手すらいませんでした。ですので、当初は顧客接点を増やすために、まずは展示会に出展する日々を送っていました。同年6月にようやくサイトが完成し、以降は特にSEO対策に注力している、というのがここまでの流れです。当初は例えばウェビナーを開催しても、視聴者がゼロといったことがありました。それでも、途中参加の可能性があるのでそのまま続けましたね。
現在は展示会への出展を少しずつ減らしながら、SEO対策のほか、HRプロの活用や各種ポータルサイトへの掲載、リスティング広告など、マルチチャネルで集客できる体制を整えています。ハウスリストからウェビナーの集客もできるようになりました。
SEOの記事づくりに関しては私自身が書き手となって、2年あまりで計580本を公開しました。とはいえ最近は量より質を重視し、今まで作ってきた記事をリライトするなど、より効果的な内容へとブラッシュアップする方向にシフトしています。
――ご自身で記事を書かれているとは驚きです。現在も書かれているのですか?
新井 「マーケティングをやり直す」と言ったときに、自社のサービスについて一番早く、かつ的確に伝えられるのは誰かと考えたら、それは自分だろうと。この仕事だけは逃げてはいけないと思ったんです。したがって当時は営業活動などもしていたのですが、営業は他のスタッフにすべて任せ、記事の執筆に集中。とにかく毎週毎週書き続けました。現在は記事の量産体制がようやく落ち着いてきたので、少しずつ解放されつつあります。
HRプロを活用したことで
リード獲得単価は約半分、獲得数は約3倍に
――HRプロの活用状況についてお聞かせください。また実際にお使いになられて、どのような手応えを感じておられますか?
立松 年3回実施のアンケート調査をはじめ、メルマガ広告、セミナー動画の掲載、また資料ダウンロードのキャンペーンへのエントリーなど、幅広い形で活用しています。なかでも手応えを感じているのは、やはりアンケート調査でしょうか。SEO対策として独自性のあるコンテンツを作るにあたり、今の世の中の流れや価値観を的確にキャッチできるので、非常に使い勝手がよいと考えています。アンケート結果はホワイトペーパーにしたり、ウェビナーにも活用できるため、重宝していますね。
また、セミナーアーカイブ動画の掲載も手応えを感じています。定期的にお申込みをいただけるので、人事担当者のみなさまのお役に立てている実感があります。どのようなテーマ・情報を掲載するかは、お客様の声に最も多く触れているインサイドセールスチームとも、意見交換をしながら決めています。
――HRプロをご利用いただいて、どのような変化や成果がございましたか?
立松 目に見える成果という意味では、リード獲得数は確実に増えました。昨年度と比較すると、リード獲得単価は約半分に減っている一方で、獲得数は約3倍に急増し、アンケート調査や各種企画などHRプロを通じた施策が効いてきた結果だと感じています。
新井 展示会から始まった我々のマーケティング活動ですが、その後SEOを覚え、メルマガや広告を運用し、さらにはホワイトペーパーやウェビナーも展開して…と、繰り出す技がどんどん増えてきました。格闘技に例えるなら、最初に打撃を覚え、そこから絞め技、関節技などを着実に身につけたことで、今ようやく総合格闘技で戦える素地ができてきたなと。これもひとえにHRプロのおかげだと思っています。
――競合サービスと比べて、HRプロの強みや活用するメリットは何だと思われますか?
新井 あくまでも感覚論ですが、競合サービスと比較して、HRプロからのコンバージョンのほうが求めているターゲット層に近い感じはしますね。
立松 ウェビナーのアーカイブを掲載すると、HRプロで取り上げていただきやすくなるので、我々としても新しいウェビナーをどんどん作っていこうというモチベーションになり、それが良い相乗効果になっていると感じます。また定期的にトレンド情報を提供いただけるなどサポートも細やかで手厚く、とても心強いです。
――最後に、マーケティング活動における今後の展望をお聞かせください。
新井 まだまだリード獲得数を増やしていかなければなりませんので、引き続き手を替え品を替え、マーケティング活動に注力していきたいです。またその中で、今後は生成AIに対応したマーケティングを進めていくことも重要な課題となるでしょう。それらを実践しながら、先ほども申し上げた通り、これまであまり認識してこなかった「社内講師」で研修を行なっている企業様のニーズも見据えて、自分たちのプレゼンスを発揮していきたいと思います。
聞き手:ProFuture株式会社 マーケティングソリューション部 営業グループ マネージャー 小多田隼也(右)