企業の人事・経営層向けのマーケティング活動に最適!会員数10万人超の人事ポータルサイト
会員数10万人超の人事ポータルサイト「HRプロ」で貴社商品・サービスのプロモーションを行い、法人リードを獲得できます。
2025.6.19
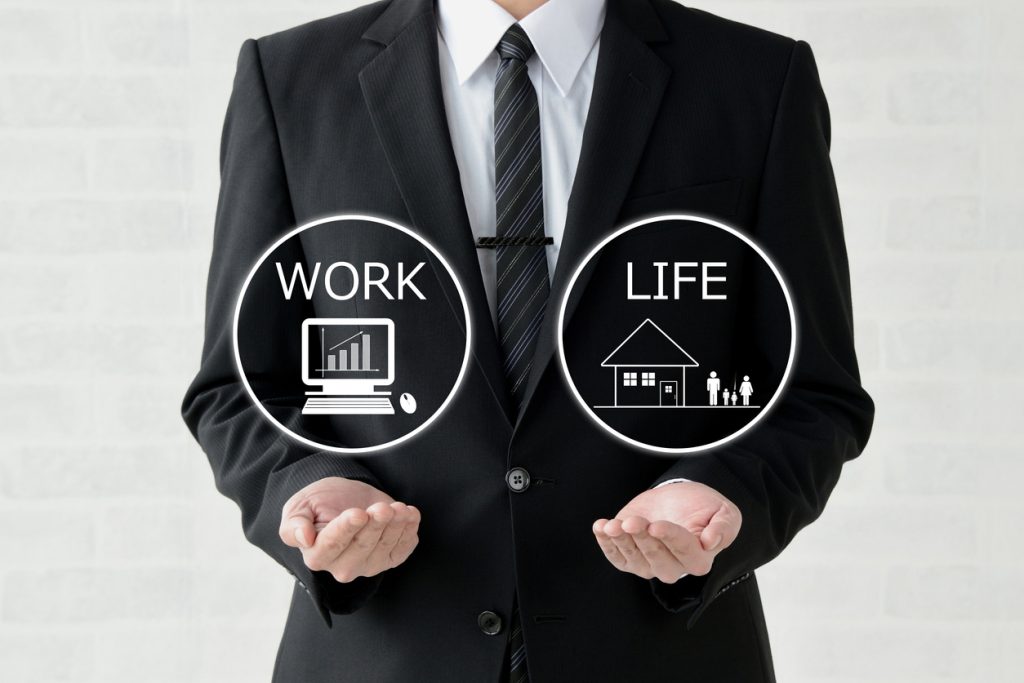
「ワークライフバランス」という言葉は、働き方改革の推進とともに広く浸透してきました。しかし、この概念の本質を正確に理解せず、仕事と生活のどちらかを重視すべきかという誤解をしている人も少なくありません。
ワークライフバランスとは、単に仕事と私生活の時間配分を調整することではありません。むしろ、仕事と生活の両方の質を高め、相乗効果を生み出すことを目指す考え方です。つまり、仕事の生産性を向上させながら、同時に充実した私生活を送ることで、全体的な生活の質を向上させることを意味します。
近年、テクノロジーの進歩やコロナ禍の影響により、リモートワークが急速に普及しました。これに伴い、従来のワークライフバランスの概念も進化を遂げています。例えば、「ワークライフインテグレーション」や「ワークライフブレンド」といった新しい考え方が登場しています。これらは、仕事と私生活をより柔軟に融合させ、個人のライフスタイルに合わせて最適化することを提唱しています。
本記事では、ワークライフバランスの定義や背景、具体的な取り組み事例を紹介するとともに、リモート時代に適した新たな考え方についても詳しく解説します。働き方の多様化が進む現代において、自分に合ったワークライフバランスを実現するヒントを見つけていただければ幸いです。
目次
会員数10万人超の人事ポータルサイト「HRプロ」で貴社商品・サービスのプロモーションを行い、法人リードを獲得できます。
「ワークライフバランス」という言葉は、働き方改革の推進とともに広く浸透してきました。しかし、その本来の意味を正確に理解せず、仕事と生活のどちらかを重視するものと誤解している人も少なくありません。
ワークライフバランスとは、本質的に「仕事と生活の調和や調整」を意味します。この概念は、仕事か生活かどちらか一方だけを重視するのではなく、両者をバランス良く充実させることを目指すものです。つまり、キャリアの充実とプライベートの充実を同時に追求する考え方なのです。
従来の日本社会では「仕事一筋」な生き方が主流となっており、仕事のみが重要視される傾向がありました。そのため、ワークライフバランスは、このような従来の考え方に対する一種の反動とも言えるでしょう。
ワークライフバランスという概念は、1980年代にアメリカで誕生しました。日本では、バブル崩壊後の1990年代以降に普及し始めました。当初は、女性の社会参画が活発になったことで、仕事と子育ての両立が問題視されるようになり、無理なく働き続けられるような対策を講じ始めたことが契機となっています。
その後、家族のあり方や働き方の多様化が進み、雇用不況によって企業に経済的な豊かさを期待できなくなったことも相まって、男女ともに仕事だけでなく、プライベートも重視するような生き方が注目を集めるようになりました。
ワークライフバランスの実現によって、以下のようなメリットが期待できます。
・仕事以外の時間が確保でき、充実した生活を送れるようになる
・家庭での時間が増え、家族との絆が深まる
・適切な休息を取ることで、心身の健康を維持できる
・時間に余裕ができ、自己啓発や地域活動など、本人が真に望むことに取り組める
・子育てや介護などの負担があっても、自分らしい形で仕事と両立できる
ワークライフバランスが適切に機能すれば、充実した生活が仕事のパフォーマンス向上につながり、それによって私生活もさらに潤うという相乗効果が期待できます。例えば、時間に余裕ができることでスキルアップの機会が増え、その結果、仕事の効率が上がるといった好循環が生まれる可能性があります。
このように、ワークライフバランスは単なる仕事と生活の時間配分ではなく、個人の幸福度と生産性を同時に高める重要な概念として認識されています。企業にとっても、従業員のワークライフバランスを支援することで、モチベーションの向上や優秀な人材の確保・定着につながるため、重要な経営戦略の一つとなっています。
関連記事:ワーケーションとは?政府も推進している施策。ワーク(仕事)とバケーション(休暇)は組み合わさるのか?
日本でワークライフバランスが重視されるようになったことには、以下のような背景がある。
・少子化の進行
・団塊世代の大量退職
・共働き世帯の増加
・女性が活躍できる社会への期待
・高齢化問題
・長時間労働の是正
・多様な働き方への対応
このなかでも、とくに少子高齢化の問題が大きな要因だといえるだろう。少子高齢化によって働く人が減少し、長時間労働が蔓延したことや、仕事と子育てや親の介護との両立が難しいことなどが社会問題となった。これらの理由により、仕事と生活のバランスを取ることの重要性が高まっていった。
企業としても、従業員の労働環境の整備や健康管理、業務管理などの努力をおこなうことが重要である。ワークライフバランスを実現できた場合には、企業にとって以下のメリットがある。
・従業員満足度が高まり離職率の低下と定着率の向上が期待できる
・従業員の意欲や能力を向上させられる
・労働環境の良さをPRでき、有能な人材を確保しやすくなる
・長時間労働をしないことで、自然と業務の効率が上がる
・女性社員が定着する
・従業員のストレス軽減によるメンタルヘルスの改善
・イノベーションを生み出す余裕と創造性の向上
そのため、企業をより良くするためにもワークライフバランスを重視すべきなのだ。また、政府も「働き方改革」を推進し、長時間労働の是正や有給休暇の取得促進、多様な働き方の実現などを目指している。これらの取り組みにより、ワークライフバランスの重要性はますます高まっていくと考えられる。
関連記事:エンゲージメントとは?従業員の定着率をあげるためにできるエンゲージメント向上の施策
ワークライフバランスの取り組みについて、実際に導入して成功している企業の事例を見てみると、どのように実施すればいいのかをイメージしやすくなるでしょう。ワークライフバランスの実現に向けた取り組みは、企業の規模や業種によって異なりますが、従業員の満足度向上や生産性の向上につながる重要な施策です。
今回ワークライフバランスの取り組みについて紹介するのは、以下の4社です。
・ サイボウズ株式会社
・ 信州ビバレッジ株式会社
・ 株式会社スープストックトーキョー
・ 株式会社資生堂
これらの企業は、独自の制度や取り組みを通じてワークライフバランスの改善に成功しています。例えば、柔軟な勤務時間制度の導入や、休暇取得の促進、育児・介護支援など、様々なアプローチがあります。
ワークライフバランスの取り組みは、単に従業員の私生活の充実だけでなく、企業の競争力向上にも寄与します。優秀な人材の確保や離職率の低下、従業員のモチベーション向上など、多くのメリットがあります。
各企業の具体的な取り組み事例を見ていくことで、自社に適したワークライフバランス施策のヒントを得ることができるでしょう。それぞれの企業がどのような課題に直面し、どのような解決策を講じたのか、その過程と成果に注目することが重要です。
サイボウズ株式会社は、Great Place to Work® Institute Japan(GPTWジャパン)が実施する日本における「働きがいのある会社」ランキングの中規模部門で、2019年には第2位に選ばれている。同社のなかでもユニークな制度が「働き方宣言制度」で、社内のグループウェアで勤務時間を宣言し、自分の働き方を決められるようになっている。
この制度により、社員一人ひとりが自分に合ったワークライフバランスを実現できるようになりました。また、育児や介護などの理由で時間的制約のある社員も、自分のペースで働くことができるようになりました。
サイボウズ株式会社では、ワークライフバランスの改善のために、他にもさまざまな工夫がなされています。例えば、在宅勤務制度の導入や、フレックスタイム制の採用などが挙げられます。これらの取り組みにより、社員の働きやすさと生産性の向上を同時に実現しています。
その結果、2005年には28%だった離職率が、わずか4%前後にまで大幅に減少しました。この数字は、サイボウズ株式会社のワークライフバランス施策が成功していることを示す明確な指標といえるでしょう。
信州ビバレッジ株式会社では、繁忙期と通常期があることや工場の24時間操業などで労働環境が安定せず、残業時間が多い状態であった。そこで週休3日制や残業時間を少なくするなど、年間を通して安定した働き方になるように労働環境の改善に取り組んだ。
この取り組みの結果、従業員が趣味を楽しむ時間が充分に取れるようになり、それが入社を決める理由にもなっている。また、会社は年3回のアンケートを実施し、従業員の声を積極的に聞くことで、継続的な改善を行っている。これらの努力により、ワークライフバランスが向上し、働きやすくて離職率の低い、従業員満足度の高い環境が実現している。
株式会社スープストックトーキョーでは、お客様が温かい気持ちになる接客ができるように、従業員の熱量が上がるような働き方を目指して独自の社内制度づくりをしている。
ワークライフバランスの実現に向けて、年12日の生活価値拡充休暇などを実施し、飲食業ではかなり珍しい年間休日120日取得可能な体制に変革した。また、ピボットワークといった制度も創設し、副業を認めることで意欲ある社員を後押ししている。
これらの取り組みによって、従業員のワークライフバランスが向上し、新卒や中途採用の応募が増え、離職者が減るなどの成果が出ている。さらに、従業員の満足度が高まることで、顧客サービスの質も向上し、企業全体の業績にも好影響を与えている。
スープストックトーキョーの事例は、ワークライフバランスの改善が従業員だけでなく、企業の成長にも寄与することを示す好例といえるだろう。
株式会社資生堂では、ワークライフバランスの実現に向けて、仕事と家庭の両立ができるようにさまざまな支援をおこなっている。もともと女性社員の多さもあって、女性の働き方に関する取り組みが進んでいる企業だ。そのうえで、数が少ない男性社員も制度を利用しやすいように育児休業の取得などを促進し、男女ともに育児に参加しつつキャリアアップもできるような環境を作っている。
具体的には、育児・介護休業制度の充実や、フレックスタイム制度の導入、在宅勤務制度の拡充などを通じて、社員一人ひとりのライフステージに応じた柔軟な働き方を支援している。また、社内保育所の設置や、育児・介護関連の情報提供サービスなど、ワークライフバランスを重視した施策を積極的に展開している。これらの取り組みにより、社員の仕事と生活の調和を図り、多様な人材が活躍できる職場環境の整備に努めている。
関連記事:週休3日制のメリット・デメリットは?導入が進む5つの企業事例もご紹介
ワークライフバランスという概念は広く浸透していますが、リモートワークの普及に伴い、新たな課題や考え方が生まれています。従来のワークライフバランスでは、仕事と私生活を明確に分けることが難しく、両者のバランスを取ることに苦心する人も多くいました。
そこで、リモート時代に適した新しい考え方として、以下の3つが注目されています。
・ ワークライフマネジメント
・ ワークライフインテグレーション
・ ワークライフブレンド
これらの新しい概念は、従来のワークライフバランスの課題を克服し、より柔軟で効果的な働き方を実現することを目指しています。例えば、ワークライフブレンドでは、仕事と私生活を完全に分けるのではなく、うまく融合させることで、両者の相乗効果を生み出すことができます。
リモートワークの増加により、時間や場所の制約が少なくなった今、これらの新しい考え方はより重要性を増しています。企業は従業員のワークライフバランスを支援するだけでなく、個人の主体性や創造性を活かせる環境づくりが求められています。
また、テクノロジーの進化により、仕事と私生活の境界線が曖昧になっている現状も、これらの新しい考え方の背景にあります。スマートフォンやクラウドサービスの普及により、いつでもどこでも仕事ができる環境が整っていますが、同時に常に仕事モードになってしまうリスクも高まっています。
そのため、個人が自律的に時間や労力を配分し、仕事と私生活の質を高めていく「ワークライフマネジメント」の重要性が増しているのです。この考え方は、従業員の自己管理能力を向上させ、結果として生産性の向上にもつながる可能性があります。
ワークライフマネジメントとは、仕事も生活もどちらも成功できるように、積極的にマネジメントしていくという考え方のことです。この概念は、従来のワークライフバランスの考え方を一歩進めたものと言えるでしょう。
もともとワークライフバランスは、ワークとライフのどちらも充実させる考え方でした。しかし、言葉が浸透していくなかで、どちらもほどほどにしようと考える人が出てきてしまいました。本来の「自発的によくしよう」とするものではなく、従業員のために企業がおこなうものであるかのような認知のされ方をするようになってしまったのです。
そのため、仕事と生活のバランスを自らがマネジメントし、生活や仕事の質を主体的に高めていこうとする、ワークライフマネジメントの考え方が生まれました。この考え方では、個人が自身の価値観や優先順位に基づいて、仕事と生活の両立を戦略的に管理していくことが求められます。
ワークライフマネジメントのメリットには、以下のようなものがあります。
・生産性の向上
・優秀な人材が長期間活躍できること
・私生活も仕事も充実できること
・ストレス管理の改善
・キャリア開発の促進
特に、ワークライフマネジメントを実践することで、個人は自身のワークライフバランスを主体的にコントロールし、より効果的に時間とエネルギーを配分できるようになります。これにより、仕事と生活の両面で高いパフォーマンスを発揮することが可能となるのです。
企業にとっても、従業員のワークライフマネジメントを支援することは重要です。従業員が自身の仕事と生活をうまくマネジメントできるようになれば、モチベーションの向上や離職率の低下につながり、組織全体の生産性と競争力の向上に寄与するからです。
このように、ワークライフマネジメントは、個人と組織の双方にとって有益な考え方であり、現代の働き方改革の中で重要な位置を占めています。
ワークライフインテグレーションとは、仕事とプライベートを切り離さずに統合する考え方です。この考え方は、ワークライフバランスの発展形として注目されています。ワークライフインテグレーションのメリットには、メンタルヘルスの維持や生活の質を高める効果、ダイバーシティの環境を実現できることなどがあります。また企業にとっては、生産性の向上や従業員の自己成長につながる効果、企業の業績アップなども期待できます。
ワークライフインテグレーションを実践することで、従業員は仕事と私生活の境界線をより柔軟に捉えることができるようになります。例えば、午前中に子どもの学校行事に参加し、午後から仕事に取り組むといった働き方が可能になります。これにより、個人のライフスタイルに合わせた柔軟な時間管理が実現し、ワークライフバランスの向上にもつながります。
一方で、ワークライフインテグレーションには課題もあります。仕事と生活の切り分けが難しくなり、オフの時間が確保しづらくなる可能性があります。また、従業員の自己管理能力が求められるため、マネジメントが難しくなるというデメリットもあります。そのため、企業はワークライフインテグレーションを導入する際には、従業員のワークライフバランスを考慮しつつ、適切な支援体制を整えることが重要です。
ワークライフブレンドとは、仕事と私生活を切り分けない考え方です。従来のワークライフバランスとは異なり、勤務時間などにとらわれずに自分の裁量で働けるようにするものであり、欧米の企業で採用され始めています。
このワークライフブレンドの考え方は、仕事とプライベートを共存させることで得られるメリットを重視しています。主なメリットは、以下のとおりです。
・自由度が高い
・仕事や私生活を無理せずに両立できる
・仕事や私生活で得られる知識などをどちらにも活かしていける
・アイデアがひらめきやすい
ワークライフブレンドを導入することで、従業員は自分のライフスタイルに合わせて柔軟に仕事と私生活を調整できるようになります。例えば、午前中に子供の学校行事に参加し、午後から仕事に集中するといった働き方が可能になります。これにより、ワークライフバランスの実現が容易になり、従業員の満足度向上にもつながります。
一方で、ワークライフブレンドには以下のようなデメリットもあります。
・制度化が難しい
・各々でのスケジュール管理の重要性が増す
・仕事と私生活の境界が曖昧になりやすい
特に、仕事と私生活の境界が曖昧になることで、労働時間が長くなりすぎたり、プライベートの時間が確保できなくなったりする可能性があります。そのため、ワークライフブレンドを導入する際は、従業員の自己管理能力の向上や、適切な労務管理の仕組みづくりが重要となります。
ワークライフブレンドは、従来のワークライフバランスの概念を一歩進めた考え方であり、多様な働き方を求める現代社会に適した新しいアプローチといえるでしょう。しかし、その導入には慎重な検討と適切な運用が必要です。企業は従業員の well-being を考慮しつつ、ワークライフブレンドの導入を検討することが求められます。
関連記事:自社の離職率は高い?低い?日本の業界別離職率と下げる取り組みを解説
ワークライフバランスとは、「仕事と生活の調和や調整」を意味する。どちらか一方だけではなく、仕事をすることも生活の質も充実させるという考え方だ。
ワークライフバランスがうまくいけば、充実した生活を送ることで仕事がはかどるようになり、それによって私生活も潤うといった相乗効果を期待できる。時間に余裕ができることでスキルアップを図れ、その効果で仕事が効率的に進められるようになるなど、ワークライフバランスによる好循環が見込めるだろう。
日本でワークライフバランスが重視されるようになったことには、以下のような背景がある。
・少子高齢化問題
・団塊世代の大量退職
・共働き世帯の増加
・女性の活躍できる社会への期待
・長時間労働の是正
多くの企業がワークライフバランスの改善に取り組んでおり、その事例としてサイボウズ株式会社や信州ビバレッジ株式会社などが挙げられます。これらの企業では、柔軟な勤務制度や休暇制度の導入により、従業員の満足度向上や離職率の低下などの成果を上げています。
近年では、ワークライフバランスの概念をさらに発展させた新たな考え方も登場しています。例えば、「ワークライフマネジメント」は個人が主体的に仕事と生活のバランスを管理する考え方です。また、「ワークライフインテグレーション」や「ワークライフブレンド」は、仕事と私生活を明確に分けるのではなく、融合させる新しいアプローチです。
これらの新しい考え方は、特にリモートワークが普及した現代の働き方に適していると言えるでしょう。ワークライフバランスの実現は、個人の幸福度を高めるだけでなく、企業の生産性向上や人材確保にも貢献する重要な課題です。今後も、社会の変化に合わせて、より効果的なワークライフバランスの実現方法を模索していく必要があります。

ProFuture株式会社 取締役 マーケティングソリューション部 部長
大手インターネット関連サービス/大手鉄鋼メーカーの営業・マーケティング職を経て、ProFuture株式会社にジョイン。これまでの経験で蓄積したノウハウを活かし、クライアントのオウンドメディアの構築・運用支援やマーケティング戦略、新規事業の立案や戦略を担当。Webマーケティングはもちろん、SEOやデジタル技術の知見など、あらゆる分野に精通し、日々情報のアップデートに邁進している。
※プロフィールに記載された所属、肩書き等の情報は、取材・執筆・公開時点のものです

マーケターが知りたい情報や、今、読むべき記事を発信。Webマーケティングの基礎知識から、知っておきたいトレンドニュース、実践に役立つSEO最新事例など詳しく紹介します。 さらに人事・採用分野で注目を集める「採用マーケティング」に関する情報もお届けします。 独自の視点で、読んだ後から使えるマーケティング全般の情報を発信します。
