ビジネスにおいて、製品開発や業務提携などで他社と重要な機密情報を共有する場面は少なくありません。そうしたシーンで交わされる重要な契約の一つが「NDA(秘密保持契約)」です。
とくにマーケティング部門では、購買や発注のプロセスで他社とNDAを締結する機会が多くあります。そのため、マーケターにとってNDAは必須の知識と言えるでしょう。この記事ではNDAについて、その目的や記載内容、確認すべきポイントなどを詳しく解説します。
人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?
BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!
目次
NDA(秘密保持契約)の基本情報

はじめに、NDA(秘密保持契約)の基本的な情報を確認していきましょう。
NDA(秘密保持契約)とは:片務契約と双務契約がある
NDA(秘密保持契約)とは、企業が他者に開示する秘密情報の取り扱いに関するルールを定めた契約です。自社が保有する生産、販売、製造技術、研究開発データ、顧客の個人情報といった秘密情報について、管理方法や禁止事項を文書化することで、情報漏洩の防止と円滑な協力関係の構築を可能にします。
英語の正式名称は「Non-Disclosure Agreement」で、その頭文字を取ってNDA(エヌディーエー)と呼ばれています。
ビジネスにおいては、自社だけが秘密情報を提供する場合、相手にのみ秘密保持義務を課す「片務契約」を結ぶのが一般的です。一方、お互いに秘密情報を提供し合うのであれば、双方に義務が生じる「双務契約」を締結します。
締結のタイミングは?
NDAは、相手に秘密情報を提供する前に締結することが推奨されます。NDAの締結前に秘密情報を共有してしまうと、情報の流出や意図しない利用のリスクが高まります。さらに、相手がその情報を秘密情報だと認識しておらず、のちのちのトラブルに発展する可能性もあるでしょう。
万が一、NDAの締結前に秘密情報を提供してしまった場合は、できる限り早く契約を締結し、締結前に提供した情報も、さかのぼって秘密情報に含める旨の条項を取り決めるようにしましょう。
NDA(秘密保持契約)を締結する目的

NDA(秘密保持契約)を締結する主な目的は、次の3つです。
秘密情報の流出や悪用を防止できる
NDAを結ぶことで、情報の受領側が秘密情報を第三者に開示したり、不正に利用したりすることを禁止できます。企業同士の取引では、自社の重要なデータを開示しなければならないケースがあるでしょう。しかし、開発中の製品仕様や価格戦略などの情報を開示した結果、受領側から競合他社に漏れてしまえば、大きな損害につながるおそれがあります。
NDAではこうした情報を明確に「秘密情報」と定義し、その取り扱い方法を制限できるため、情報流出や悪用のリスクを未然に防ぐ有効な手段となります。
法律で保護されない情報も守れる
NDAは、法律による保護範囲外の情報も守れる点が特徴です。たとえば、不正競争防止法では「営業秘密」として、顧客リストや営業のノウハウ、製品の技術情報が保護されています。ただし、営業秘密として認められるためには、情報の有用性や管理体制などの各種要件を満たす必要があります。そこでNDAを締結することで、法律だけではカバーしきれない情報についても、「秘密情報」として契約に基づいて保護することが可能になります。なお、NDAに関連する法律は、次の章で詳しく紹介します。
違反時に損害賠償を請求しやすくなる
NDAを締結しておけば、秘密情報の漏洩や不正利用があった際に、損害賠償を請求しやすくなります。仮に秘密情報の流出が発覚しても、契約が存在しなければ法的な責任追及のハードルは高くなるでしょう。NDAにもとづいて「秘密保持義務があった」と証明できれば、損害賠償や差止請求を行う根拠となります。訴訟を起こしたからといって必ず勝訴できるとは限りませんが、NDAがあることで交渉や法的手続きにおいて自社に有利な立場を築くことができます。
▼NDAのメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
秘密保持契約(NDA)とは!締結をする目的やメリット・デメリットを解説
NDA(秘密保持契約)に関する重要な法律

NDA(秘密保持契約)を締結する前に、関連する重要な法律について正しく理解しておく必要があります。NDAに関わる主な法律として、以下3つが挙げられます。
不正競争防止法
不正競争防止法とは、他社の利益を侵害するさまざまな「不正競争行為」を取り締まる法律です。この法律の中でNDAととくに関わりが深いのが「営業秘密の不正利用行為」の禁止です。不正競争防止法が定める営業秘密とは、次の3つの要件をすべて満たす情報とされています。
・秘密として管理されている情報(秘密管理性)
・事業活動に有用な情報(有用性)
・自社以外に一般に知られていない情報(非公知性)
上記すべての要件を満たす他社の営業秘密を不正に利用した事業者は、法的な罰則が科される可能性があります。一方、これらの要件を満たさない情報は営業秘密とみなされず、法律による保護の対象となりません。そのため、NDAを締結する際は、営業秘密に該当しない情報もしっかりと保護範囲に定義することが重要です。
個人情報保護法
個人情報保護法とは、事業者による個人情報の適切な利用・管理について定めた法律です。氏名や住所、メールアドレスといった特定の個人を識別できる情報は、すべてこの法律によって保護されます。
NDAが関係するのは、個人情報を取引先や業務委託先などの他社に共有する場面です。たとえ他社から個人情報が流出したとしても、提供元である自社の社会的信用も揺らいでしまいます。「個人情報保護法があるから相手側も守るだろう」と油断せず、NDAできちんと個人情報の不適切な使用や第三者への開示を禁止するようにしましょう。
特許法
特許法とは、新しい技術的発明に対して、その発明者に一定期間の独占的な権利を与える法律です。特許を受けるためには「進歩性」や「産業で利用可能な技術」などの要件がありますが、その中でもNDAに関する重要な要件が「新規性」です。
特許における新規性とは、出願する技術が世の中にまだ公開されていないことを意味します。たとえば、発明内容を事前に展示会やWebサイトで公表してしまうと新規性が失われ、特許として認められなくなる可能性があります。
そのため、受領側へ特許関連の情報を開示する際には、NDAによってその情報が第三者に漏れる事態を防ぎ、新規性を守り抜くことが非常に重要です。
NDA(秘密保持契約)と似ている用語との違い
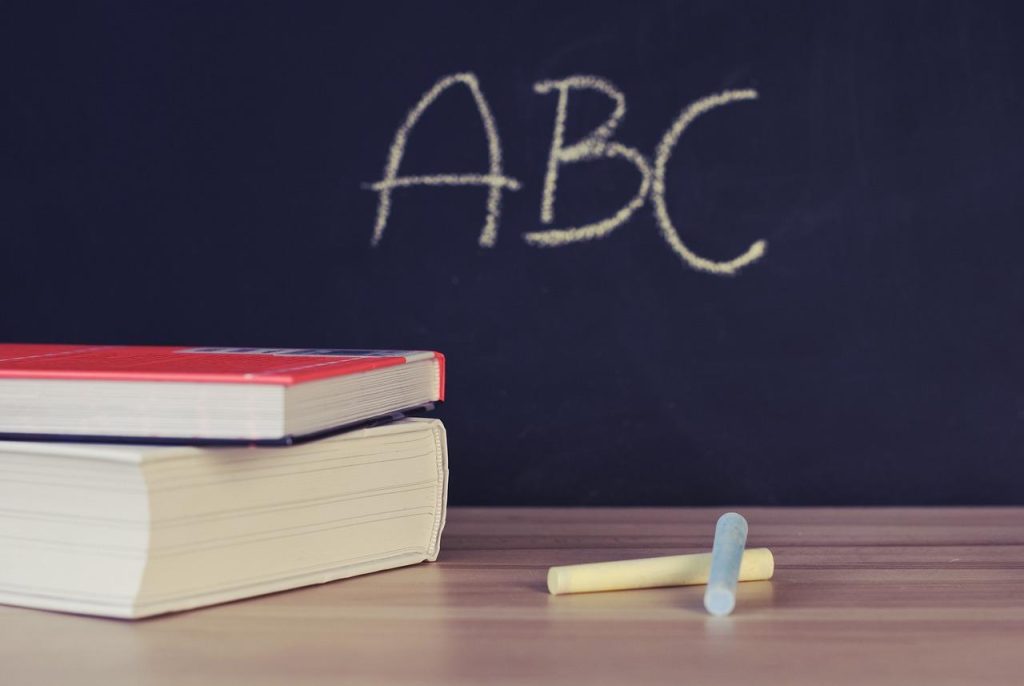
NDA(秘密保持契約)と似た意味で使われる用語に「CA」「CDA」「機密保持契約」の3つがあります。それぞれとNDAとの違いについて見ていきましょう。
CA:M&Aで使用される
CAとは、「Confidentiality Agreement」の略称で、NDAと同じく秘密保持のために結ばれる契約であり、その意味合いや法的な効力も全く変わりません。ただし、CAはM&A(企業の買収・合併)における秘密保持契約を指すケースが一般的です。一方のNDAは特定の場面に限らず、より多様なビジネスシーンで広く使われている用語です。
CDA:評価・検討のための情報開示
CDAは「Confidentiality Disclosure Agreement」の略称です。NDAと同様に秘密保持を目的とした契約であり、基本的には同じ意味と効力を持つ言葉として使われます。
ただしCDAは、とくに企業間で将来的な提携や協業を検討する際に、相手の技術やノウハウなどを評価する目的で情報を開示し合う場面で用いられることがあります。この場合、NDAとCDAは実質的に同じ役割を果たしますが、CDAという名称を使うことで、特定の「開示(Disclosure)」を伴う評価目的の秘密保持契約であることをより明確に示すニュアンスがあります。
機密保持契約:NDAの日本語訳
「機密保持契約」は、日本語における一般的な呼称として、NDAと同じ文書を指す場合があります。NDAの和訳である「秘密保持契約」と同様に、単なる表現の違いであり、契約の内容や法的効力に違いはありません。参考までに、経済産業省管轄の中小企業庁は「秘密保持契約」と表記しています。
参考:中小企業庁「知的財産取引に関するガイドライン・契約書のひな形について」
NDA(秘密保持契約)の締結が推奨される場面

NDA(秘密保持契約)の締結が推奨される代表的なシーンを5つ紹介します。
マーケティングやプロモーションの業務委託
外部の広告代理店やマーケティング会社にプロモーション業務などを委託する際には、NDAの締結が非常に重要です。たとえば、新商品のプロモーションを依頼する場合、商品の仕様、価格、販売戦略、ブランド戦略、ターゲット層など、多くの内部情報を開示する必要があります。こうした情報が競合他社に漏れてしまえば、マーケティング戦略に大きな悪影響をおよぼすおそれがあるため、NDAによって適切な情報管理を求めることが大切です。
製品開発や販売などの業務提携
他社と業務提携するケースでも、NDAの必要性は高まります。共同で製品開発を進める場合や、自社商品を他社の流通網を使って販売する場合など、相手に開示する情報には、自社にとって非常に重要なデータが含まれているでしょう。具体的には、技術仕様書や試作品に関するデータ、製品のプロダクトロードマップ、原価情報、購買履歴、販促企画などが挙げられます。また、提携先の販売活動で顧客情報を扱う可能性もあるため、個人情報保護の観点からも、開示した情報の使用範囲や保管方法、返却・破棄義務を明確に定めておく必要があります。
M&Aや資本提携
M&A(企業の買収・合併)や資本提携を行う際には、経営状況や財務情報、人事体制、顧客リスト、未公開の事業戦略、知的財産など、多岐にわたる経営情報を相手企業に開示することになります。
ここで注意すべきは、M&Aや資本提携の話が進んだものの、最終的に成立しなかったケースです。仮に計画が白紙になったとしても、交渉段階で開示した情報が相手側に残っている限り、適切な契約がなければ不正利用や情報流出のリスクが残ります。
NDAを事前に結んでおけば、上記のようなトラブルを防止できるうえ、万が一の契約違反時にも損害賠償請求などの法的手段に訴える根拠となります。
自社情報を開示する商談
自社が行う商談においても、NDAが必要になる場合があります。たとえば、サービス導入の提案や見積書の作成に際して、自社の製品仕様、価格体系、顧客事例などの機密情報を開示する商談は、NDAの締結が推奨されます。
こうした情報をNDAが未締結のまま相手に渡してしまうと、関係会社への流用や競合企業への情報リークといったリスクが生じる可能性があります。成約前であっても、自社の秘密情報を開示する際は、NDAを交わしたうえで商談を進めることをおすすめします。とりわけ競合の多い業界では、スムーズな秘密保持の取り決めが情報管理リスクの軽減に直結するといえるでしょう。
従業員の雇用契約
従業員を雇用する際にも、NDAは活用されています。従業員が業務の中で知り得た情報を外部に漏らしてしまうと、企業にとって深刻な損害となりかねません。そのため、従業員を採用する際にも、雇用契約と併せて秘密保持契約の締結が推奨されます。製品の技術仕様やソフトウェアのソースコード、営業資料、顧客リストなどの取り扱いについて明確なルールを定めることで、退職後の情報漏洩リスクも抑えることができます。
NDA(秘密保持契約)の契約書に記載する内容
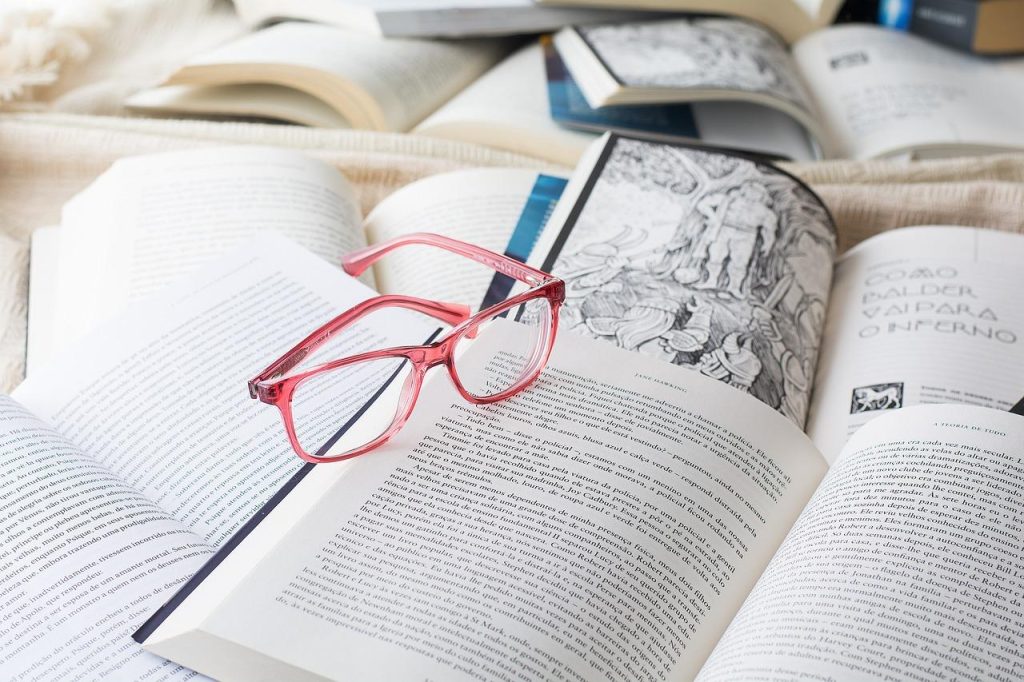
NDA(秘密保持契約)の契約書には、主に次の8つの項目を記載します。
秘密情報の定義
NDAには、どのような情報を秘密情報として扱うのかをはっきりと定義します。秘密情報の定義が曖昧なままだと、トラブルが起きた際に「そもそも開示されたデータは秘密情報ではない」主張され、争いになるリスクがあるからです。
具体的には「秘密情報とは、開示する側が秘密として扱うことを明示した情報を意味する」などと表現するといいでしょう。さらに「技術、営業、販売、顧客に関するデータ」のように、情報の種類を具体的に示すことで、より一層わかりやすくなります。
また、秘密情報から除外するデータがある場合は、その対象も詳しく記載します。
秘密保持義務
秘密保持義務の項目では、秘密情報の扱い方について定めます。秘密情報の管理方法や、開示する側が秘密情報を提供してもいい相手の範囲を明確にしましょう。たとえば、秘密情報を共有できる相手として、子会社や業務委託先、顧問弁護士などが挙げられます。受領する側が例外的に秘密情報を共有できる相手を明確にすることで、秘密情報を有効活用しやすくなります。
利用目的の定義・目的外使用の禁止
NDAを締結する目的には、情報が外部に漏れるのを防ぐだけでなく、不適切な利用を防ぐことも含まれます。そのため、開示された情報をどのような目的で利用していいのかを明確に定義し、さらにその目的以外で使用するのを禁止する必要があります。たとえば、利用目的を「A製品の共同開発に関する協議を行うため」と定め、「本取引における利用目的以外の使用を禁ずる」と記載すると良いでしょう。
制限事項
目的外使用の禁止と合わせて、秘密情報の扱いについての制限事項も定めます。代表的な項目として、秘密情報のコピーや複製についての制限があります。コピーや複製を完全に禁止するのではなく、複製物があった場合の取り扱いについて明確にしましょう。「秘密情報の複製は本取引の利用目的の範囲に限り許可する」「複製物の管理は原本と同等に行う」など、細かいルールを設けることが大切です。
秘密情報の返還や破棄
契約の終了時には、秘密情報を受け取った側にその情報の返還や破棄を求めます。また、契約期間内であっても、開示する側が返還・破棄を要請する場合もあります。秘密情報の返還や破棄を求める際の根拠となるため、この項目は必ずNDAに盛り込みましょう。
廃棄方法については、「電子データは指定のデータ消去ソフトで消去」「紙媒体は溶解処理サービスを利用して廃棄」などと具体的に示します。さらに、返還や廃棄が行われた証拠の提示も求めるとより効果的です。
契約の有効期間
NDAによる契約の有効期間を明確に記載します。一般的には1年から5年とする契約が多く見られます。有効期間中であれば、秘密情報を受け取った側は、NDAで定められた秘密情報の取り扱いを遵守する義務が生じます。開示する側はできる限り長く設定したいと考えるかもしれませんが、有効期間が長すぎると受領する側の負担が必要以上に大きくなってしまいます。そのため、利用目的や情報の性質に合わせて、最適な有効期間を定めることが望まれます。
誠実協議条項
誠実協議条項とは、契約段階で予期していなかった事態が起きた場合や、契約違反の疑いがあった際に、まず当事者間で話し合いによる解決を望む、という決め事です。トラブル時にいきなり法的な措置をとるのでなく、第一段階として交渉の道を残す役割を果たします。この条項があることで、秘密情報の開示・受領の双方にとって、不必要な訴訟リスクを減らす効果が期待できます。
違反時の損害賠償
NDAの取り決めに違反した際の損害賠償について定めます。損害賠償を請求する際の根拠となるため、損害の範囲について明記しましょう。「秘密情報の漏洩により直接発生した損害」「営業活動の停滞や取引停止等による営業上の損失」と詳しく記載し、曖昧な表現は避けましょう。損害の範囲を決めておくことで、違反時の話し合いや訴訟における争点をはっきりさせることができます。
NDA(秘密保持契約)の有効期間と存続条項

前述の通り、NDA(秘密保持契約)を結ぶ際は契約の有効期間を定めます。有効期間を決める際に「存続条項」を設定することで、有効期間を過ぎたあとも一部の取り決めの効力を継続できます。
NDAにおける存続条項とは、有効期間の終了後にNDA全体の効力は失っても、秘密情報の取り扱いに関する一部の義務だけを継続できる規定です。たとえば、「秘密情報の開示および目的外利用の禁止については、契約終了後も3年間有効とする」といった存続条項を設けることができます。自社独自の技術や顧客データなど、長い期間にわたって価値を持つ情報を扱う場合には、この取り決めがとくに重要になります。
NDA(秘密保持契約)の契約書について

続いて、NDA(秘密保持契約)の契約書についての基本的なポイントを確認しましょう。
情報の開示側が文書を作成する
片方だけが秘密保持義務を負う「片務契約」の場合、NDAは秘密情報を開示する側が作成します。双方が秘密情報を提供し合う「双務契約」であれば、より多くの秘密情報を開示する側が中心となって作成するのが一般的です。
どちらの契約形式であっても、秘密情報の開示によって情報漏洩などのリスクを負う側が、自身に不利益が生まれないよう、最適な規定を作るために主導権を握ります。ただし、法的なルールがあるわけではないため、秘密情報を受領する側が文書を作成するケースもあります。
紙媒体または電子契約を選ぶ
NDAの契約書は、紙媒体でも電子媒体でも作成に問題はありません。紙媒体の場合は、契約を主導する側が社内で契約書類を作成し、相手に郵送または持参して署名・捺印をもらう必要があります。
電子媒体であれば、電子文書で作成したNDA契約書をシステムなどにアップロードして、相手に電子署名をもらいます。電子契約の場合、何ページにもわたる契約書であっても、紛失する心配がありません。また、検索性も高いため、管理のしやすさを重視するならば電子契約のほうが適しています。
収入印紙は不要
NDAの契約書は印紙税法における課税対象の文書ではないため、収入印紙は不要です。ただし、ほかの課税文書の中にNDAが含まれていたり、反対にNDA契約書の中に課税対象となる契約が含まれたりする場合は、収入印紙が必要になる可能性があります。課税対象の契約文書の例としては、請負契約や合併・吸収契約などが該当します。
NDA(秘密保持契約)の締結前に確認すべきチェックポイント
NDA(秘密保持契約)を締結する前に、以下の4つのポイントを必ず確認しましょう。
違反時の損害額を決めているか
NDAの契約に違反した場合の損害賠償の金額は、あらかじめ契約書に明記しておきましょう。訴訟で損害賠償の金額を認めてもらうためには、契約違反の事実と、その違反によって発生した損害額を証明しなくてはなりせん。
「怪我をさせた」「設備を壊した」といった物理的な損害に比べて、秘密保持契約の契約違反行為と損害額の因果関係を証明することは難しい傾向にあります。そのため、あらかじめ契約違反時の損害金額を決めておくことで、契約違反の事実さえ証明できれば、損害額の証明は不要になります。
秘密情報を扱う業務の委託範囲は適切か
秘密情報を扱う業務を外部に委託する場合、必要以上に委託する範囲を広げないように注意することが必要です。
まずは、NDA締結が必要な情報を開示するリスクと、業務委託で得られる効果を慎重に検証してみてください。リスクよりも効果が上回る場合にのみ、業務委託を選択することをおすすめします。
第三者へ委託する部分を不必要に広げないことで、万が一の情報漏洩などのリスクを抑えることができます。
秘密情報の利用目的は明確か
NDAにおける秘密情報の利用目的がはっきりしない場合、「目的外利用の禁止」の条項がきちんと機能しません。当事者間で秘密情報の解釈が異なってしまうと、秘密情報の受領側が悪意なく契約目的に含まれない使い方をしてしまう危険性があります。また、利用目的が曖昧な文書では、契約違反による損害賠償請求の根拠とならない可能性も考えられます。
NDAを作成する際は、秘密情報の利用目的を明確に決めることが重要です。
契約内容を確認しているか
NDAの契約文書は秘密情報を開示する側が主導して作成するのが一般的ですが、秘密情報を受領する側も内容をきちんと確認する必要があります。受領側が秘密情報の定義や利用目的、求められる管理体制を把握していなければ、意図しない情報の漏洩や不正利用のリスクが高まってしまうためです。
加えて、違反時のペナルティについても認識することで、秘密保持義務を守る意識を持ちやすくなるでしょう。
第三者へ秘密情報を提供する際はNDA(秘密保持契約)を締結しよう
ビジネスにおいては、さまざまな場面でNDA(秘密保持契約)を締結する機会があります。技術データ、営業ノウハウ、販促情報、顧客リストといった自社の秘密情報を第三者に提供する場合、情報漏洩や意図しない利用を極力防がなくてはなりません。NDA(秘密保持契約)を締結することで、自社の重要な情報を守りやすくなります。
NDAは従業員の雇用やマーケティング活動を行う際にも重要な契約です。人事・労務などのHR領域にも関わるため、充分な知識が求められます。他社へHR領域のマーケティング支援を求める場合、NDAについて正しく理解しておくことが大切です。
▼HR領域のマーケティング支援が可能なポータルメディア「HRプロ」はこちら
https://www.profuture.co.jp/mk/solution/248

