インフルエンサーとは、人々に影響を与え、行動や意識の変化を促す人物のことです。
マーケティングや広報・PRに関わるビジネスパーソンにとって、認知拡大や購買促進の観点から、基本知識として理解しておくべき存在といえます。
一方で、「フォロワー数が多ければインフルエンサー」と誤解されたり、「芸能人との違いが不明」といった認識の曖昧さも見受けられます。また、SNSごとの特性や戦略が十分に理解されていないケースも少なくありません。
本記事では、インフルエンサーの定義から、フォロワー数別の分類、SNSごとの特徴、収益モデル、起用の流れ、活用のポイントまでを幅広く解説します。
人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?
BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!
目次
インフルエンサーとは? 定義・語源

インフルエンサーと聞くと、世間では多くのフォロワーを持つSNSユーザーを想像しがちですが、本質は「影響を与える人」を指します。
語源の“Influence”が示すように、行動や購買に影響を与える存在であり、必ずしも著名人である必要はありません。特定分野で発信力を持つ一般ユーザーも同じように注目されています。
また、混同されやすい存在に「アンバサダー」があります。
アンバサダーは企業と契約し、ブランドの顔として中長期的に発信するのに対し、インフルエンサーは個人として短期・単発で活動するのが一般的です。
ただし、両者の境界は曖昧で、インフルエンサーがアンバサダーを兼ねる例も増えています。
▼アンバサダーについては、こちらの記事もぜひあわせてご覧ください。
アンバサダー(Ambassador)とは?アンバサダーマーケティングの意味や事例
インフルエンサーが注目される背景
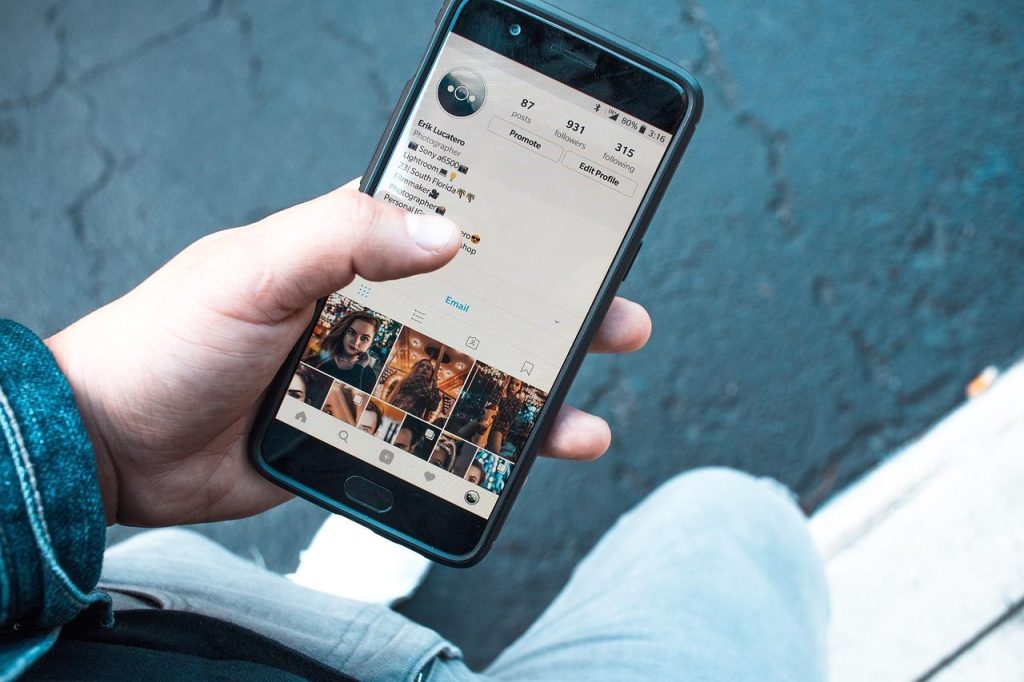
ここでは、インフルエンサーが注目される3つの理由を見ていきます。
SNS利用者拡大とUGC信頼性向上
インフルエンサーが注目される最大の理由は、SNSが生活インフラとして定着したことにあります。
総務省の調査では、国内のSNS利用状況は約8割に達しており、全年代で利用が拡大しています。
この中で、企業広告よりも、消費者同士のレビューや体験談といったUGC(User Generated Content)への信頼が高まりつつあります。
第三者のリアルな声は本音として受け取られやすく、購買の後押しになるケースも増えています。
こうしたUGCを安定的に生み出す存在として、インフルエンサーの価値が再び見直されているのです。
▼UGCについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
UGCとは?今注目されている理由と具体的な手法を徹底解説
広告効率・リーチ単価の改善ニーズ
インフルエンサー施策は、広告効率を高める手段としても注目されています。
デジタル広告費の高騰やCookie規制によるターゲティング精度の低下を背景に、1フォロワーあたりのリーチコストが低いインフルエンサーは、費用対効果の面で優れています。
また、投稿は一過性で終わらず、ハッシュタグや検索から継続的に閲覧されます。資産型コンテンツとしても機能するため、コンテンツマーケティングに活用できます。
リーチだけでなく、エンゲージメントや信頼性も担保できる点から、SNSに強い業界では広告出稿よりも優先されるケースが増えています。
関連記事
・SNSとは?2025年版の最新一覧:種類・特徴・目的別に徹底比較
・リーチとは?インスタや広告での意味と向上させる方法
・エンゲージメントとは?マーケティングにおける意味合いを徹底解説
・SNSのハッシュタグ検索をマーケティングに活用! 検索ツールの使い方
・コンテンツマーケティングとは?基本的な概念から実践までを解説します
Z世代を中心とした情報取得行動の変化
最後に注目すべきは、Z世代の情報取得スタイルの変化です。
彼らはGoogle検索よりもInstagramやTikTokで検索し、YouTubeのレビューで商品の実態を確認するなど、共感できる個人の言葉を重視する傾向が強まっています。
簡単に言えば、SNSは単なるコミュニティ以上の役割を担っているのです。
「#使ってみた」「#本音レビュー」などの投稿からリアルな使用感を把握し、それをそのまま購買判断につなげる流れが定着しつつあります。
企業広告よりも、信頼するインフルエンサーの推薦が最大の決め手となっているのです。
▼「Z世代」の意味については以下の記事で解説しています。
Z世代とは何歳でなぜZ?特徴、X・Y世代との違いを簡単に解説
インフルエンサーの4分類(フォロワー規模)

インフルエンサーと一口にいっても、その影響力の大きさや役割は千差万別です。
ここでは、現在一般的に使われている4つのカテゴリーを紹介し、それぞれの特性について簡潔に整理します。
メガ/トップインフルエンサー(100万+)
国内外で高い知名度を持つ著名人や有名クリエイターは、テレビや雑誌などSNS以外でも露出が多く、大規模キャンペーンやブランド認知の加速に適しています。
ただし、投稿単価が高額であるうえ、商材との親和性によってはフォロワーとの乖離が生じるリスクもあるため、企業側にはブランディング重視の慎重な投資判断が求められます。
ミドルインフルエンサー(10万〜100万)
ジャンル特化型の発信を行いながら、一定のファンベースを築いている中堅層のインフルエンサーです。
料理、ファッション、美容、育児、ビジネスなど、それぞれの専門性において高い信頼を獲得している点が特長です。
エンゲージメントとリーチのバランスがよく、プロモーションと販促の両立を図る施策に適しています。
マイクロインフルエンサー(1万〜10万)
フォロワーとの距離が近く、日常の延長で共感を呼ぶ発信を行う層です。
UGCの生成力が高く、コンバージョンに直結する施策や地域密着型のキャンペーンに活用されるケースが増えています。
投稿単価も比較的低コストなため、複数人への依頼による「面展開」がしやすく、近年ではD2Cブランドやスタートアップ企業に人気のカテゴリです。
関連記事:市場規模が拡大する「Electronic Commerce(EC)」とは?注目のビジネスモデルD2Cについても解説
ナノインフルエンサー(〜1万)
もっとも小規模なフォロワーベースながら、熱量の高いコミュニティを形成しているのがナノインフルエンサーです。
身近な友人や知人との関係性を基盤とし、信頼に基づいた推奨が大きな影響力を持つため、信頼性を重視したマーケティング施策に向いています。
また、企業の社員や既存顧客をナノインフルエンサー化するブランドアンバサダー戦略にも通じる要素があるといえるでしょう。
主要SNS別インフルエンサーの特徴

以下に主要SNSの特徴を整理します。
Instagramインフルエンサー
Instagramは、写真や動画などのビジュアル訴求に強みを持つSNSです。
ストーリーズやリールを活用した短尺動画、世界観を統一したフィード投稿によって、ブランドイメージを直感的に伝えられます。
Z世代〜30代女性を中心に購買検討層が多く、ECやD2C商材との相性が良好です。
X(旧Twitter)インフルエンサー
速報性と拡散力に優れたプラットフォームで、テキストベースの気軽な発信が可能です。
IT・ビジネス領域、サブカルチャー、ニュース系などのインフルエンサーが活躍しており、BtoBや知的関心の高いユーザーへのアプローチにも適しています。
リツイートによる二次拡散も期待でき、トレンド形成力がある点も強みです。
TikTokクリエイター
エンタメ性とショート動画による爆発力が特徴のTikTokでは、若年層を中心に新たなトレンドが次々と生まれています。
「音楽」「動き」「編集」が融合した動画は、視覚と感情に強く訴えかけるため、認知拡大フェーズの施策に効果的です。
さらに、AIによるレコメンド機能により、フォロワー数に関係なくバズが起きやすい点も大きな魅力です。
YouTubeクリエイター
長尺動画による深いコンテンツが特徴のYouTubeは、商品レビューや体験コンテンツ、Vlog型のストーリーテリングに優れています。
視聴時間が長いため、ブランドストーリーの訴求や比較検討段階のユーザーへのアプローチに向いており、BtoCにとどまらずBtoB領域でも活用例が増えています。
インフルエンサーの主な収益モデル

ここでは、インフルエンサーの代表的な5つの収益モデルを紹介します。
PR投稿・タイアップ
企業から依頼を受け、商品やサービスの宣伝を行う最も一般的な収益モデルです。
近年ではステルスマーケティング対策として「#PR」などの明示が法的に義務づけられており、信頼性と透明性の両立が重要視されています。
関連記事:ステマ(ステルスマーケティング)とは?意味や規制、事例を簡単に
▼タイアップ広告についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
タイアップ広告のメリットと進め方
アフィリエイト/プロモコード
インフルエンサー自身が紹介した商品が購入・申込された際に成果報酬を得るモデルです。
アフィリエイトリンクや限定のプロモコードを通じてトラッキングが可能で、フォロワーとの相互信頼が強いほどコンバージョン率も高まる傾向があります。
▼アフィリエイトについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
アフィリエイトとは?仕組みと始め方や収益化のポイント
自社ブランド・ライブコマース
一定のフォロワー規模と影響力を持ったインフルエンサーは、自身のブランドを立ち上げてEC販売を行うケースも増えています。
サブスク・オンラインサロン
コンテンツやコミュニティへの定期課金を収益源とする形も浸透しつつあります。
ノウハウ発信、限定配信、直接交流といった「クローズドな価値」を提供することで、ファンとの関係性を深化させながら、安定収入を得られる点がメリットです。
講演・書籍化など多角展開
発信を続ける中で培った知見やブランド力を活かし、出版、講演、テレビ出演、コンサルティングといったオフライン領域に進出するインフルエンサーも増えています。
インフルエンサーになる方法

いまや影響力は一部の著名人だけのものではなく、誰もが築ける時代です。とくに広報・マーケティング担当者にとって、自らが影響力を持つことは大きな強みになります。
以下がインフルエンサーになる主な手順です。
1. 発信テーマを明確にする
2. ターゲットを具体化する
3. 最適なSNSを選ぶ
4. 無理なく継続する
5. 投稿の分析と改善をする
インフルエンサーを目指すうえでは、自己表現だけでなく、フォロワーに価値を届けるマーケットイン型の思考が重要です。
フォロワーの課題やニーズを把握し、自身がどのような価値を届けられるのかを考えたうえで、継続的な発信に取り組みましょう。
▼マーケットイン型の思考については、こちらの記事で深掘り解説を行っています。
マーケットインとはどんな考え方・手法? プロダクトアウトとの違いやメリットなど事例を用いながら解説
インフルエンサーマーケティングのメリットとデメリット

ここでは、インフルエンサーマーケティングの代表的なメリットとデメリットについて整理します。
メリット
インフルエンサー施策の最大の魅力は信頼性です。
企業の広告とは異なり、本人の言葉で語られる紹介は「身近な人のおすすめ」として受け取ってもらうことが可能で、購買やシェアといった行動につながりやすくなります。
また、ターゲティング精度の高さも特徴です。
たとえば育児系なら子育て世代、美容系なら20〜30代女性など、自然にセグメントされた層へリーチできます。
結果として、高いコンバージョン率を生むこともあります。
さらに、インフルエンサーの投稿は先述のUGCとしても活用可能です。
デメリット
インフルエンサー施策の最も大きなリスクは炎上で、投稿内容が誤解を招いたり、過去の発言が問題視されたりすることで、ブランドへの批判に波及する可能性があります。
特にSNS時代は拡散速度が速いため、起用前のチェック体制を厳格に整えることが不可欠です。
また、不透明な投稿が「ステルスマーケティング」と受け取られるリスクもあります。
広告であることを明示しないまま発信すると、フォロワーの不信感を招き、ブランドの信頼性を損なう恐れがあります。
さらに、施策の効果測定が難しい点も課題です。売上への直接的な貢献が見えにくいため、KPI設計や検証体制が曖昧だと、投資対効果の判断が困難になります。
▼企業が行うべき炎上対策は以下の関連記事をご覧ください。
ポリコレの意味とは?マーケ・広報・人事が企業活動で炎上しないためのポイントを解説
インフルエンサーマーケティングの手順

インフルエンサーマーケティングの手順を5つのステップにわけて解説します。
①目的・KPI設定
まず行うべきは目的の明確化です。
認知拡大、EC流入、店舗送客、ブランディング強化など、目的に応じて起用すべきインフルエンサーのタイプも異なります。
また、リーチ数・保存数・クリック数・CV数などのKPIを事前に設定することで、施策全体の判断基準が明確になります。
関連記事:KPIの意味とは?初心者にもわかる徹底解説と設定事例
②候補抽出・指標
目的が定まったら、実際に起用するインフルエンサーを選定します。
フォロワー数だけではなく、エンゲージメント率、投稿ジャンル、過去のタイアップ実績、フォロワー属性などを総合的に評価するようにしましょう。
③オファー・契約
候補が決まったら、依頼内容や報酬条件、投稿本数、掲載期間、画像の二次使用許諾などの一覧を明記したオファー文を送ります。
その後、インフルエンサーまたは所属事務所と契約書を取り交わし、法令やステマ対策に配慮した形で合意を形成します。
④コンテンツ企画
インフルエンサーの投稿は単なる広告ではなく、フォロワーに自然に届くコンテンツにしなければいけません。
ブランドから一方的に指示するのではなく、インフルエンサー本人の表現力を尊重し、共同で企画をつくる姿勢が成果を左右します。
⑤効果測定&PDCA
施策実施後は、事前に設定したKPIと照らし合わせながら成果を分析します。
その結果をもとに、今後のインフルエンサー選定基準やクリエイティブ改善案を導き出し、PDCAを回すことで施策の精度を高められます。
インフルエンサーと関連法律

ここでは、インフルエンサーマーケティングをするうえで、必ず押さえておきたい2つの法的ルールについて解説します。
景品表示法・薬機法
景品表示法とは、消費者の誤認を防ぐための法律で、インフルエンサーによるPRにも適用されます。
「飲むだけで痩せる」「絶対に効果がある」といった根拠のない表現は、優良誤認にあたる可能性があり注意が必要です。
加えて、健康食品や化粧品、医薬部外品を扱う際には、薬機法にも注意が必要です。
医薬品でない商品に対し「病気が治る」「医師が推奨」といった表現は禁じられており、違反すれば販売元だけでなく投稿者も責任を問われる可能性があります。
投稿文だけでなく、画像・ハッシュタグ・ストーリーまで含めた表現全体に配慮が求められます。
▼景品表示法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
景品表示法を基礎からわかりやすく解説:違反事例から学ぶ適切な広告の秘訣
#PR表示義務
消費者庁は2023年に「広告であることの明示義務」をガイドライン化しました。
報酬を受け取って投稿する際は、「#PR」や「#広告」などを使い、フォロワーに明確に広告と認識させる必要があります。
表記は投稿内の目立つ位置に配置する必要があり、コメント末尾などに埋もれる形では不十分です。
とくにショート動画では、画面上でしっかり視認できるかが重要視されます。
インフルエンサーマーケティングの成功ポイント

ここでは、インフルエンサーマーケティングを成功に導くうえで押さえておきたい3つのポイントを紹介します。
フォロワー数だけで選定しない
インフルエンサーをフォロワー数だけで選定するのは、よくある失敗のひとつです。数が多ければリーチは広がりますが、エンゲージメントが低ければ反応は期待できません。
むしろ、マイクロインフルエンサーやナノインフルエンサーのように、フォロワー数は少なくても関係性が深い層のほうが、コンバージョン率やロイヤリティの向上に貢献するケースが多く見られます。
自社と関連性の高いインフルエンサーを選定する
インフルエンサーの世界観や発信内容が、自社ブランドとどれほど親和性があるかは、成果を大きく左右します。
たとえば、高級志向のブランドが庶民派インフルエンサーを起用すれば、イメージのズレを招く結果になるでしょう。
過去の投稿やファン層、価値観の一貫性を事前に確認することで、自然で説得力のある発信が実現できます。
企画力をチェック
フォロワーとの関係を築いてきたインフルエンサーは、情報発信者であると同時に優れたクリエイターでもあります。
そのため、企業が一方的に指示するのではなく、インフルエンサーの視点や表現力を活かした企画設計が重要です。
インフルエンサーに関するよくある質問

ここでは、企業担当者から特によく寄せられる質問8項目に対して、端的に答えを整理しました。
インフルエンサーは何をする人ですか?
SNSやブログなどを通じて、多くの人に影響を与える個人のことです。
「ブログ」に関連する記事:【超入門】「ブログって何?」から始める企業ブログ~若手社員のための法人ブログ設計・運用ガイド~
誰でもインフルエンサーになれますか? 必要条件は?
発信ジャンルとターゲットを明確にし、継続的な投稿とフォロワーとの信頼関係を築ければ、一般の人でもインフルエンサーになることは可能です。
インフルエンサーの主な収入源は何ですか?
企業とのタイアップ投稿、アフィリエイト、自身のブランド販売、講演、オンラインサロンなど複数の収益モデルを組み合わせることが一般的です。
関連記事
・アフィリエイトとは?仕組みと始め方や収益化のポイント
・オンラインサロンとは?実は簡単だった作り方から運用方法のポイントまで解説
企業がインフルエンサーを起用するメリットは?
信頼性の高い訴求ができる、ターゲット層にダイレクトに届く、UGCとして再利用できるなど、広告にはない独自の効果が期待できます。
効果測定はどう行いますか? 主要KPIは?
リーチ数、クリック数、保存・シェア数、CV数、エンゲージメント率などが主要KPIです。目的に応じて数値と定性両面で分析します。
#PR表記など法規制・ステマ対策は必要ですか?
報酬が発生する投稿には「#PR」などの明示が法的に義務づけられています。違反すると企業とインフルエンサー双方にリスクが及びます。
インフルエンサー施策でよくある失敗と回避策は?
フォロワー数だけで起用し、ターゲットや表現がずれるケースが多いです。事前のチェックと綿密なすり合わせでの防止が有効です。
フォロワー数よりエンゲージ率が大事と言われる理由は?
実際に反応し、行動を起こすフォロワーの割合が高いほど、PRの説得力が増します。見られるだけの投稿では成果につながりません。
まとめ:インフルエンサーを活用して効果的にPRしよう
インフルエンサーは今や、単なるSNSの有名人ではなく、消費者の意思決定に影響を与える企業マーケティングに欠かせない存在です。
フォロワー数に関係なく、共感性の高い発信力があれば十分に成果を上げられます。
信頼を基盤にしたパートナーシップが、長期的な成果をもたらすでしょう。
SNS活用に加え、HR専門領域に特化したマーケティング支援を検討している場合、「HRSEO」や「HRプロ」といったソリューションも視野に入れてみてください。
▼ProFutureのマーケティング支援ソリューションはこちらからご覧いただけます。
https://www.profuture.co.jp/mk/solution/248
https://www.profuture.co.jp/mk/solution/3040

