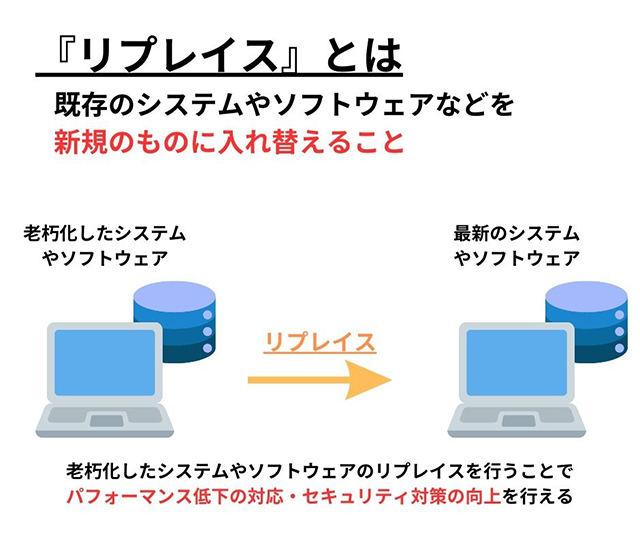「リプレイス」という言葉をご存知でしょうか。ITの分野で広く使用される用語であり、既存のシステムやソフトウェアなどを新しいものに入れ替える作業のことを指します。例えば、企業などでセキュリティ強化を目的として、既存のものとは異なるシステムを導入する際にリプレイスが活用されることがあります。
一般的にはあまり知られていない言葉かもしれませんが、現代ではITが急速に発達していることもあり、システムの最新化やセキュリティ対策の強化など、様々な場面でリプレイスが実施されています。特に、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進に伴い、多くの企業がリプレイスを検討しています。
リプレイスは、企業のIT基盤を刷新し、業務効率化やコスト削減、競争力強化につながる重要な取り組みです。しかし、適切な計画と実行が求められるため、リプレイスプロジェクトを成功させるには専門知識と経験が必要です。
本記事では、リプレイスの概要や実施する目的、実際に行う際の進め方などを詳しく解説していきます。また、リプレイス戦略の立て方や、リプレイス時に注意すべきポイントについても触れていきますので、IT担当者や経営者の方々にとって参考になる情報をお届けします。
人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?
BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!
目次
リプレイスとは
「リプレイス」という言葉をご存知でしょうか。ITの分野で広く使用される用語であり、既存のシステムやソフトウェアなどを新しいものに入れ替える作業のことを指します。例えば、企業などでセキュリティ強化を目的として、既存のものとは異なるシステムを導入する際にリプレイスが活用されることがあります。
一般的にはあまり知られていない言葉かもしれませんが、現代ではITが急速に発達していることもあり、システムの最新化やセキュリティ対策の強化など、様々な場面でリプレイスが利用されています。特に、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進や、クラウドコンピューティングへの移行などの文脈で、リプレイスの重要性が高まっています。
リプレイスは、企業のIT戦略において重要な役割を果たします。例えば、老朽化したシステムをリプレイスすることで、業務効率の向上やコスト削減、さらにはビジネスの競争力強化にもつながる可能性があります。また、セキュリティリスクの軽減や、新しい技術の導入による革新的なサービスの創出なども、リプレイスの重要な目的となります。
本記事では、リプレイスの概要や実施する目的、実際に行う際の進め方などを詳しく解説していきます。IT環境の変化が激しい現代において、リプレイスの重要性を理解し、適切に実施することは、企業の持続的な成長と発展に不可欠です。
既存のシステムやソフトウェアなどを新規のものに入れ替えること
リプレイス(リプレース)とは、既存のシステムやソフトウェアなどを新規のものに入れ替える作業のことを指します。「replace」は英語で「新しく交換する」「置き換える」などの意味を持つ言葉です。リプレイスは、問題を抱えていたり老朽化したりしているシステムなどの一部または全体を、新しいものに置き換えることを意味します。
ITの分野で広く使用されるこの概念は、企業のデジタル化やDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する上で重要な役割を果たします。例えば、セキュリティ強化を目的として、既存のものとは異なるシステムを導入する際にリプレイスが活用されることがあります。
現代ではITが急速に発展しているため、システムの最新化やセキュリティ対策の強化など、様々な場面でリプレイスが必要とされています。特に、クラウドコンピューティングの普及により、オンプレミス環境からクラウド環境へのリプレイスも増加しています。
リプレイスを実施する際は、単に古いものを新しいものに置き換えるだけでなく、業務プロセスの見直しや効率化、新技術の導入なども同時に検討することが重要です。これにより、企業の競争力向上やコスト削減、業務効率化などの様々なメリットを得ることができます。
「マイグレーション」との違い
関連する言葉として「マイグレーション」という言葉があります。マイグレーション(migration)は、英語で「移住」「移転」などの意味を持つ言葉で、既存のシステムやデータなどを別の環境に移転したり、新しいプラットフォームに移行したりすることを意味します。
リプレイスとマイグレーションの主な違いは、変更の範囲にあります。マイグレーションは既存のシステムなどを新しいプラットフォームやシステムに移行するといったように基盤ごと変更を行いますが、リプレイスは問題を抱えているシステムなどを新しいものに置き換えるだけで、プラットフォームなどの基盤となる部分までは変更を行いません。
具体的な例を挙げると、故障や破損など劣化したため同一の新規のソフトウェアを導入する場合はリプレイスでの対応となります。一方、旧式のシステムを最新版にする場合や新技術導入のために新しいプラットフォームへの移行を行う場合などはマイグレーションでの対応となります。
リプレイスは、既存のシステム構成を維持しつつ、特定の部分を新しいものに置き換えることで、運用の継続性を保ちながら改善を図ることができます。一方、マイグレーションは、より大規模な変更を伴い、システム全体の刷新や新しい技術の導入を目的とすることが多いです。
企業がITシステムの更新を検討する際は、リプレイスとマイグレーションの特徴を理解し、自社の目的や状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。リプレイスは比較的短期間で実施できる一方、マイグレーションはより長期的な計画と準備が必要となる場合が多いため、プロジェクトの規模や期間も考慮に入れる必要があります。
関連記事:Google BigQueryとは?特徴を分かりやすく解説!
リプレイスを実施する目的
既存のシステムやソフトウェアなどを新規のものに交換する作業を行うことには、Webを活用してビジネスを行う人たちにとって大きなメリットがあるため、目的を持って実施しています。主な目的としては以下の5つがあげられます。
● パフォーマンス低下への対応
● システム老朽化への対応
● システムのブラックボックス化への対応
● セキュリティ対策の向上
● 新技術の導入
これらの目的は、企業のIT環境を最適化し、業務効率を向上させるために重要です。例えば、パフォーマンス低下への対応では、データ処理能力の向上やレスポンス時間の短縮が期待できます。また、システム老朽化への対応により、故障リスクの軽減や保守性の向上が図れます。
セキュリティ対策の向上は、近年特に重要性が増しています。サイバー攻撃の脅威が日々進化する中、リプレイスによって最新のセキュリティ機能を導入することで、企業の重要データを守ることができます。
さらに、新技術の導入は、企業の競争力強化につながります。例えば、AIやIoTなどの先端技術を活用したシステムへのリプレイスにより、業務プロセスの自動化や意思決定の迅速化が可能になります。
リプレイスを実施する際は、これらの目的を明確に定義し、優先順位をつけることが重要です。また、リプレイスの規模や方法を適切に選択することで、コストと効果のバランスを取ることができます。企業の現状と将来のニーズを見据えた上で、戦略的にリプレイスを計画・実行することが、長期的な成功につながるでしょう。
パフォーマンス低下への対応
自社の事業が発展したり、顧客が増えたりしていくことにより、データはどんどん蓄積されて膨大になっていきます。システムが古いままだと、その膨大なデータにシステムが耐え切れず、データを処理しきれなくなったり、動作が重くなったりしてしまうなどのトラブルが発生する恐れがあるのです。トラブルが起きてパフォーマンスが下がってしまうことで、自社の従業員の作業効率なども低下してしまうことに繋がります。パフォーマンスの低下を事前に防ぐためにも、リプレイスを行って、処理能力に問題はないか配慮することが大切です。
リプレイスによるパフォーマンス向上は、ビジネスの継続性と競争力の維持に不可欠です。例えば、顧客管理システムのリプレイスを行うことで、データ処理速度が向上し、顧客対応の迅速化につながります。また、社内の業務システムをリプレイスすることで、従業員の生産性が向上し、業務効率が大幅に改善される可能性があります。さらに、Webサイトやeコマースプラットフォームのリプレイスは、ユーザー体験の向上やコンバージョン率の改善につながり、売上増加に寄与する可能性があります。
リプレイスを検討する際は、現在のシステムのパフォーマンス指標を明確に把握し、新システム導入後の目標値を設定することが重要です。また、リプレイス後の運用コストや保守性も考慮に入れ、長期的な視点でパフォーマンス向上の効果を評価することが求められます。
システム老朽化への対応
システムなどは使用年数を重ねることで、データ使用容量が不足し、処理能力が低下していくケースもあります。そのような老朽化に伴って、システムの作業パフォーマンスの低下を改善させる目的もあります。
国税庁が定める税法上、一般的にサーバーなどの機器は耐用年数が5年、パソコンが4年、購入したアプリケーションソフトが5年と定められています。そのため、5年以内を目安にリプレイスするケースが多いです。また、ソフトウェアなどには、メーカーによるサポート期限も設定されていることが多く、通常はサポート期限が終了するのにリプレイスを実施することが多いです。
老朽化してしまったハードウェアやソフトウェアについては、社内でメンテナンスできる人材も限られるため、早急にリプレイスを検討することをおすすめします。対応できる人材が少ないなどの理由で老朽化の問題を後回しにしておくと、プラットフォームなどシステムを提供している会社のサポートが終了するなどの問題も発生する可能性があるため、注意が必要です。
リプレイスを実施することで、最新のテクノロジーを導入し、業務効率化やコスト削減にもつながります。また、セキュリティリスクの軽減や、新しい機能の追加による競争力の向上も期待できます。定期的なリプレイスは、企業のITインフラを最適な状態に保つための重要な施策といえるでしょう。
システムのブラックボックス化への対応
長年使用しているシステムなどは、カスタマイズなどを繰り返すうちに内部構造が複雑になり、ブラックボックス化してしまうことがあります。このブラックボックス化は、リプレイスを実施する重要な理由の一つとなっています。
ブラックボックス化とは、システムの内部構造が不明瞭になってしまっているため、改修が必要であっても手をつけることができず、不明瞭な状態で運用し続けているシステムのことをいいます。自社でシステムの導入や管理に携わっていた技術者が退職してしまうことで、それらの中身が分かっている人材がおらず、ブラックボックス化してしまうというケースも少なくありません。
ブラックボックス化したシステムは、以下のような問題を引き起こす可能性があります。
●メンテナンス困難:システムの内部構造が不明確なため、必要な修正や更新が難しくなります。
●セキュリティリスク:脆弱性の特定や対応が困難になり、セキュリティ上の問題が生じる可能性があります。
●業務効率の低下:システムの非効率な部分を改善できないため、業務プロセスの最適化が阻害されます。
ブラックボックス化してしまっているものをどうにか改善しなければいけないと分かってはいるものの、不明瞭なものを変に改善してしまい、全体的なシステムに悪影響を与えてしまう恐れがあるため手をつけづらいものです。そのような理由から、サポート期限の終了にあわせてリプレイスを実施する企業も多いと考えられます。
リプレイスを行うことで、ブラックボックス化したシステムを新しい、透明性の高いシステムに置き換えることができます。これにより、システムの管理や改善が容易になり、長期的な運用コストの削減にもつながります。また、新しいシステムでは最新の技術やセキュリティ対策を導入することができ、より効率的で安全な業務環境を構築することが可能となります。
セキュリティ対策の向上
古いソフトウェアなどは、セキュリティ面でも不安な点が大きくなります。使用年数が重なり、サポートが終了している製品は、セキュリティに関してのアップデート等も行われなくなることが多いです。そのため、セキュリティが甘くなったことから、不正アクセスやウイルス感染のターゲットにされる恐れがあります。企業は顧客のデータなど絶対に流出してはいけない情報データを持っていますが、不正アクセスなどにより重要情報の流出などの事件を起こしてしまうケースは少なくありません。
リプレイスを行うことで、最新のセキュリティ対策を導入し、システムの脆弱性を解消することができます。例えば、暗号化技術の強化、多要素認証の導入、ファイアウォールの更新などが可能になります。また、リプレイスによって、セキュリティパッチの適用や脆弱性スキャンの実施が容易になり、継続的なセキュリティ管理が可能になります。
さらに、リプレイスを通じて、従業員のセキュリティ意識向上のための教育プログラムを実施したり、セキュリティポリシーの見直しを行ったりすることも重要です。これにより、人的要因によるセキュリティリスクも軽減できます。
対策を万全にするためにも、定期的にリプレイスを行い、最新のセキュリティへの更新や向上を行う必要があるのです。セキュリティ対策の強化は、企業の信頼性向上にも直結するため、リプレイスの重要な目的の一つと言えるでしょう。
新技術の導入
今やデジタルの技術は急激な進化をとげ、社内システムにおいてもAI、IoT、VRなどさまざまな技術を用いた仕組みが進出してきています。そのような仕組みを活用してさらに業務の効率化などを図り、事業の発展を進めている企業も多く存在します。また、データ管理のシステムをより良いものに更新することで、マーケティングに有効活用するなどビジネスに変革をもたらしている企業なども増えてきています。このように新技術を導入することで、経営の発展に活用することができるのです。
リプレイスを通じて新技術を導入することで、企業は競争力を高めることができます。例えば、クラウドコンピューティングの導入により、柔軟なスケーラビリティと高いコスト効率性を実現できます。また、ビッグデータ分析ツールの導入により、顧客行動の深い洞察を得て、より効果的な意思決定を行うことが可能になります。さらに、ブロックチェーン技術を活用することで、取引の透明性と安全性を向上させることができます。
リプレイスによる新技術の導入は、単なる技術更新にとどまらず、ビジネスモデルの変革や新たな価値創造の機会をもたらします。そのため、企業はリプレイスを戦略的に位置づけ、長期的な成長戦略の一環として取り組むことが重要です。
関連記事
・DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?意味や手法をわかりやすく解説
・DX化とは?DX(デジタルトランスフォーメーション)の意味やIT化との違いを解説
リプレイスの4つの方法
リプレイスを行う際は、主に以下の4つの方法があります。これらの方法は、システムの規模や業務への影響、コストなどを考慮して選択する必要があります。リプレイスの目的や企業の状況に応じて、最適な方法を選ぶことが重要です。以下に、リプレイスの4つの代表的な方法を紹介します。
● 一括移行方式
● 段階移行方式
● 並行移行方式
● パイロット方式
これらの方法には、それぞれ特徴やメリット・デメリットがあります。例えば、一括移行方式は短期間で完了できる一方で、システム全体を停止する必要があります。段階移行方式は部分的に実施できますが、古いシステムと新しいシステムが混在する期間が生じます。
並行移行方式は安全性が高いものの、コストがかかります。パイロット方式はリスクを最小限に抑えられますが、時間がかかる傾方針です。リプレイスを行う際は、これらの特徴を十分に理解し、自社の状況に最適な方法を選択することが成功の鍵となります。
リプレイスの方法を選択する際は、以下の点を考慮することが重要です。
●システムの規模と複雑さ
●業務への影響度
●予算と時間的制約
●リスク許容度
●社内のIT人材の能力
適切な方法を選択することで、リプレイスのプロセスをスムーズに進め、新しいシステムへの移行を成功させることができます。次のセクションでは、各方法の詳細について解説していきます。
一括移行方式
システムを構成するハードウェアやソフトウェアなどの全ての要素を一括で交換する方法となります。これは、リプレイスの中でも最もシンプルな手法の一つです。
比較的単純な流れで実施することができ、全てを一度に入れ替えることができるので作業が一回で済みます。そのため、費用的・時間的コストも最小限に抑えられるメリットがあります。また、これまで抱えていた問題が複数個ある場合、入れ替えをすることで一気にその問題を解決することにも繋がるでしょう。リプレイスによって、システムのパフォーマンスや機能が大幅に向上する可能性があります。
ただし、一括で入れ替えをする必要があるため、入れ替え時はシステムの全体的に停止する必要があります。システムなどが大きな規模である場合、停止時間はより長くなることが想定されます。そのため、1日中常に稼働させる必要がある場合に関しては、この方式を利用することは難しいと考えるべきです。リプレイスの実施時期や影響範囲を慎重に検討する必要があります。
逆に、全面的に停止を行える日程があったり、別のものを代用することで業務には支障がなかったりする場合には、効果的な方式となるでしょう。企業などでこの方式を利用する際には、全体的な影響をチェックしたうえで活用するようにしましょう。リプレイスの計画段階で、システム停止による影響を最小限に抑えるための対策を講じることが重要です。
段階移行方式
現在使用しているシステムから部分ごとに新しいものに切り替える方法となります。システムの老朽化が進んでいる部分や不具合がある部分のみを選定し、部分ごとにシステムを停止しながら順番に切り替えを行っていくため、全面的な停止を行わなくてもよい点がメリットとなります。部分ごとに行うため、大きな規模になることは少なく、一度当たりの時間は短くなることもメリットです。
リプレイスを段階的に行うことで、業務への影響を最小限に抑えつつ、システムの更新を進めることができます。例えば、まずはデータベースシステムをリプレイスし、次に基幹システム、最後にWebアプリケーションというように、優先度や依存関係を考慮しながら順次移行を進めていくことができます。
ただし、部分ごとに切り替えを行っていくため、一括移行方式より費用的・時間的コストはかかってしまう傾向にあります。また、部分ごとに移行するということは、元々の古いシステムと部分的に入れ替えた新しいシステムが混在してしまうことになり、設定が難しくなってしまうことも想定されます。古いものと新しいもので相互性がない場合もあるので、注意が必要です。
リプレイスの計画を立てる際は、各部分のシステムの依存関係や、移行順序による影響を十分に検討することが重要です。また、移行期間中は旧システムと新システムの両方をメンテナンスする必要があるため、運用負荷が一時的に増加することも考慮に入れておく必要があります。
並行移行方式
並行移行方式は、現在使用しているシステムと新しいシステムを一定期間同時に稼働させながら、段階的にリプレイスを行う手法です。この方式の最大のメリットは、システムの稼働を停止させることなくリプレイスを実施できる点です。また、新システムへの移行時にトラブルが発生した場合でも、比較的容易に旧システムに戻すことができるため、リスク管理の観点からも有効です。
並行移行方式によるリプレイスでは、両システムを同時運用する期間中に、新システムの動作確認や問題点の洗い出しを十分に行うことができます。これにより、本格的な切り替え時のトラブルを最小限に抑えることが可能となります。特に大規模なシステムや、業務への影響が大きいシステムのリプレイスにおいて、この方式は有効です。
一方で、並行移行方式にはデメリットもあります。2つのシステムを同時に運用するため、コストや管理の負担が増大します。また、データの整合性を保つために、両システム間でのデータ同期作業が必要となる場合もあります。さらに、ユーザーが両方のシステムを使い分ける必要があるため、一時的に業務効率が低下する可能性もあります。
リプレイスの計画を立てる際は、並行移行方式のメリットとデメリットを十分に検討し、運用担当者や移行に携わる人々の負担を考慮しながら実施することが重要です。また、並行運用期間中は、新旧システムの比較検証を綿密に行い、新システムの性能や機能が期待通りであることを確認することが不可欠です。
最終的に新システムへの完全移行を行う際は、十分なテストと準備を経て、影響の少ない時期を選んで実施することが望ましいでしょう。並行移行方式を採用することで、リプレイスのリスクを軽減しつつ、スムーズな移行を実現することができます。
パイロット方式
パイロット方式とは、ある部門で現在使用しているシステムから新しいシステムに切り替え、テスト的に運用を行い、問題なく利用できると判断できた後に全体の部門でも切り替える方法です。この方式は、リプレイスの中でも慎重なアプローチを取るため、リスク管理に優れています。
影響の少ない部署でテスト的に運用を行ってから全体での切り替えを実施できるので、不安要素を解決したり、リスクをおさえたりしたうえで、実施することができます。もし新システムでトラブルが発生したとしても、それを1つの運用ノウハウとして蓄積することに繋がります。そのノウハウを手に入れた上で本番に取り組むことができるのです。
パイロット方式によるリプレイスでは、以下のようなメリットがあります。
●リスクの最小化:小規模な部門での試験運用により、大規模な問題を回避できます。
●ユーザーフィードバックの獲得:実際の使用環境での評価が可能となります。
●段階的な導入:全社的なリプレイスの前に、システムの改善や調整が可能です。
ただし、テスト運用を行っていく必要があるため、もちろん費用や時間がかかることは避けられません。また、パイロット部門と他の部門で一時的にシステムが異なる状況が発生するため、データの整合性や業務プロセスの違いに注意を払う必要があります。
リプレイスを成功させるためには、パイロット方式を含む適切な移行方法を選択し、綿密な計画を立てることが重要です。各部門の特性や業務への影響を考慮しながら、最適なリプレイス戦略を策定することが求められます。
4つの方法から選ぶ際のポイント
4つの方法を解説しましたが、現在の状況などから適切な方法を選択して実施することが必要となります。4つの方法から選ぶ際のポイントは以下の通りです。
| 方法 | ポイント |
| 一括移行方式 | 現在のシステムを一定時間・一定期間全体的に停止することが可能 |
| 段階移行方式 | 移動させる必要のある機能やデータが複数存在するが、現在のシステムを長時間停止させることは難しい |
| 並行移行方式 | 現在のシステムを一時的でも停止させることは難しい |
| パイロット方式 | テスト的にシステムの運用を行い、納得したうえで移行し、最大限活用したい |
関連記事:レガシーシステムとは!意味や企業にとっての課題をわかりやすく解説!
リプレイスの進め方5ステップ
新規のものに交換することで、パフォーマンスの向上やセキュリティ対策を行うことができるリプレイスですが、誤った移行方法をしてしまうとトラブルが起きてしまうリスクもあります。正しい手順で進めていくことが重要です。ここからは基本的な進め方を解説していきます。
リプレイスの内容を決定
まずは、内容や要件を決めることが重要です。既存のシステムの分析や課題の洗い出しを行い、「何をどのように変えたいのか」「変えなくてもよい点はどこか」を明らかにしたうえで、実施する必要があります。
内容や要件を決定する際は、上層部と運用担当者だけでなく、実際に利用をしている従業員などからも意見や要望を聴くことをおすすめします。
計画立案
内容や要件を決定させたら、計画を立案させましょう。以下の点をおさえて計画を立てていくと良いでしょう。
● 全体スケジュール
● 実施日
● 移行の方法
● システムの停止期間・時間
● 事前の準備を行う日程や行う人
● リハーサルを行う日程
計画を具体的に立案して社内などに共有することで、準備をしっかりと行った上で取り組むことができます。
移行データの準備
移行させるデータの確認は念入りに行っておきましょう。そのままの状態で移行できるデータはよいですが、リプレイス後に仕様が変わる場合などは、データの調整などが必要な場合もあるので注意が必要です。システムが新しくなって、データが利用できなくなってしまったり破損してしまったりすると、業務に支障が出る恐れがあります。重要なものや機密情報にあたるものなどは、特に細心の注意を払いましょう。
リハーサルの実施
移行を行う前は、必ずリハーサルをしましょう。リハーサルを事前に実施することで、考えている作業手順で円滑に進めることができるかをチェックすることができます。また、トラブルが起きた際も、対処方法を準備しておくことができるので、そのノウハウを本番に活かすことができます。主に以下のような点に着目しながらリハーサルを行ってください。
● 考えている手順で円滑に進めることができるか
● 手順通りに進めてトラブルになり得ることはないか
● データを移しても問題は発生しないか
● 想定している時間で進めることができそうか(システムの停止時間も考慮する)
● 想定していたトラブルが発生した場合どのような対処を行うか
リプレイスの実施
リハーサルが完了すれば、実際に本番に進みましょう。リハーサルでは出てこなかったトラブルなども発生するかもしれませんが、落ち着いて対処するようにしましょう。
リプレイスの際の注意点
リプレイスを問題なくスムーズに完了させるためには、いくつかの注意点を把握し、しっかりと対処しておくことが重要です。ここからは注意点について解説します。
システムを止めることで影響を受ける範囲を正しく確認する
既存システムの停止をする方法で実施する場合、停止することで影響を受ける範囲を正しく確認するようにしておきましょう。
計画などが甘いまま社内のシステム入れ替えを行ってしまうと、直接的に影響を受ける部署に関してのみ対策を行っていたため、間接的に影響を受けてしまう部署に関しては対策を行っておらず、業務に支障をきたしてしまうといったケースは少なくありません。
きちんと計画を立てていないことで、社内全体の業務が停止してしまったり、会社の収益に悪影響を与えてしまったりする場合があるので、計画立案の時点で影響を受ける範囲を正しく確認するようにしておくことが重要です。
既存のシステムとの連携を把握しておく
既存のシステムに他のシステムを連携させている場合は、入れ替えを実施した後もスムーズに連携が行えるのか確認・把握をしておきましょう。新しいシステムが連携したいシステムと結びつかないケースも考えられます。もし、確認を怠って新しいシステムへの入れ替えを行ってしまうと、入れ替えた後に連携できないことに気づいてしまい、無駄にコストを使ってしまうことになるかもしれません。企業によっては大きな損害となってしまう恐れがあります。
「現状連携させているシステムは何か」「新しいシステムと連携させることは可能か」などを計画立案の時点で確認・把握を行い、適切な方法で実施しましょう。
業者と連携して進めていく
リプレイスは、「よく分からない」という理由で業者に丸投げしてしまうのではなく、必ずシステムを保有・入れ替えをする企業が主体となり、業者と連携して進めていくことが重要です。
今後新しいシステムを利用していく企業が主体とならなければ、自社が求める理想のリプレイスは実現することが難しいでしょう。きちんと自社で計画の立案やスケジュールの決定、必要な機能などを考えた上で、業者に共有を行いましょう。それを元に業者の意見を取り入れたり、自社の要望や意見などを伝えたりすることが重要です。
もちろん難しい点は業者に任せてもよいですが、きちんと内容を聞き、把握した上で業者に任せるようにしましょう。
無謀な計画は立てない
現代ではITの進歩がかなり早くなってきているため、自社にも一早く新しい技術や最新のものを導入したいという想いから、無謀な導入の計画を立ててしまう企業も存在します。自社の発展を望むことからより良いものを導入したいのは分かりますが、企業がかけられる費用や時間的コストなど利用できるリソースには限りがあります。無謀な計画は、むしろシステムの導入の実現を阻んでしまう要因となる恐れもあるので、注意しましょう。
また、システムの入れ替え・導入が決まったとしても、スケジュールや実施方法などには注意が必要です。いち早く実施したいからといって、社内全体を考えず実施を行ってしまうと、トラブルなどが起きてしまった際に従業員たちの業務に支障をきたしてしまう恐れもあります。社内全体を把握した上で、最適なリプレイスの方法を行いましょう。
実施後に改善を行っていく
リプレイス後は、稼働時に完璧な完成を期待しないことも重要です。しっかりと計画を立て、最適なリプレイスを行ったとしても、機能の修正事項や追加したい点などは出てくる可能性があります。そのため、運用担当者や移行に携わっている人たち、または社内の従業員たちに、稼働後にも改善していくという姿勢を共通認識できるように伝えておくことが大切です。
関連記事:複雑化するB to Bの顧客管理/システム導入のメリットや成功パターンを把握する方法
リプレイス導入時の課題
これまで使用していたシステムからより良くするためにリプレイスを実施するものの、導入時や実際の運用でトラブルや問題が起こってしまう場合もあります。
スケジュールの遅れ
導入時に、実際に計画していたスケジュールより遅れてしまう要因としては、企業と業者のコミュニケーション不足が考えられます。企業が念入りに計画を立てたとしても、その計画が業者に共有されていなければスムーズに進めることができません。また、企業だけで計画を立てた場合、その計画が甘い場合も想定されます。プロである業者の意見も取り入れることでより適切な流れが構築できたり、両社の共通認識が増えたりしていくので、入念に事前準備を行うことができます。結果、実際の作業がスムーズに行うことができるでしょう。もしも途中でトラブルが起きてしまったとしても、企業と業者で事前にしっかり情報の共有をしておくことで、迅速に対処できる可能性が高まります。
既存システムとの連携
多くの企業では、販売管理や顧客管理など複数のシステムを導入し、日々稼働しています。そのため、これらの既存システムと新しく導入したシステムをうまく連携させる必要があるのです。
もし、システム同士の連携が取れなくなってしまうと、各システムが個々に独立して稼働し、業務の効率化やデータ管理の簡易化のためにシステムを利用しているはずなのに、利用の意味が無くなってしまうかもしれません。従業員の負担が増えてしまったり、ミスが増えてしまったりなど、悪い影響を与えてしまいかねないので、きちんと連携については導入時にチェックを行いましょう。
関連記事:マイルストーンの意味とは!使い方や書き方を徹底解説!
まとめ
本記事では、リプレイスの概要や実施する目的、実際に行う際の進め方などを解説しました。「今はとりあえず大丈夫」という考えで、古いソフトウェアをそのままにしていたり、ブラックボックス化したシステムなどをそのまま使ったりしていると、将来的に大きな問題に発展してしまうことも考えられます。企業などはそれがWeb上の事件や情報の漏洩に繋がってしまう可能性もあるので最大限の注意をする必要があるでしょう。
リプレイスはさまざまな方法や注意点があり、簡単な作業ではありませんが、実施することで企業や事業のこれからの発展に繋がるものとなります。ぜひ最適な方法で実施を行ってみましょう。