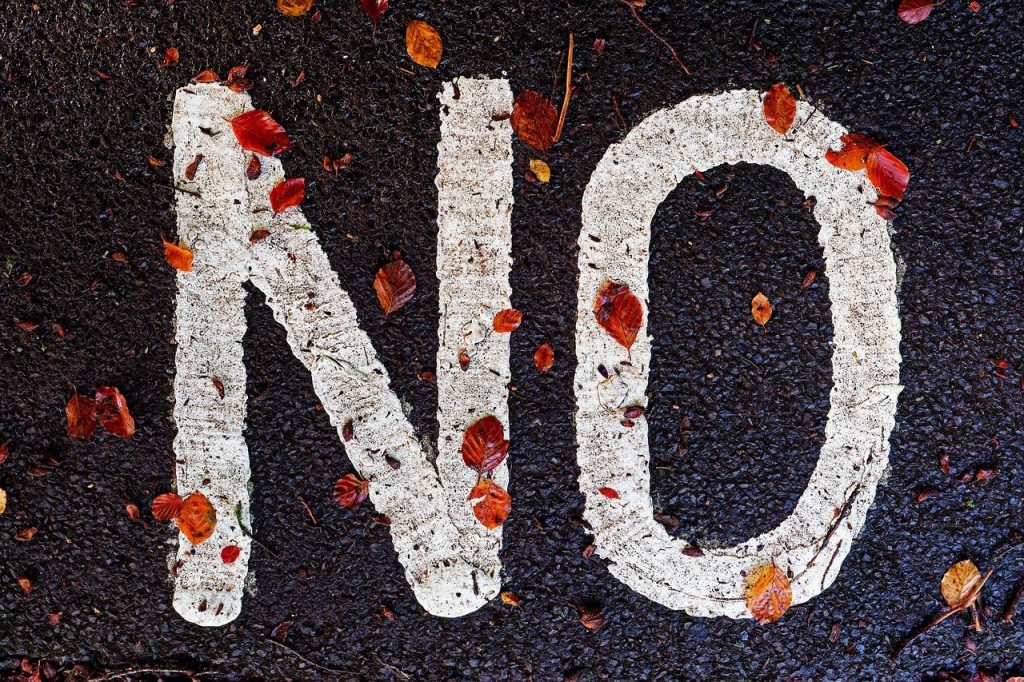今やX(旧Twitter)は、情報発信だけでなく、ビジネスの収益源として活用され始めています。
とはいえ、「インフルエンサーでないと無理そう」「始め方がわからない」と感じている方も多いでしょう。しかし、Xの収益化はフォロワー数に関係なく実現可能です。自社サイトやYouTubeへの誘導、PR案件の受注、公式機能の活用など、多様な方法があります。
本記事では、Xでの具体的な収益化手法や成功事例、運用のポイントまでをわかりやすく解説します。
関連記事:インフルエンサーとは? 定義・SNS別特徴・マーケ施策を徹底解説【2025完全ガイド】
人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?
BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!
目次
X(旧Twitter)で収益化を行うメリット
X(旧Twitter)は、SNSの中でも特に収益化の可能性が広がっているプラットフォームのひとつです。
近年の機能拡充やユーザー層の多様化により、企業・個人を問わず多くの人々が収益化へと踏み出しています。
ここでは、Xを通じて収益化を目指す際の主なメリットを3つの視点から整理します。
収益化の手段が豊富にある
Xでは、従来の情報発信に加え、収益化の手段が大きく広がっています。
クリエイター収益配分プログラムやサブスクリプション機能を活用すれば、フォロワーとの関係を深めながら直接収入を得ることが可能です。
さらに、アフィリエイト、自社商品の販促、企業案件の受注など、Xを起点とした多様なマネタイズ手段も構築できます。
動画や広告に依存せず、ビジネスモデルに合わせて柔軟に活用できる点が特徴です。
数あるSNSのなかでも、歴史が長くユーザーが多いためマネタイズのチャンスが大きい
Xは2006年にサービスが開始され、すでに10年以上の歴史を持つ老舗SNSです。
長期的に運用されてきたこともあり、多くのユーザーが利用しています。総務省の調査によると、全年代の49%が利用しており、主要SNSの中でもトップクラスのアクティブユーザー数を誇ります。
ユーザー数が多いということは、すなわち自社アカウントを見てもらえる機会が多いということ。
フォロワー数が少ない段階でも、リポスト(旧リツイート)や検索機能を通じて投稿が拡散されやすいXでは、想定以上のリーチが得られることもあります。
そのため、地道な発信が広告なしでも収益につながるチャンスがあるのです。
関連記事
・SNSとは?2025年版の最新一覧:種類・特徴・目的別に徹底比較
・BtoB企業向けSNSマスターガイド×成功事例集
機能面や利用文化の面で、ポストが拡散されやすい
Xの最大の特長のひとつが、拡散力の高さです。
他のSNSと異なり、ユーザーが自分のタイムラインに他人の投稿を自由にリポストできるため、有益な情報や面白いコンテンツは瞬時に数万〜数十万規模で広がる可能性を秘めています。
また、Xではリアルタイム性と話題性が重視される傾向にあり、たとえばトレンドワードや社会的ニュースに関連付けて投稿することで、より多くの人の目に触れる可能性があります。
このような構造的特性を踏まえると、発信力を持たない段階からでも、収益化への道筋を立てることは十分に可能です。
X(旧Twitter)で収益化を行うデメリット・注意点
Xを活用した収益化は、多様な可能性を秘めている一方で、実際に取り組む際には注意すべき点も少なくありません。ここでは、代表的なデメリットやリスクについて解説します。
担当者の負担が大きくなりやすい
収益化を目指すということは、単なる情報発信とは異なり、KPI(重要業績評価指標)やKGI(重要目標達成指標)を明確に設定し、その達成に向けた継続的な運用が求められます。
つまり、Xを「ビジネスチャネルのひとつ」として位置づける以上、戦略的なコンテンツ企画、日々の運用、分析・改善までを包括的に担う体制が必要です。
また、フォロワー数やエンゲージメント数など、定量評価しやすい指標だけに縛られてしまうと、施策の本質を見失うリスクもあるため、成果定義の見直しも含めた柔軟な運用が求められます。
▼KPIやKGIについては、以下の関連記事で深掘り解説を行っています。
・KPIの意味とは?初心者にもわかる徹底解説と設定事例
・コンバージョンの種類とは?KGI・KPIとの関係性や成果を上げるための施策も紹介
炎上リスクに常に配慮する必要がある
SNS、とりわけXのように拡散力の高いプラットフォームでは、炎上リスクが常に伴います。
たとえば、何気ない一文が文脈を外れて切り取られたり、ポストの意図が誤解されて広まってしまったりといった事例は後を絶ちません。
収益化を目指す場合、ポストが収益に直結するビジネス資産となるため、炎上によるブランド棄損や信頼失墜は致命的です。
加えて、ステークホルダーや既存顧客への波及リスクもあるため、BtoB領域では特に慎重な投稿管理が必要となるでしょう。
具体的には、運用のレギュレーションを定め、投稿前のダブルチェック体制、リスクが高い発言・テーマのガイドライン化などが有効です。
関連記事
・ステークホルダーとは何か簡単に解説。企業にとっての重要性と関係構築のポイント
・X(Twitter)で炎上しないためのポイントとは?企業アカウントに重要なベストプラクティス
・レギュレーションとは?ビジネスでの意味や例を解説
フォロワーの購入には手を出さない
フォロワー数は影響力の可視化指標として重視されがちですが、数を増やすために購入することは、短期的には見栄えをよくしても、中長期的には明確なデメリットがあります。
なぜなら、購入によって増えるのはアクティブでない偽アカウントであるケースが多く、結果としてポストのエンゲージメント率(反応率)が大きく低下します。
Xのアルゴリズム上、エンゲージメント率が低下すれば、投稿の表示優先度が下がり、本来届くべきユーザーにも届きにくくなってしまいます。
さらに、利用規約違反により、アカウント凍結(BAN)やペナルティの対象となる場合もあるため、目先の数値にとらわれず、信頼性ある運用を心がけることが重要です。
関連記事:エンゲージメントとは?マーケティングにおける意味合いを徹底解説
X(旧Twitter)運用を収益につなげる5つの基本的な方法
ここでは、Xを起点として収益につなげるための代表的な5つのアプローチを解説します。
1. Xから自社メディアへの流入を目指す
Xを通じて、自社サイトやオウンドメディア、YouTubeチャンネル、LPなどに誘導し、商品・サービスの購入や問い合わせ、メルマガ登録などに結びつける方法です。
Xでの発信内容をあえてさわりにとどめ、詳細はメディアに誘導する設計にすることで、集客→ナーチャリング→CVというマーケティングファネルを構築しやすくなります。
2. 企業PR案件を受注、あるいは発注する
一定のフォロワー数や業界内での影響力を持つ場合、企業PR案件を受注して収益化することも可能です。
具体的には、企業の商品紹介ポストやキャンペーン告知を投稿して報酬を得ます。
企業側の立場としては、自社商品を紹介してくれるインフルエンサーをX上で探し、発注することで認知向上や購買促進を図れるでしょう。
特にニッチな業界での影響力を持つアカウントに依頼すれば、高精度なターゲティングが期待できます。
3. X内の収益化機能を活用する
Xでは、近年「クリエイター支援」への動きが加速しており、収益化に直結する公式機能が複数提供されています。
たとえば以下のようなものです。
● チップ(Tips)投げ銭:ユーザーから直接支援金を受け取る機能
● スーパーフォロー(現在はクリエイターサブスクリプションに統合):月額課金で限定コンテンツを提供
● スペースの有料チケット制:ライブ音声配信に課金できる仕組み
これらは「認証済みアカウント」や「フォロワー数500人以上」といった利用条件があるものの、投稿そのものが価値として認識される設計になっているため、継続的に投稿するモチベーションにもつながります。
4. アフィリエイトへつなげる
X上の投稿にアフィリエイトリンクを掲載し、商品やサービスの紹介を通じて成果報酬を得る方法も一般的です。
たとえば、Amazonアソシエイトや楽天アフィリエイトなどのメジャーなプログラムのほか、専門性の高い商材を扱うASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダー)を活用するケースもあります。
注意点としては、アフィリエイト投稿があまりに露骨だったり、頻度が高すぎたりすると、ユーザーの信頼を損なう恐れがあるため、日常的な投稿とのバランスを意識しながら運用することが重要です。
関連記事:アフィリエイトとは?仕組みと始め方や収益化のポイント
5. X上でキャンペーンを実施する
たとえば「フォロー&リポストで応募」「指定ハッシュタグをつけて投稿」など、インセンティブ付きのキャンペーンを実施することで、フォロワーやインプレッション数を一気に伸ばし、商品やサービスの認知を高められます。
直接的な収益化ではなくとも、こうしたプロモーション活動を通じて見込み顧客との接点を増やし、将来的な購買や商談につなげる間接的なマネタイズとして有効です。
関連記事
・マーケティングキャンペーンの基本とは?その概要と事例をご紹介
・ハッシュタグの意味とは!付け方や活用シーンを徹底解説
・ハッシュタグの付け方は?インスタやTwitter(X)での基本と注意
・インプレッション(impression)とは?意味や類似用語との違い、増やす方法
クリエイター向けのX(旧Twitter)公式収益化機能2つ
ここでは、代表的な2つの収益化機能「クリエイター収益配分プログラム」と「クリエイターサブスクリプション」について、概要・条件・活用ポイントを詳しく解説します。
クリエイター収益配分プログラム
このプログラムは、投稿(ポスト)に表示される広告収益の一部を、対象となるクリエイターに還元する制度です。2023年7月にXが開始したもので、いわばYouTubeにおける広告収益モデルのX版ともいえる仕組みです。
利用条件(執筆時点の公式情報より)
● X Premium(旧Twitter Blue)または認証済み組織のサブスクリプションに加入していること
● フォロワーが500人以上
● 過去3か月間でインプレッション数が500万回以上(すべての投稿合算)
● Stripeアカウントを持ち、Xと接続できること(報酬受け取り用)
広告収益の対象となるのは、フォロワーのタイムライン上で表示された投稿のインプレッション数で、X側での審査を通過したアカウントに対して報酬が支払われます。
なお、広告主が付かない投稿や不適切と判断される投稿は対象外となることがあります。
クリエイターサブスクリプション
旧「スーパーフォロー」からアップデートされた機能で、クリエイターが月額課金モデルを通じて、限定コンテンツを提供できる制度です。
ファンは月額料金を支払うことで、有料フォロワー限定の投稿やスペース、Q&A、コンテンツアーカイブなどにアクセス可能になります。
利用条件(執筆時点の公式情報より)
● X Premiumへの加入
● 18歳以上
● フォロワー数が500人以上
● 過去30日間アクティブ
● Stripeアカウントを持ち、Xと連携していること
この機能は「熱量の高いフォロワー」が多いアカウントほど効果を発揮します。
情報発信だけでなく、価値あるナレッジや限定ノウハウ、エンタメ性の高いコンテンツなど、フォロワーがお金を払ってでも得たいと感じる価値の提示が不可欠です。
X(旧Twitter)収益化をおこなった著名人アカウントの事例
ここでは、代表的な3名の著名人による収益化事例を紹介しながら、「実際にいくら稼げるのか」「どんな運用スタイルが効果的なのか」といったリアルな視点を掘り下げます。
「ひろゆき」さん(@hirox246)の事例
匿名掲示板「2ちゃんねる」の開設者として知られる西村博之氏(ひろゆき氏)は、Xでも高い発信力を誇り、論理的かつ皮肉を交えた投稿で多くの反応を集めています。
2023年の情報によると、ひろゆき氏はXの収益配分プログラムを通じて、1か月あたり約36万6,000円の広告収入を得ていたとされます(為替レートにより変動あり)。
当時のインプレッション数は約8,000万回以上と推定され、投稿の拡散力と頻度が成果に直結していることがうかがえます。
投稿内容は、時事ニュースへのコメントや社会問題の批評が中心で、話題性・タイミング・意外性のバランスを意識した運用が特徴です。
「ぬこー様ちゃん」さん(@nukosama)の事例
「ぬこー様ちゃん」さんは、イラストやキャラクター系コンテンツを中心に活動する漫画家で、X上でも高い人気を誇るユーザーです。
フォロワー数はひろゆき氏の約4分の1ながら、インプレッション数は4億回を超えており、その「バズる力」の高さが際立っています。
共感や癒しを感じさせるイラストに加え、拡散されやすい投稿を戦略的に設計している点も特徴です。
収益額の具体的な公表はありませんが、インプレッション数に基づく広告収入モデルを踏まえると、相当な金額を得ていると推定されます。
関連記事:バズるとは?意味や使い方を解説します
「村瀬歩」さん(@murase_pipipi)の事例
人気声優の村瀬歩さんも、Xの収益化機能を活用している一人です。
フォロワー数は約46万人(執筆時点)で、厚いファン層を背景に安定した支持を得ています。
村瀬さんは、Xのクリエイター収益配分プログラムに参加し、1か月で134.55ドル(約18,940円)の収益を得たことを公開しました。これは、フォロワー数やインプレッション数と収益との相関を示す好例といえます。
彼のようにファンとの関係を丁寧に築いてきたアカウントでは、「広く浅く」よりも「狭く深く」価値を届けるスタイルが、収益化にもつながりやすいことがわかります。
X(旧Twitter)上での収益化が規定で禁じられているジャンル
Xで収益化を行うには、事前に確認すべき重要なルールがあります。それは、収益化の対象から明確に除外されているジャンルが存在するという点です。
【収益化が禁止されている主なジャンル】
● 大麻や違法薬物
● タバコ製品
● アルコール類
● 武器・弾薬・軍事用品
● ギャンブル、賭博、くじ引き類
● 暴力的・差別的な投稿
● 死亡事故・災害・事件などを利用した投稿
● 誤情報や誤解を招く内容
これらは「倫理的に問題がある」「広告主のブランド毀損リスクが高い」とされる領域であり、Xの広告収益配分ポリシーにより明確に収益化の対象外とされています。
収益化ポリシーに反する投稿を続けた場合、以下のような措置を受ける可能性があります。
● 収益化機能の停止
● 広告配分からの除外
● アカウントの一時停止または凍結
● 投稿の削除や非表示措置
明確に収益化を目指す場合の、X(旧Twitter)運用のポイント
ここでは、アカウント設計から日々の運用に至るまで、収益を生むための実践的なポイントを5つに分けて解説します。
収益化を前提としたアカウント設計をおこなう
まず重要なのは運用目的を明確にすることです。どの収益モデルを軸にするのか、誰に届けたいのか、最終的なゴールは何かを明文化し、運用方針と世界観を統一しましょう。
企業アカウントであれば、KGI・KPI・ペルソナ設定・投稿体制(誰が、いつ、何を発信するか)などをまとめた運用マニュアルの整備が重要です。
これにより、属人的にならず再現性のある運用が実現できます。
関連記事:コンセプト(concept)の意味ってなに?なぜ必要なのか含め解説します
アカウントプロフィールを整備する
どれだけ魅力的な投稿をしても、プロフィールが不十分だとフォローに至りません。特に新規訪問者は、投稿よりも先にプロフィールや固定ポストを見る傾向があります。
● 発信ジャンルが一目でわかる
● 実績や経歴が信頼性を裏付けている
● 親近感をもてる人柄やストーリーが含まれている
こうした要素を意識し、フォローするべき理由を明示するプロフィールにしましょう。
▼アカウントプロフィール検討の際にぜひ念頭におきたい「セルフブランディング」については、以下の関連記事をご覧ください。
「セルフブランディング」とは? 意味や目的、実践方法まで徹底解説
質の高いポスト(ツイート)を維持する
Xでの収益化は、投稿そのものが収益の源泉になるケースが多いため、1件1件の投稿の質が重要になります。ただ単に情報を出すだけではなく、以下のような投稿を意識しましょう。
● 課題提起から解決策までをコンパクトに整理
● 誰かの役に立つ知見やノウハウを提供
● エンタメ性やユーモアを交えた人間味ある投稿
情報過多のSNS環境では、ユーザーがエンゲージメントしたくなる要素を含むことが拡散の鍵です。
閲覧者とのコミュニケーションを積極的におこなう
Xは双方向性の強いSNSです。
投稿の発信だけでなく、フォロワーや潜在的な見込み顧客との関係性を深めることで、信頼と共感が収益につながる土台になります。
● リプライへの返信やいいね対応
● 他ユーザーの投稿へのリポストやコメント
● DMでのやり取り(自動化ツールを併用するケースも)
関連記事
・エゴサ(エゴサーチ)とは?意味や企業としてのやり方
・いいねとは?インスタ、X(Twitter)を例に解説
データの収集と分析を常におこなう
運用成果を最大化するには、定期的な振り返りと改善が欠かせません。
Xには標準で「Xアナリティクス(旧Twitter Analytics)」が用意されており、以下のようなデータを取得できます。
● インプレッション数
● エンゲージメント率(いいね、リポスト、クリックなど)
● フォロワーの増減と属性分析
こうしたデータを活用し、「どの投稿が収益につながったのか」を分析・検証することで、PDCAサイクルを確立できます。
まとめ:X(旧Twitter)の収益化には複数の方法あり! 自分に合った選択肢を
X(旧Twitter)は、もはや単なる情報発信ツールではなく、クリエイターや企業にとって「収益を生むプラットフォーム」へと進化しています。
しかし、収益化を目指す以上、リスク管理やアカウント設計、コミュニケーション設計といったマーケティング視点が不可欠です。
特に企業として発信する場合には、「運用戦略」「データ活用」「ブランド設計」を含めた包括的な取り組みが求められます。
そこで重要となるのが、SEOとSNSを連携させたコンテンツマーケティングの戦略構築です。
▼HR SEOでは、人事・採用部門に特化したSEOおよびオウンドメディア運用支援を行っています。
https://www.profuture.co.jp/mk/solution/3040