マーケティングにとって「セグメント」は必要不可欠な概念です。この記事では、マーケティングにおけるセグメントの重要性とともに、セグメントをする際に役立つ「6R」という新指標や、BtoBマーケティングで必須となる「ファーモグラフィック変数」に関する情報など、2025年の最新情報を解説します。
関連記事:セグメントとは。マーケティングだけでなくビジネス全般で使われる用語の意味
人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?
BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!
目次
マーケティングにおけるセグメントの意味
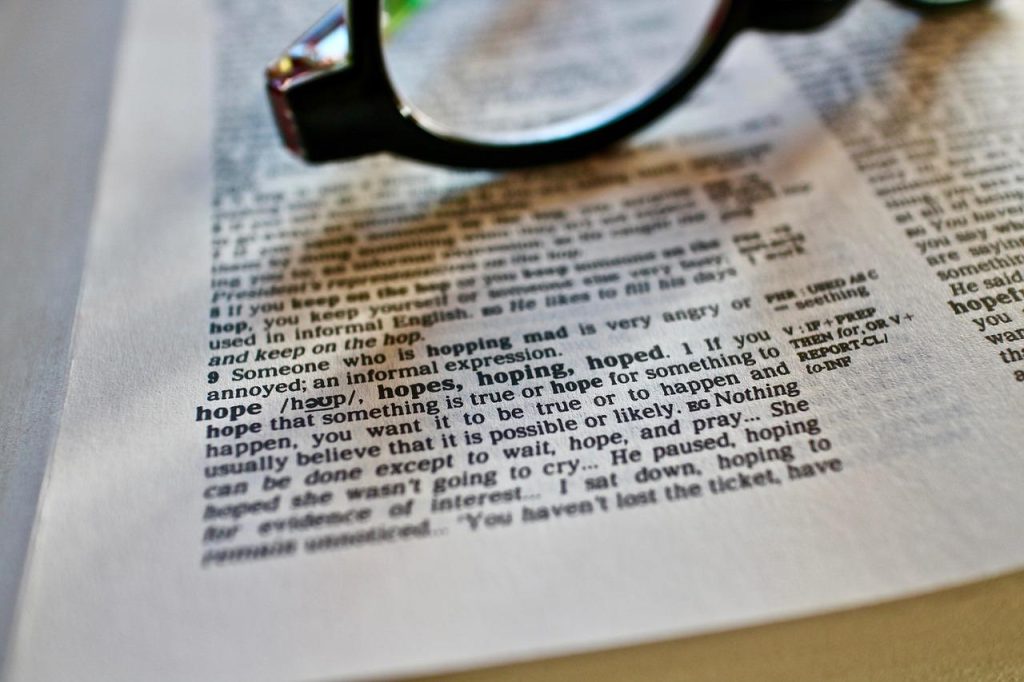
はじめに、ビジネスにおけるセグメントの意味から確認しましょう。
セグメントとは
ビジネスにおけるセグメントとは、顧客や市場を特定の要素に沿って分けたグループです。年齢や購買行動など、複数の要素によってグループ化します。既存顧客だけでなく、潜在顧客など、現在は取引のない相手を対象にする場合もあります。
セグメントは主にマーケティングで使われている概念であり、広告出稿などでも使用する用語で、マーケターにとっては必須の知識です。
関連記事:【図解つき】潜在顧客とは?課題発生時に“第一想起”されるマーケ支援会社直伝のリード枯渇を防ぐ開拓手法
セグメンテーションとは
セグメンテーションとは、特定の対象をセグメントに区切る行為を意味します。ただし、「セグメント=セグメンテーション」の意味で用いるケースもあります。そのため、言葉の認識に齟齬がないか、部署やチームで確認しておきましょう。
関連記事:セグメンテーションとは?ターゲティングとの違いや分類する方法、具体例
ターゲットとの違い
セグメントと近い言葉に「ターゲット」があります。前述の通り、セグメントとは特定のルールのもと、顧客を含む市場を細分化したグループです。一方のターゲットは、セグメントの中からマーケティングの対象として抽出したグループを指します。マーケティングでは、セグメントとターゲットのどちらの言葉も広く使われています。それぞれの意味を混同しないように注意しましょう。
関連記事:ターゲティングの意味
市場や顧客をセグメントで分類する必要性
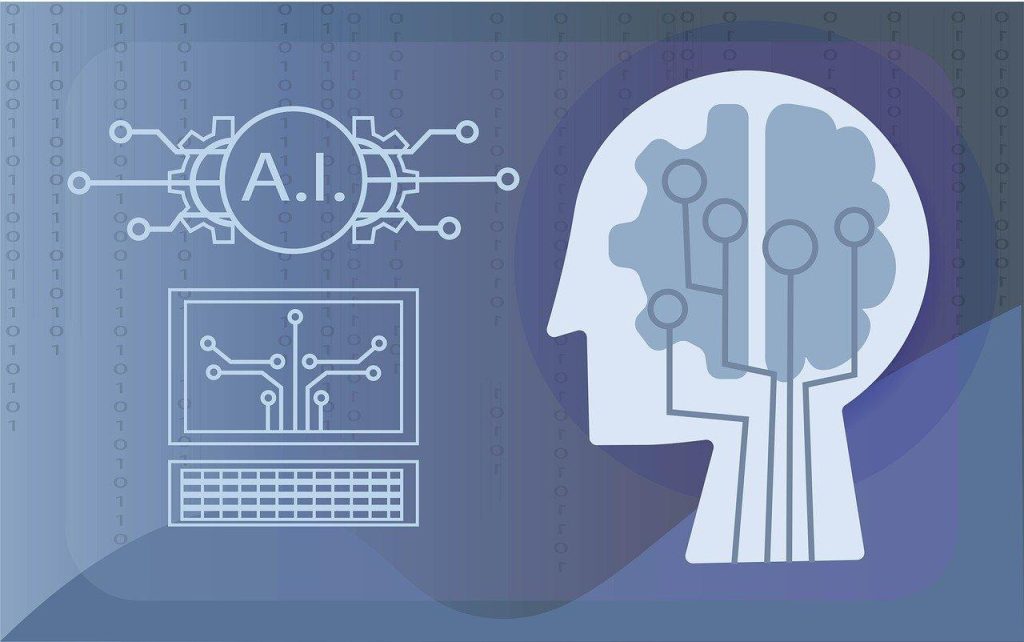
市場や顧客をセグメントで分類する必要性として、以下3つの理由が挙げられます。
さまざまな顧客層に応えるため
かつては、テレビCMや新聞などを通じて不特定多数に訴求する「マスマーケティング」が主流でした。しかし、インターネットやスマートフォンの普及によって、消費者の情報収集手段は多様化しています。さらに、価値観や働き方も激変したことで、画一的なマーケティングでは効果が得にくくなりました。ニーズや行動が異なる多様な顧客層をしっかりセグメントし、それぞれに最適化された訴求が必要とされる時代に変化しつつあります。
多様な顧客層に対応するダイバーシティマーケティングについては下記を参考にしてください。
ダイバーシティとインクルージョン入門|意味、重要性、推進によって企業・社会にもたらす変革を解説
顧客ロイヤルティの重要性が高まったため
近年は、新規顧客の獲得だけでなく、既存顧客との関係継続および売上拡大の重要性が高まっています。これは、市場の飽和や競合の激化、消費者の価値観やニーズの多様化、そして少子高齢化による市場全体の縮小傾向により、新規顧客獲得のコストが増大しているためです。
既存顧客との関係を深めることは、アップセル・クロスセルといった売上拡大の施策や、LTV(顧客生涯価値)の向上にもつながります。既存顧客をリピーター化させ、LTVを向上させるためには、顧客ロイヤルティの向上が不可欠です。
顧客ロイヤルティとは、顧客が自社ブランドに対して持つ信頼感や愛着心です。顧客ロイヤルティが高いユーザーほど、自社ブランドを継続的に購買してくれます。
顧客ロイヤルティを高めるためには、セグメント化した小さなグループごとのニーズを理解して、最適な体験やサービスを提供することが重要です。
▼顧客ロイヤルティについては次の記事でも解説しています。
顧客ロイヤルティを意識したマーケティング戦略のポイント
マーケティング5.0へ進化したため
マーケティング手法は時代とともに進化しており、2020年代には「マーケティング5.0」が提唱されました。経済学者のフィリップ・コトラー氏が提唱したマーケティング理論で、最新テクノロジーを活用し、顧客体験を高めることの重要性を説いています。
マーケティング5.0では、データにもとづいて施策を決定する「データドリブン」がより一層重要になりました。AIやビッグデータを活用して顧客行動を詳細に分析すれば、顧客層をより正確にセグメントできます。
さらに、細かくセグメントしたグループに対する戦略も、顧客心理を深く理解したパーソナライズされた施策を打ち出せるようになりました。
▼データドリブンなマーケティング手法の詳細は以下の記事をご覧ください。
データドリブンとは?データドリブンマーケティング実現のために必要なことを解説
マーケティングにセグメントを活用するメリット・デメリット

続いて、マーケティングにセグメントを活用するメリットとデメリットを解説します。
メリット
市場や顧客をセグメントで分けると、自社の各商材に最適なターゲット層を明確にしたうえで、効率的なアプローチが可能になります。「誰に、いつ、どんな情報を届けるか」といった必要な施策を考案できるため、広告や販促の無駄を減らし、費用対効果を高められるでしょう。また、顧客層を細かく分類することで、競合他社が見落としているニッチな市場を発見し、独自のポジションを構築できます。
関連記事:5W1Hとは?意味や正しい順番、ビジネスでの使い方を解説
デメリット
セグメントを導入したマーケティングには多くのメリットがある反面、セグメントの設定や分析にはコストと手間がかかります。そのため、予算やリソースに制限がある場合、セグメントの工程が想定以上の負担になる可能性もあるでしょう。
また、使用するデータが古かったり、量が不十分だったり、偏っていたりすると、的外れなターゲティングにつながる可能性もあります。結果として、効果の薄い施策を連発してしまうリスクがあるため、セグメントを実行する際は、データの正確性、そして適切な量のデータを集め、継続的に見直すことが求められます。
セグメントに用いる情報の種類
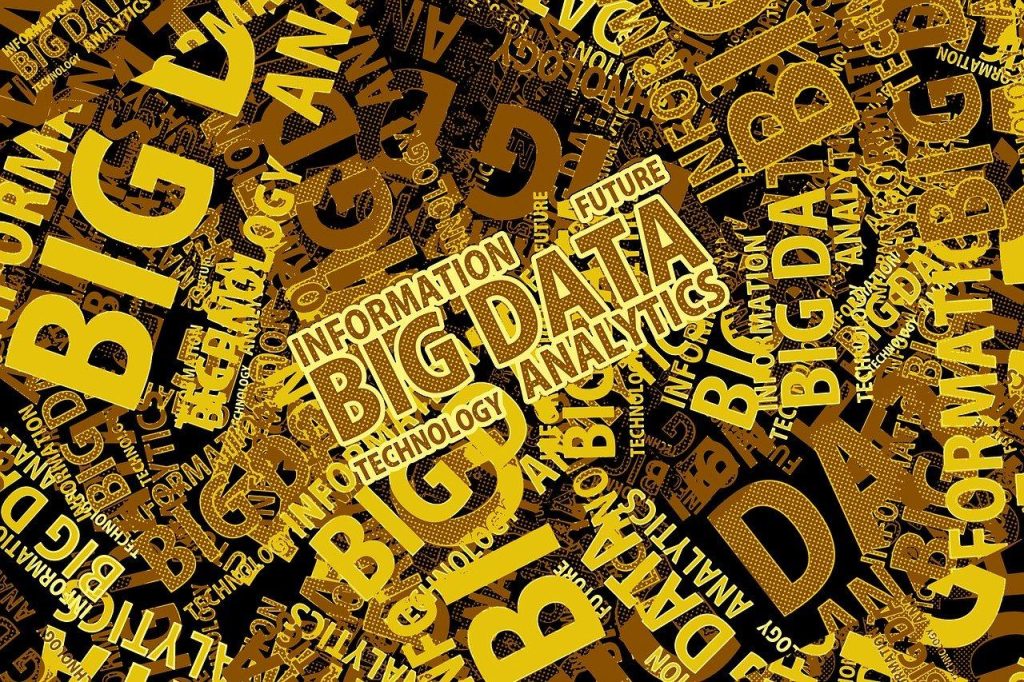
セグメントを実施する際は、対象集団に関する情報が必要です。主に次の5種類の情報が使われます。
ビヘイビアル変数(行動変数)
ビヘイビアル(行動変数)とは、消費者の購買行動をもとにしたデータ項目(変数)です。代表的な情報は、次の通りです。
・過去の購買履歴
・購入頻度
・購入した商品・サービスの利用目的
・利用チャネル
・商品への関心度
・閲覧ページやクリック履歴
・Webサイトでの滞在時間
・特定のコンテンツへの反応(例:資料ダウンロード、動画視聴完了率)
近年はインターネットの普及により、ユーザーごとのWeb上の行動ログを簡単に取得できます。ビヘイビアル変数を分析することにより、顧客がどのような行動をとっているかを具体的に把握し、次のアクションを予測することが可能になります。
デモグラフィック(人口動態変数)
デモグラフィック(人口動態変数)とは、年齢や性別などの人口統計に関するデータ項目です。具体的には、以下の情報が該当します。
・年齢
・性別
・職業
・最終学歴
・世帯構成
・収入レベル
・家族構成(例:既婚・未婚・子供の有無)
デモグラフィックは、比較的収集しやすいデータです。たとえば「20代女性向けの化粧品」といった明確な属性にもとづくターゲティングを行う際に広く活用されています。この変数は、顧客の基本的な属性を理解し、市場の全体像を把握する上で基盤となります。
ジオグラフィック(地理的変数)
ジオグラフィック(地理的変数)とは、居住地域や文化などの地理的な要素に関するデータ項目です。主な項目は以下の通りです。
・居住国
・市町村などの地域
・人口密度
・人口規模
・気候
・文化
・都市開発の度合い
・交通機関の利便性
気候や地域で売れ行きが変わる衣類や食料などの商品に加え、店舗型ビジネスでジオグラフィックデータが重要になります。地域ごとの特性や消費者の行動パターンを理解することで、より地域に密着した効果的なマーケティング戦略を立案できます。
▼ジオグラフィックデータを活用するMEO(マップ検索エンジン最適化)対策については、以下の記事をご覧ください。
MEO対策とは?メリット・デメリットから対策方法まで、MEOとは何かを徹底解説
サイコグラフィック(心理的変数)
サイコグラフィック(心理的変数)とは、趣味や価値観といった心理的な要素によるデータ項目です。具体的な項目は、以下の通りです。
・趣味嗜好
・ライフスタイル
・価値観
・興味関心
・製品やサービスに対する感想
・購買動機
・性格特性(例:保守的、革新的、衝動的、慎重派、権威志向、挑戦的、など)
サイコグラフィックデータは、SNSの投稿分析やアンケート、インタビューなどの手法により取得します。顧客行動の背景にある内面的な特徴を捉えることで、よりパーソナライズしたマーケティングを実現できます。この変数は、顧客の感情や思考に深く踏み込み、共感を呼ぶメッセージングやブランド構築に不可欠です。
ファーモグラフィック(企業変数)
ファーモグラフィック(企業変数)とは、企業の特性によるデータ項目です。主に、次の情報が当てはまります。
・業種
・業界の特性
・所在地
・設立年数
・従業員数
・売上高
・担当者の役職
・対象企業の市場規模
・資本金
・IT・DX化状況
・意思決定プロセス
ファーモグラフィックデータは、とりわけBtoBマーケティングにおいて必須の情報となります。BtoBビジネスでは顧客一社ごとの価値が高く、ターゲット別に的確な施策を立案することで成約率の向上につながります。これらの情報を複合的に分析することで、企業の課題やニーズを具体的に把握し、最適なソリューション提案につなげることが可能になります。
▼BtoBにおける意思決定者リードを獲得するには「HRプロ」への広告掲載がおすすめ
セグメントを行う主なフレームワーク

マーケティングにおいて、セグメントを行う3種類のフレームワークを紹介します。
STP分析
STP分析とは、マーケティング戦略を立案する基本のフレームワークです。「セグメンテーション(Segmentation)」「ターゲティング(Targeting)」「ポジショニング(Positioning)」の3段階で構成されています。
はじめに、既存顧客と潜在顧客を含む市場全体を複数のセグメントに分けます。次に、その中から自社が狙うべきターゲット層を選定します。最後に、競合他社との差別化ポイントを明確にすることで、効果的な戦略決定が可能です。
▼STP分析についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
STP分析のすべて┃メリット、やり方、活用事例、注意点まで解説
関連資料:ポジショニングマップの作り方とパワポテンプレート×5パターン【競合分析資料】
デシル分析
デシル分析とは、既存顧客の分析に使うフレームワークの一つです。既存顧客を累計購入金額が高い順に並べて、10個のセグメントに分割します。ちなみにデシルとは、ラテン語で「10」を意味する言葉です。
デシル分析により、売上構成比が高いグループがわかるため、優先的にアプローチすべき対象を選別できます。また、各セグメントの購買傾向や施策への反応を測定できるため、それぞれへの適切なアプローチを設計できるでしょう。
RFM分析
RFM分析とは、「Recency(最終購入日)」「Frequency(購入頻度)」「Monetary(累計購入金額)」の3要素から既存顧客を分類するフレームワークです。
たとえば「購入頻度が高く、最終購入日が近い顧客」は優良顧客、「購入頻度は高いが最終購入日が遠い顧客」は休眠顧客と分けられます。顧客の購買行動から現在の状態や傾向を把握できるため、セグメントごとに適切なフォローを行えます。
▼デシル分析とPRM分析の詳しい違いについては、こちらをご覧ください。
デシル分析とRFM分析の違いとは?活用方法と事例をご紹介
従来の4Rから進化した「6R」によるセグメント評価方法

市場や顧客をセグメント化した後は、マーケティングで使われる指標「6R」でセグメントの妥当性を評価しましょう。なお、セグメントの評価方法として「4R」もありますが、現在は「市場規模(Realistic Scale)」「成長性(Rate of Growth)」「競合(Rival)」「顧客の優先順位(Rank)」の4つの指標に、「到達可能性(Reach)」と「測定可能性(Response)」の2つの指標が加わり、「6R」が主流になっています。
これらの2つの指標が追加された背景には、デジタルマーケティングの進化とデータ活用の重要性の高まりがあります。 顧客へのアプローチチャネルが多様化し、施策の効果測定がより詳細に行えるようになった現代において、「顧客に確実に情報を届けられるか(到達可能性)」、そして「施策の効果を数値で把握し改善できるか(測定可能性)」が、セグメントの有効性を判断する上で不可欠となったためです。
市場規模(Realistic Scale)
市場規模とは、セグメントの経済的なポテンシャルを見極める指標です。セグメントの潜在的なニーズや顧客層の厚さを確認して、マーケティング費用に見合った利益を得られるほどの市場があるかを確かめます。小規模な市場でも高単価な商材に適していれば投資の価値はありますが、収益構造の確立が難しいのであれば優先度は下がるでしょう。
▼市場環境を詳しく分析する「3C分析」については以下の記事で解説しています。
3C分析とは?やり方や手順、テンプレートも紹介
成長性(Rate of Growth)
成長性とは、セグメントの市場が今後どの程度発展するのかを測る指標です。仮に現在の市場規模が小さくても、将来的な拡大が見込まれる場合は長期的なマーケティング戦略を立てる価値があるでしょう。反対に、現在は規模が大きいものの将来的に衰退が予測される場合、新規参入計画および既存戦略の再考が求められます。
顧客の優先順位(Rank)
顧客の優先順位とは、セグメントの顧客にとっての自社の優先度を示す指標です。自社商材の価格帯・機能性・ブランドイメージといった要素が、セグメントのユーザーが持つ興味関心やニーズとマッチしているかを確認します。自社の強みが顧客の求める価値と一致していれば、マーケティングのリソースを集中させることで、より良い成果を得られるでしょう。
競合状況(Rival)
競合状況とは、セグメントにおける競合他社の影響力を分析する指標です。競合が多数存在して飽和状態であれば、新規参入やシェア拡大のハードルは高いでしょう。一方で、競合が少ない、あるいは自社商材による明確な差別化ができる場合、優位に立てる可能性があります。競合製品のシェア率や価格帯、ブランディング戦略を調査して、自社にチャンスがあるかを見極めましょう。
▼自社の立ち位置を明確にする「ポジショニングマップ」のダウンロードはこちら
ポジショニングマップの作り方とパワポテンプレート×5パターン【競合分析資料】
到達可能性(Reach)
ここからは4Rに足された新たな指標です。
5つ目の指標である「到達可能性」とは、セグメントのターゲット層へ自社商材を認知させられるかを判断する指標です。どれほど優れた商品やサービスであっても、顧客に認知してもらえなければ意味がありません。SNSや検索エンジン、イベント、店舗など、ターゲット層が利用するチャネルを把握し、有効なアプローチ施策を実行できるかを確認します。
測定可能性(Response)
6つ目の指標である「測定可能性」とは、マーケティング施策の効果測定が可能な市場や顧客であるかを評価する指標です。たとえば、セグメントからのリード獲得を目的してWeb広告を出稿する場合、セッション数やコンバージョン数を測定するツールが必要になります。効果測定が難しいセグメントでは、施策改善のPDCAサイクルを回しにくくなり、効率的なマーケティングが困難になります。
関連記事:PDCAとは!時代遅れといわれる理由やOODAとの違いについて解説!
セグメントを活用したマーケティング施策の具体例

セグメントを活用した具体的なマーケティング施策として、主に以下の5つが挙げられます。
メール・SNSのセグメント配信
メールやSNSマーケティングでは「セグメント配信」が欠かせません。セグメント配信とは、年齢や性別、購買履歴、行動履歴などの条件でユーザーを分類し、それぞれに最適なメッセージを届ける手法です。セグメント配信を取り入れることで、ターゲットのニーズに合致した情報が届くため、開封率やクリック率が向上し、コンバージョンへつなげやすくなるでしょう。最近では、AIを活用したユーザー行動や配信結果の分析により、パーソナライズされた配信も可能になっています。
動的なコンテンツの実行
セグメントの変数の中には、顧客の行動や属性が時間とともに変化する「動的な要素」が含まれます。たとえば、年齢(デモグラフィック変数)や居住地(ジオグラフィック変数)、購買行動(ビヘイビアル変数)などのデータが該当します。
こうした動的なセグメントにリアルタイムで対応するために活用される手法が、「動的なコンテンツ」です。たとえば、ECサイトでは、ユーザーの購入履歴や閲覧傾向に応じて商品を自動提案する「レコメンド機能」があります。また、前述のセグメント配信においても、MAツールを活用すれば、顧客データの更新に応じてユーザーを自動的に再分類し、常に最適なコンテンツを配信することが可能です。
製品の新規開発や改善
セグメントは、製品の開発や改善にも活かされます。セグメントごとに異なるニーズを把握することで、ターゲット層に合致する新商品の企画が可能です。加えて、既存顧客からのフィードバックをセグメント単位で分析すれば、製品改善のヒントが得られます。セグメントにもとづいた商品展開は、競合他社との差別化や顧客ロイヤルティ向上にもつながるでしょう。
コンテンツの最適化
コンテンツマーケティングを取り入れる場合、「誰に、いつ、どのような情報を提供するか」が重要です。セグメントによってニーズや課題は異なるため、記事や動画、セミナーといった最適なコンテンツの制作が求められます。
さらに、インサイドセールスの現場でも、コンテンツの最適化が欠かせません。リードに提供する資料やホワイトペーパーをセグメント別に用意することで、商談化の可能性を高めることができるでしょう。
▼インサイドセールスの詳細は、以下の記事で解説しています。
インサイドセールスとは?フィールドセールスとの違いやメリットを分かりやすく解説
Web広告のターゲティング設定や出稿媒体
セグメントによって、Web広告を表示するユーザーの属性を細かく設定できます。6Rで妥当性を検証したセグメントからターゲットを絞り込むと、さらに広告の精度を上げられるでしょう。
また、広告出稿する媒体の選定も重要です。セグメントに合致するターゲットが多く、効率的にリードを獲得できるメディアを選びましょう。たとえば、意思決定者に近い人事や経営層へ効率的にアプローチしたい場合は、「HRプロ」のような人事専門ポータルメディアへの出稿が適しています。
セグメントをマーケティング戦略に活用した企業事例

実際にセグメントをマーケティング戦略に取り入れた企業事例を紹介します。
成城石井の事例
「成城石井」は、高価格帯の食品をメインに扱うスーパーマーケットです。低価格路線を重視するスーパーマーケットが多いなか、成城石井は高級志向の消費者にターゲットを絞っています。新規店舗を出店する際も、高所得者層の居住比率が多い地域であるかを判断基準に取り入れるなど、セグメントを重視した戦略を展開しています。
Appleの事例
Appleは、米国のテクノロジー企業です。PCやスマートフォンなどのIT機器は、一般的に機能性が重視されます。しかし、Appleは機能性だけでなく、デザイン性にも重きを置いています。デザイン性を重視するユーザーをターゲットにして製品を開発した結果、多くのファンを獲得しました。
スターバックスの事例
スターバックスは、米国のコーヒーチェーンです。1996年に日本初出店した当初、日本国内の喫茶店は「喫煙可能」「格安メニュー」の路線が一般的でした。スターバックスは全面禁煙や高品質なメニュー、インターネット普及後はフリーWi-Fiの設置などの施策をいち早く実行して、居心地の良い空間を求める消費者の獲得に成功しました。
市場や顧客のセグメントをもとにマーケティング施策を考案しよう
マーケティングでは、顧客や市場を特定の要素に沿って分けるセグメントが欠かせません。顧客層の行動や地理的要因などの変数をもとに、自社商材が狙うべきセグメントを明らかにしましょう。特にBtoBマーケティングにおいては、企業の業種や規模といった「ファーモグラフィック変数」が、効果的なターゲット選定に不可欠です。
さらに、細分化したセグメントは、メールマーケティングや広告出稿先の選定に役立ちます。そして、そのセグメントを6Rなどの指標で評価・検証することも重要です。これらのプロセスを通じて、適切なマーケティング施策を考案し、効果的な戦略実行へとつなげることが可能になります。

