商談の成否を左右する「決裁権」の重要性は、多くのビジネスパーソンが肌で感じていることでしょう。しかし、その決裁権を持つキーパーソンをどう見極め、いかに効果的にアプローチすれば良いのか、具体的な戦略に悩む方も少なくありません。
この記事では、決裁権の定義から、キーパーソンの特定方法、決裁権者への効果的なアプローチ戦略、さらには決裁権を持たない担当者との商談術、見極め失敗時の対処法まで、商談の勝率を劇的に上げるための実践的なノウハウを網羅的に解説していきます。
人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?
BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!
目次
決裁権とは何か:商談におけるその重要性

ビジネスにおいて、商談を成功に導くためには「決裁権」の理解が不可欠です。決裁権とは、企業や組織において、特定の事項に関する最終的な意思決定を行う権限を指します。特にBtoBビジネスの営業活動では、この決裁権を持つ人物、すなわち「決裁者」を見極め、適切にアプローチすることが、受注率を劇的に向上させる鍵となります。
決裁権の定義とビジネスにおける役割
決裁権とは、企業が商品やサービスを導入したり、新たなプロジェクトを開始したりする際に、最終的な承認を与える権利のことです。この権限を持つ人物が「決裁者」と呼ばれます。決裁者は、単に提案を承認するだけでなく、企業戦略に基づき、人材、予算、時間といったリソースを適切に配分する重要な役割を担っています。
決裁権は、その内容や金額、企業規模によって、担当役員、部門長、事業部長、あるいは代表取締役社長など、様々な役職の人物が持つことがあります。中小企業では社長や経営幹部が、大企業では各部門の責任者や専門部署が担う傾向があります。
決裁権と混同されやすい言葉に「承認」や「稟議」がありますが、これらは決裁とは異なるプロセスです。以下の表でその違いを整理します。
| 用語 | 定義 | ビジネスにおける役割 |
|---|---|---|
| 決裁 | 最終的な意思決定を下す行為 | 企業活動における最終的なGoサインを出す。責任を伴う最終判断。 |
| 承認 | 決裁の前段階で、提案内容に同意する行為 | 決裁に至るまでのプロセスで、関係者が内容を認め、上位者へ進める。最終決定権は持たない。 |
| 稟議 | 決裁や承認を得るための社内手続きや文書 | 自身の権限を超える事項について、文書を作成し、関係者の承認・決裁を得るためのボトムアップ型の意思決定方式。 |
なぜ決裁権が商談の成否を分けるのか
商談において決裁権が重要である理由は、最終的な導入決定権を持つ人物への直接的なアプローチが、商談の効率と成約率を大きく左右するためです。 どんなに優れた商品やサービスであっても、決裁者の承認が得られなければ契約には至りません。
決裁者との商談は、以下のようなメリットをもたらします。
- プロセスの高速化:決裁者が早い段階で承認すれば、その後のプロセスがスムーズに進行し、無駄な工数を削減できます。
- 効果的な提案:決裁者が抱える課題や企業の方針を直接ヒアリングできるため、より的確で魅力的な提案が可能です。
- インサイトの獲得:企業の戦略や重視するポイントといった貴重な情報を直接得ることができ、今後の営業戦略に役立てられます。
- 受注率の向上:決裁者に直接アピールすることで、提案の納得性が高まり、成約に繋がりやすくなります。
特にBtoBビジネスでは、複数の部門や役職、それぞれの目的やニーズが複雑に絡み合うことが多く、最終的な決定権を持つ決裁者の存在は非常に大きいです。現場担当者との商談で良い感触を得ても、決裁者に情報が正確に伝わらなかったり、優先度が低く判断されたりすると、成約の機会を逃してしまうリスクがあります。 したがって、決裁権を持つキーパーソンを早期に見極め、戦略的にアプローチすることが、商談を成功に導く上で極めて重要なのです。
キーパーソンを見極める 決裁権を持つ人物の特定方法
商談の成功には、最終的な意思決定者である「決裁権者」を見極めることが不可欠です。しかし、このキーパーソンは常に明確であるとは限りません。この章では、事前調査から商談中のヒアリング、そして組織構造の理解を通じて、決裁権を持つ人物を効果的に特定するための具体的な方法を解説します。
事前調査で決裁権者を推測する
商談に臨む前段階での入念な事前調査は、決裁権者を推測し、効果的なアプローチ戦略を立てる上で非常に重要です。公開されている情報から、企業の意思決定プロセスやキーパーソンの存在を読み解くことができます。
公開情報を活用した決裁権者推測のポイント
- 企業ウェブサイト・IR情報: 企業の組織図や役員構成、事業内容、企業理念などを確認しましょう。特に、役員紹介ページやIR情報に掲載されている事業報告書は、経営層の関心事や事業戦略の方向性を把握する上で役立ちます。
- プレスリリース・ニュース記事: 新規事業の発表や提携、人事異動に関するプレスリリースは、そのプロジェクトの責任者や意思決定に関わる人物を特定する手がかりとなります。関連するニュース記事もチェックし、企業が現在注力している領域や課題感を把握しましょう。
- SNS(LinkedInなど): 担当者の役職や経歴、発信内容から、その人物の社内での影響力や関心事を推測できます。また、LinkedInのようなビジネスSNSでは、特定の役職を持つ人物のリストアップも可能です。
- 業界レポート・競合分析: 業界全体の動向や競合他社の事例を把握することで、ターゲット企業がどのような課題を抱え、どのようなソリューションに関心を持つ可能性があるかを推測できます。これにより、決裁権者が注目するであろうポイントを事前に予測し、提案内容を最適化できます。
これらの情報から、「誰が最終的な決定を下すのか」「その決定に影響力を持つのは誰か」という仮説を立て、商談に臨む準備を進めます。特に、企業の規模によって決裁権を持つ人物の役職は異なる傾向があります。例えば、従業員200名未満の中小企業では社長が決裁権を握るケースが多い一方、大企業では役員や事業部長がキーパーソンとなることが一般的です。
商談中のヒアリングで決裁権者を特定する質問術
事前調査で仮説を立てた上で、実際の商談では、担当者との会話の中から決裁権者を特定するヒアリングが不可欠です。直接的に「決裁権は誰にありますか?」と尋ねるのではなく、自然な流れで情報を引き出す質問術が求められます。
決裁権者特定のための質問フレームワーク「BANT」
営業ヒアリングの基本フレームワークとして知られる「BANT」は、決裁権者(Authority)の特定にも有効です。
| 項目 | 質問の意図 | 具体的な質問例 |
|---|---|---|
| Budget(予算) | 今回のプロジェクトにかけられる予算感を把握する | 「本件に関して、ご予算はどの程度お考えでしょうか?」「予算の承認プロセスについてお聞かせいただけますか?」 |
| Authority(決裁権) | 最終的な意思決定者が誰か、決裁プロセスを確認する | 「このプロジェクトの最終的なご判断は、どなたがされるのでしょうか?」「導入までの流れとして、社内ではどのような承認プロセスがありますか?」 |
| Needs(ニーズ) | 顧客の抱える課題や解決したいニーズを明確にする | 「現在、どのような課題をお持ちですか?」「どのような成果を期待されていますか?」 |
| Timeframe(導入時期) | 導入の時期やスケジュール感を把握する | 「いつ頃までに導入をお考えですか?」「導入に向けたスケジュール感についてお聞かせください。」 |
特にAuthorityに関する質問では、「最終的な判断」や「承認プロセス」に焦点を当てることで、担当者が決裁権を持っているのか、それとも別の人物が最終決定を下すのかを把握できます。 担当者が「上司に承認を得てから営業部長への決裁を仰ぎます」のように具体的に答えることで、決裁までの段階を理解することができます。
また、「こうした案件は、〇〇部長がOKならOKですよね」といった、相手から回答を引き出し、決裁ルートを明確にするための質問も有効です。
これらの質問を通じて、担当者の役割や影響力、そして最終的な決裁権を持つ人物の存在を把握し、次のステップへと繋げることが重要です。
関連記事:BANT(BANT条件)をBtoBにおける営業活動に活用するには?
組織図や役職から決裁権者を判断する
企業の組織構造や役職名は、決裁権を持つ人物を判断するための重要な手がかりとなります。特にBtoBマーケティングにおいては、ターゲット企業の組織体系を理解することが、適切なアプローチ先の選定に直結します。
役職と決裁権の一般的な関係性
一般的に、役職が高くなるほど決裁できる金額や範囲は大きくなります。しかし、企業規模や業界、組織文化によってその基準は異なります。以下に、役職と決裁権の一般的な関係性を示します。
| 役職 | 決裁権の傾向 | 補足 |
|---|---|---|
| 担当者・主任 | 小規模な経費や日常業務の承認 | 情報収集や社内調整役が主。最終決裁権は持たないことが多い。 |
| 課長・係長 | 部署内の予算範囲での経費、小規模プロジェクトの承認 | 現場の課題解決に直接関わり、提案への影響力を持つ。 |
| 部長・本部長 | 部門全体の予算管理、中規模プロジェクトの決裁 | 事業戦略や部門目標達成に直結する提案に関心が高い。 |
| 役員(取締役、執行役員) | 全社的な重要投資、大規模プロジェクトの決裁、経営戦略に関わる事項 | 企業の成長やROI(投資対効果)を重視する。 |
| 社長 | 企業全体の経営戦略、M&A、新規事業など最高レベルの決裁 | 特に中小企業では、社長がほぼ全ての決裁権を持つケースが多い。 |
組織図からの情報読み取り方
企業のウェブサイトなどで公開されている組織図は、決裁権者を推測する上で貴重な情報源です。 組織図からは、以下の点を読み取ることができます。
- 部門の構成: どの部門がどのような役割を担っているか、自社の製品やサービスがどの部門の課題解決に貢献できるかを把握します。例えば、営業支援ツールであれば営業部長、人事系ツールであれば人事部長がキーパーソンの候補となるでしょう。
- 指揮命令系統: 誰が誰の直属の上司であり、どのような報告ラインが存在するかを理解することで、決裁がどのように上申されていくかのルートを推測できます。
- 役職者の配置: 特定の部門に高位の役職者が多く配置されている場合、その部門が企業にとって戦略的に重要である可能性が高いです。
ただし、組織図はあくまで形式的なものであり、社内には非公式な影響力を持つ「隠れキャラ」が存在する場合もあります。 そのため、組織図から得られる情報と、商談中のヒアリングで得られる情報を組み合わせ、多角的に決裁権者を見極める視点が重要です。
決裁権者への効果的なアプローチ戦略
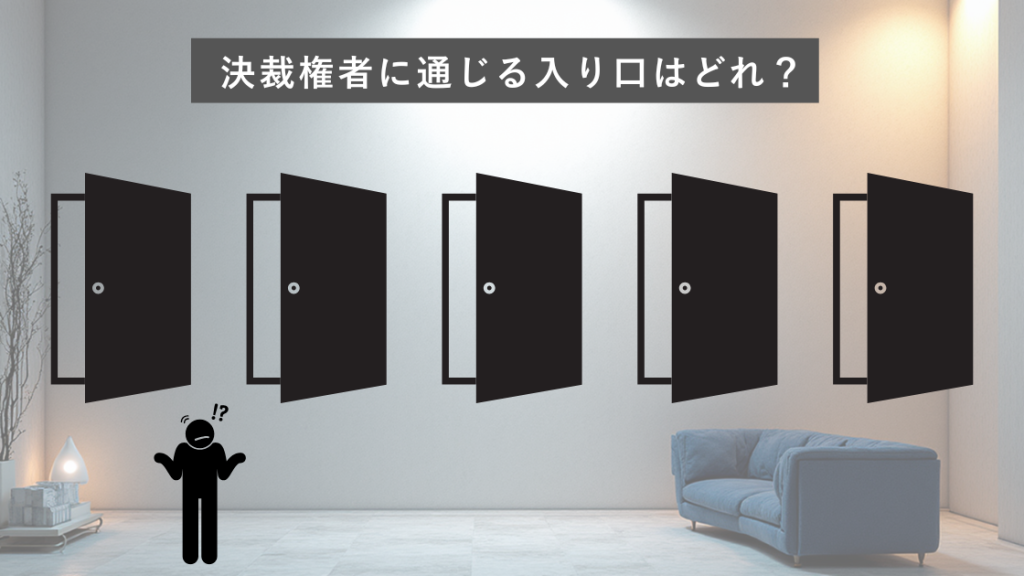
商談の最終段階において、決裁権者へのアプローチは成約を左右する最も重要なフェーズです。決裁権者が抱える課題やニーズを正確に捉え、彼らが納得できる具体的な価値を提示することが、商談成功の鍵となります。ここでは、決裁権者に対して効果的にアプローチするための具体的な戦略を解説します。
決裁権者の課題とニーズに合わせた提案
決裁権者は、自社の経営目標達成や課題解決に直結する投資かどうかを重視します。そのため、単なる製品やサービスの機能説明に終始するのではなく、決裁権者の立場に立ち、彼らが解決したい具体的な課題や達成したい目標に焦点を当てた提案を行うことが不可欠です。例えば、コスト削減、売上向上、業務効率化、リスク回避といった、彼らが直接的なメリットとして感じられる具体的な成果を明確に提示しましょう。
提案資料やプレゼンテーションでは、以下の点を意識して準備を進めます。
- データに基づいた裏付け: 競合分析、市場データ、導入事例など、客観的なデータを用いて提案の根拠を示します。
- ROI(投資対効果)の明確化: 導入によってどのような経済的効果が期待できるのかを具体的に示し、投資の正当性を訴えます。
- 具体的な導入後のイメージ: 導入によって決裁権者のビジネスがどのように変化し、どのようなメリットを享受できるのかを具体的にイメージさせます。
特に、マーケターや広告関係者であれば、自社のサービスがどのように決裁権者のマーケティングROIを改善し、ブランド価値を高めるのかを具体的に示すことが求められます。「なぜ今、この投資が必要なのか」という決裁権者の問いに明確に答える準備をしておきましょう。
決裁権者との信頼関係を築くコミュニケーション
決裁は、論理だけでなく感情も大きく影響します。決裁権者との間に強固な信頼関係を築くことは、提案内容をスムーズに受け入れてもらう上で極めて重要です。信頼関係は、誠実な態度、専門知識、そして相手への深い理解を示すコミュニケーションを通じて構築されます。
- 傾聴と共感: 決裁権者の話に真摯に耳を傾け、彼らの懸念や期待に共感する姿勢を見せます。これにより、相手は「自分のことを理解してくれている」と感じ、心を開きやすくなります。
- 専門性と知見の提示: 業界のトレンドや最新情報、競合他社の動向など、決裁権者が関心を持つであろう専門的な知見を提供することで、あなたのプロフェッショナルとしての価値を認識してもらいます。
- 透明性と誠実さ: 不都合な情報も隠さず伝え、質問には正直に答えることで、信頼性を高めます。長期的なパートナーシップを視野に入れたコミュニケーションを心がけましょう。
商談中は、決裁権者の表情や言葉のニュアンスから、彼らが何を重視しているのか、どのような疑問を抱いているのかを常に察知し、臨機応変に対応する柔軟性も求められます。一方的な説明ではなく、対話を通じて共に解決策を探るスタンスが信頼構築に繋がります。
複数人の決裁権者がいる場合の対応
現代のビジネスにおいて、一つの商談で決裁権が単一の人物に集中しているケースは稀です。多くの場合、複数の部門長や役員がそれぞれの視点から意思決定に関与します。このような状況では、それぞれの決裁権者が持つ権限、関心事、そして懸念事項を個別に把握し、それぞれに最適化されたアプローチを行う必要があります。
複数人の決裁権者が関わる商談では、以下の点を考慮した戦略を立てましょう。
| 決裁権者のタイプ | 主な関心事 | アプローチのポイント |
|---|---|---|
| 財務担当役員 | コスト、ROI、予算配分、リスク | 具体的な費用対効果、予算内での実現可能性、将来的な収益性を数値で明確に提示します。 |
| 事業部門長 | 売上、市場シェア、競争優位性、顧客満足度 | 事業目標達成への貢献度、競合との差別化、顧客体験の向上に焦点を当てた提案を行います。 |
| 技術担当役員 | システム統合、セキュリティ、技術的実現可能性、運用負荷 | 技術的な優位性、既存システムとの連携、セキュリティ対策、導入後のサポート体制を詳細に説明します。 |
| 法務担当役員 | コンプライアンス、契約条件、法的リスク | 法規制遵守、契約の透明性、潜在的な法的リスクへの対応策を丁寧に説明し、安心感を提供します。 |
これらの異なる視点を持つ決裁権者全員が納得できるような「共通の価値」を見つけ出し、それを中心に据えた提案を構築することが重要です。また、各決裁権者間の力関係や影響力を理解し、キーとなる人物に重点的にアプローチすることも効果的です。必要であれば、それぞれの決裁権者に対して個別の資料や説明の機会を設けることも検討しましょう。
決裁権を持たない担当者(橋渡し役・味方・擁護者)との商談戦略

商談の初期段階で決裁権を持たない担当者と接することは珍しくありません。しかし、彼らは決して「無駄な商談相手」ではありません。むしろ、決裁者への重要な橋渡し役であり、社内における情報源、そして味方となり得る存在です。
この章では、担当者との商談を単なる情報収集で終わらせず、最終的な成約へと繋げるための戦略を具体的に解説します。
担当者からの情報収集と社内での味方作り
決裁権を持たない担当者との商談は、「社内情報の宝庫」と捉えることが重要です。彼らを通じて、決裁者の考え、組織の課題、過去の失敗事例、予算の状況、さらには社内の人間関係や政治的な力学といった、外部からは知り得ない貴重な情報を引き出すことができます。
効果的な情報収集のためには、一方的なヒアリングではなく、担当者の立場や業務内容に寄り添った質問を心がけましょう。例えば、現在の業務フローにおける具体的な課題や、その課題が担当者自身にどのような影響を与えているかを深く掘り下げることで、共感を呼び、より本音に近い情報を得やすくなります。
同時に、担当者を社内での味方、いわゆる「インフルエンサー」に育てる視点も不可欠です。彼らがあなたの提案を社内で推進してくれるようになれば、決裁者へのアプローチは格段にスムーズになります。そのためには、担当者の貢献を認め、彼らの課題解決にも繋がるようなメリットを提示することが有効です。
| 情報収集のポイント | 社内での味方作りのポイント |
|---|---|
| 決裁者の関心事や優先順位 | 担当者の個人的な業務課題への共感と解決策の提示 |
| 組織全体の目標と現状のギャップ | 担当者が社内で評価されるための支援(資料提供など) |
| 過去の類似案件の経緯と結果 | 提案が担当者のキャリアアップに繋がる可能性を示唆 |
| 予算規模や承認プロセス | 定期的な情報共有と信頼関係の構築 |
決裁権者への橋渡しを促す提案の仕方
担当者との商談で得た情報を元に、いかに決裁者へのアプローチを促すかが次のステップです。ここでは、担当者が「自ら決裁者へ話を通したい」と思えるような提案の仕方が鍵となります。
提案内容は、担当者が決裁者に説明しやすいように、具体的なメリットと費用対効果を明確に示す必要があります。特に、決裁者が重視するであろう経営層の視点(ROI、コスト削減、売上向上、リスク回避など)を盛り込み、担当者が社内で「これは良い話だ」と自信を持って伝えられるような資料やトークスクリプトを提供しましょう。
関連記事:営業に欠かせない「トークスクリプト」の作り方|テレアポ・コルセン・IS未経験の新人でも即戦力に!
また、担当者が決裁者へ報告する際の懸念点を事前にヒアリングし、それに対する「反論処理」の材料を渡しておくことも有効です。例えば、「決裁者から〇〇と聞かれたら、このように答えてください」といった具体的なアドバイスは、担当者の不安を軽減し、積極的な橋渡しを後押しします。
さらに、決裁者へのアポイントメント取得を直接的に依頼するのではなく、担当者が社内調整しやすいような選択肢を提示するのも一案です。例えば、「もし決裁者の方にご興味をお持ちいただけそうでしたら、私の方から改めて詳細をご説明する機会を設けることも可能です」といった形で、担当者の負担を軽減しつつ、次の一手へと繋げます。
担当者を「社内チャンピオン」にする育成術
担当者を単なる情報伝達役ではなく、あなたの提案を社内で積極的に推進してくれる社内チャンピオン(導入を支援してくれる擁護者)へと育成することは、商談の成約率を飛躍的に高めます。社内チャンピオンは、決裁者への働きかけだけでなく、導入後のスムーズな運用にも大きく貢献してくれる存在です。
社内チャンピオンを育成するためには、まず彼らの成功体験を共有し、共に作り上げていく意識が重要です。提案が成功した場合に、担当者自身がどのようなメリット(業務効率化、部署の目標達成、個人的な評価向上など)を得られるかを具体的に伝え、彼らのモチベーションを高めます。
具体的には、決裁者への説明会で担当者に一部発表を任せる、あるいは社内での導入検討会議に積極的に参加してもらうなど、「当事者意識」を持たせる機会を創出します。これにより、担当者は単なる「伝書鳩」ではなく、プロジェクトの一員として責任とやりがいを感じ、より強力な推進役となるでしょう。
また、彼らが社内で決裁者や関係部署を説得するための「武器」を提供することも忘れてはなりません。競合他社との比較資料、導入事例、具体的なROIシミュレーション、導入後のサポート体制など、彼らが自信を持ってプレゼンできるような高品質な資料や情報を提供し続けましょう。
彼らが社内であなたの提案を語る際に、常に最新かつ最も説得力のある情報を持っている状態を保つことが、社内チャンピオンとしての活動を最大化します。
決裁権の見極め失敗を乗り越える対処法

状況に応じた戦略の軌道修正
商談の途中で決裁権を持つ人物を誤って認識していた、あるいは決裁権者が複数いることが判明するなど、見極めに失敗するケースは少なくありません。しかし、そこで立ち止まるのではなく、状況に応じた柔軟な戦略の軌道修正こそが、最終的な商談成功への道を開きます。
まず、決裁権者ではない担当者と商談を進めていた場合、その担当者を「社内チャンピオン」として育成する視点に切り替えることが重要です。担当者から決裁プロセスや社内政治に関する詳細な情報を引き出し、決裁権者に響くであろう論点を共に整理するのです。この際、担当者が社内で提案を通しやすくなるよう、決裁権者が重視するであろう費用対効果、導入メリット、リスクヘッジといった観点での資料作成や情報提供を強化しましょう。
また、商談の初期段階で決裁権者が特定できない、あるいはアプローチが難しいと判断した場合は、別のキーパーソン、例えば技術部門の責任者や現場のリーダーなど、プロジェクトに影響力を持つ人物へのアプローチを検討します。彼らを通じて、決裁権者へ間接的にアプローチするルートを構築することも有効な戦略です。
決裁権者が複数存在することが判明した場合は、それぞれの決裁権者が持つ関心事や懸念事項を個別にヒアリングし、全てのステークホルダーが納得できるような包括的な提案内容へと調整することが求められます。それぞれの決裁権者が持つ異なる視点を理解し、彼らが共通して抱える課題解決に貢献できる点を強調することで、合意形成を促進します。
次の商談に活かすための振り返り
決裁権の見極めに失敗した経験は、決して無駄ではありません。むしろ、次なる商談の勝率を劇的に向上させるための貴重な学びの機会と捉え、徹底した振り返りを行うことが不可欠です。
振り返りのプロセスでは、まず「なぜ決裁権者を正確に見極められなかったのか」という根本的な原因を深掘りします。事前調査の不足、ヒアリング時の質問の質、あるいは組織構造の理解不足など、具体的な要因を特定することが重要です。この際、客観的な視点を持つために、チームメンバーや上司を交えてディスカッションすることも有効でしょう。
次に、失敗要因を基に、今後の商談で実践すべき具体的な改善策を立案します。例えば、以下のようなチェックリストを作成し、商談前の準備段階や商談中に活用することで、見極めの精度を高めることができます。
| 項目 | 確認内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 事前調査 | 企業ウェブサイト、IR情報、ニュースリリース、SNSなどから、組織図や役員構成、過去の意思決定プロセスに関する情報を収集したか | 競合他社の情報も参考に |
| ヒアリング | 「意思決定プロセスはどのようになりますか?」「他に本件に関わるキーパーソンはいらっしゃいますか?」といった、決裁権者特定に繋がる質問を適切に行えたか | オープンクエスチョンを意識 |
| 情報分析 | 担当者の役職、発言内容、態度などから、決裁権の有無や影響力を正しく判断できたか | 複数の情報を総合的に判断 |
| リスク評価 | 決裁権者を見誤った場合のリスクを事前に想定し、代替案を準備していたか | プランBの検討 |
さらに、成功事例との比較分析も有効です。過去に決裁権者をスムーズに見極め、商談を成功させた事例と今回の失敗事例を比較し、何が成功と失敗を分けたのかを具体的に分析することで、より実践的な学びを得られます。これらの知見は、個人のスキルアップに留まらず、組織全体の営業戦略やマーケティング戦略の改善にも貢献します。定期的な振り返りと改善のサイクルを回すことで、決裁権の見極め能力は着実に向上し、商談の勝率を高めることができるでしょう。
まとめ
商談において「決裁権」の有無は、成否を分ける極めて重要な要素です。決裁権の定義を理解し、商談相手の中に潜むキーパーソン、すなわち決裁権を持つ人物を正確に見極めることは、無駄な時間と労力を削減し、効率的に商談を進める上で不可欠です。
事前調査や商談中のヒアリング、組織図の分析などを通じて決裁権者を特定し、その人物の課題やニーズに合わせた提案を行うことで、商談の成功率は飛躍的に向上します。また、直接決裁権を持たない担当者との関係構築も疎かにできません。彼らを「社内チャンピオン」として育成し、決裁権者への橋渡し役となってもらう戦略も、長期的な視点で見れば非常に有効です。
たとえ決裁権の見極めに失敗したとしても、その経験を次に活かし、戦略を柔軟に軌道修正する姿勢が求められます。これらの戦略を複合的に活用することで、あなたは商談における決裁権という最大の壁を乗り越え、より多くの契約獲得へと繋がる道を切り開くことができるでしょう。
キーパーソンへのアプローチには「HRプロ」のご活用がおすすめです
BtoB領域において、決裁権を持つキーパーソンへの確実なアプローチを狙うなら、人事専門ポータル「HRプロ」のご活用がおすすめです。
HRプロは上場企業の約9割を含む4万社・10万人超の人事・経営層が登録する国内最大級のBtoBプラットフォームで、購買意欲の高い法人リードを直接獲得できます。
あわせて人事向けフォーラム「HRサミット」を毎年秋に開催しており、協賛社の皆様に大変高い評価をいただいております。
BtoBリード獲得にお悩みの企業様はぜひ「HRプロ」をご活用ください。
▼決裁権者へのアプローチには「HRプロ」のご活用がおすすめです 日本最大級の人事向けポータルサイト「HRプロ」 資料請求はこちら 「HRプロ」は、人事担当者に役立つさまざまな情報配信から、課題解決に導くサービス、ダウンロード資料、各種セミナー・体験会情報を掲載する日本最大級の人事向けポータル…

