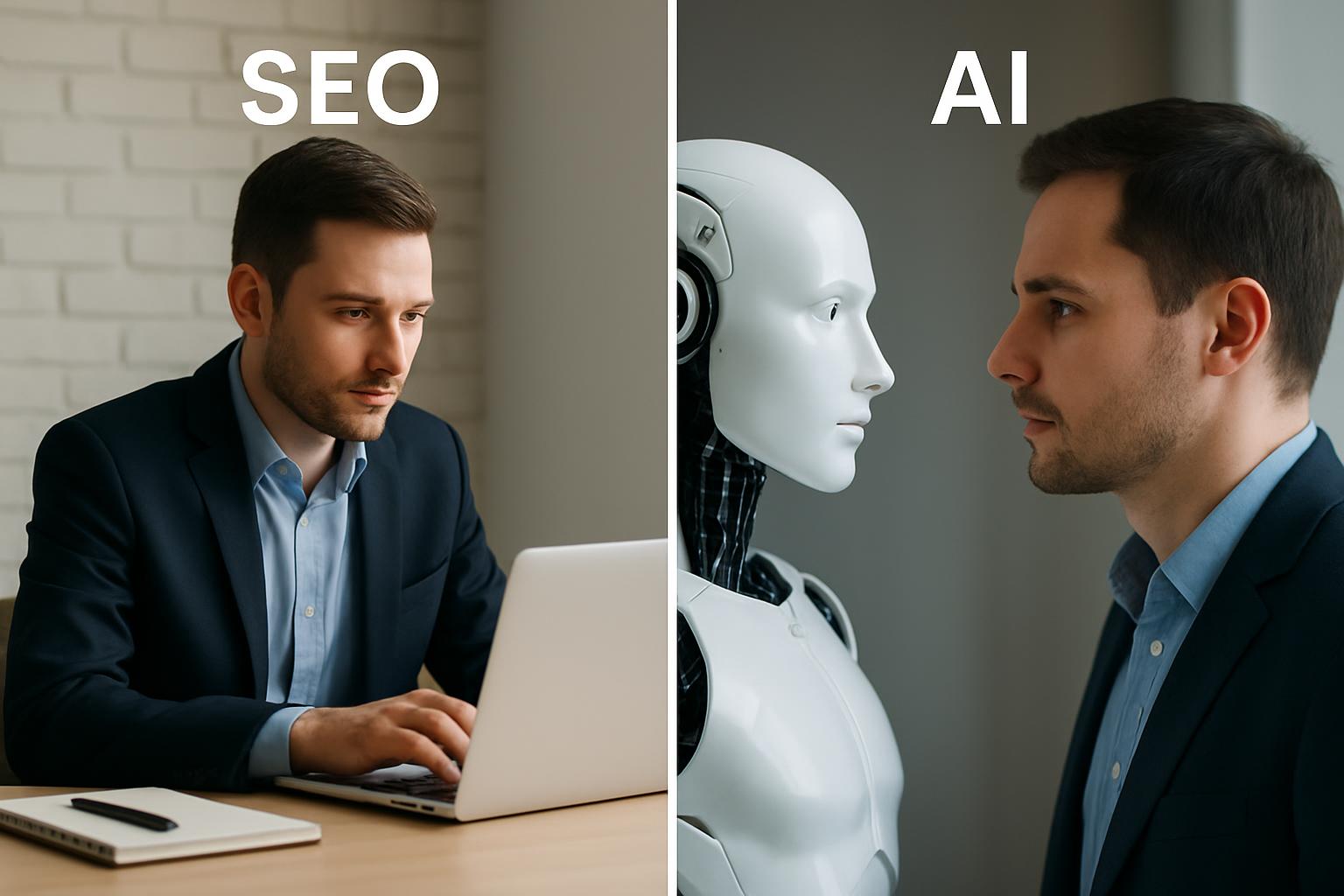この記事では、GoogleのSGE(検索生成体験)をはじめとするAIの進化がSEOの世界に与える影響を深く掘り下げます。そして、これからのオウンドメディア担当者に求められる役割の変化と、今すぐ実践すべき5つの具体的なアクションについて、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。AI時代に一層重要となるE-E-A-Tの考え方から最新ツールの活用法まで、未来の検索エンジンで勝ち抜くための本質的な戦略がわかります。
関連記事:AI検索とは何か? 従来の検索との違い&最新AI検索エンジン8選
人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?
BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!
目次
はじめに なぜ今「SEOからAIへ」のシフトが重要なのか

この章では、なぜ今「SEOからAIへ」という大きなパラダイムシフトが起きているのか、そして、この変化がオウンドメディア担当者にとってどれほど重要なのかを解説します。この不可逆的な変化の本質を理解し、次の一手を打つための準備を始めましょう。
検索体験の根底を揺るがすAIの波
近年、Googleが検索結果に導入したSGE(検索生成体験)に代表されるように、AIがユーザーの質問に対して直接的な回答を生成するようになりました。 これまでのユーザー行動が「キーワードで検索し、表示されたWebサイトのリストから答えを探す」というものだったのに対し、これからは「AIが生成した要約を読み、それで満足する」という形へと変化していきます。
この変化は、Webサイトへのトラフィックを前提としてきたオウンドメディア戦略にとって、サイトへの流入数が激減しかねない深刻な脅威となります。ユーザーが検索結果ページから離脱せずに目的を達成する「ゼロクリックサーチ」が増加し、従来のSEOのKPIであった検索順位の価値すら相対的に低下する可能性があるのです。
関連記事:SEOで注意したいゼロクリック検索〜流入を増やすポイントとは
単なるトレンドではない、不可逆的な変化
AIによる検索体験の変革は、一過性のトレンドではありません。これは、ユーザーがより速く、より的確な情報を求めるという本質的なニーズに応えるための、検索エンジンの必然的な進化です。つまり、この流れは今後さらに加速することはあっても、決して元に戻ることはないでしょう。
下の表は、従来型SEOとAI時代のSEOで求められる考え方の違いをまとめたものです。
| 項目 | 従来型SEO | AI時代のSEO |
|---|---|---|
| 主な目的 | 検索エンジンで上位表示させ、サイトへ集客する | AIに引用・参照され、検索結果上で認知・信頼を獲得する |
| 評価の主体 | 検索エンジンのアルゴリズム | アルゴリズム + AIによる文脈理解と信頼性評価 |
| コンテンツの役割 | ユーザーの検索意図を満たす「答え」を提供する | AIが生成する回答の根拠となる「信頼できる情報源」となる |
このように、もはや「様子見」が許される段階は過ぎ去りました。変化の波に乗り遅れれば、これまで築き上げてきたWeb上でのプレゼンスを失いかねません。今すぐAIを前提とした新しい戦略へと舵を切ることが、企業のマーケティング活動において喫緊の課題となっています。
本記事で解説すること
この記事では、こうした大きな変革期において、オウンドメディア担当者が具体的に何をすべきかを体系的に解説していきます。AIがSEOの世界をどう変えるのか、従来の施策の何が通用しなくなるのかを明らかにし、明日から実践できる具体的なアクションプランを提示します。
読み終える頃には、AI時代を勝ち抜くための新たな視点と、自社のオウンドメディアをさらに成長させるための具体的な戦略を描けるようになっているはずです。
SEOとAIのこれまでとこれから
この章では、AIの登場によってSEOの世界がどのように変化しつつあるのかを理解するために、まずはこれまでのSEOの歴史を振り返り、次にAIがもたらす未来の姿を明らかにしていきます。これまで当たり前とされてきた常識が、今まさに大きな転換点を迎えているのです。
AI登場以前の従来型SEO
AIが本格的に活用される以前のSEOは、検索エンジンのアルゴリズムを分析し、いかに上位表示を獲得するかというテクニカルな側面に重きが置かれていました。Googleが登場した2000年代前半から、その評価基準は被リンクの質と量が中心でした。その後、パンダアップデートやペンギンアップデートといった大規模な更新を経て、コンテンツの品質がより重視される時代へと移り変わってきました。
従来型SEOの主な施策は、以下の表のように整理できます。
| 施策の分類 | 主な内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 内部対策 | キーワード選定、タイトル・見出しの最適化、サイト構造化、表示速度改善など | Webサイトの内容を検索エンジンに正しく、かつ高く評価させる |
| コンテンツ制作 | 対策キーワードを含んだ網羅的な記事作成、定期的な情報更新など | ユーザーの検索意図に応える情報を提供し、集客の受け皿を作る |
| 外部対策 | 質の高い被リンクの獲得、サイテーション(言及)の獲得など | 第三者からの評価(権威性・信頼性)を高める |
これらの施策は、Googleのアルゴリズムが進化するにつれて、よりユーザーファーストの視点が求められるようになりましたが、基本的な考え方は「検索エンジンからの評価を最大化する」という点にありました。
関連記事
・「被リンク」とは?SEO初心者でもわかる本質と今日から始める獲得テクニック
・SEO担当者必見!サイテーションで競合に差をつける実践テクニック10選
AIが変える新しいSEOの世界
生成AIの登場は、このSEOの常識を根底から覆す可能性を秘めています。従来、ユーザーはキーワードで検索し、表示されたWebサイトを一つひとつ訪れて情報を探していました。しかし、AIがユーザーの質問に対して直接的な答えを生成・提示することで、Webサイトへアクセスせずにユーザーの検索行動が完結する「ゼロクリック検索」が増加すると予測されています。
AI時代のSEOは、もはや検索順位だけを追い求めるゲームではありません。従来との違いは以下の通りです。
| 比較項目 | 従来型SEO | AI時代のSEO |
|---|---|---|
| 検索の起点 | キーワード | 対話形式の質問・意図 |
| 評価の主体 | 検索アルゴリズム | 検索アルゴリズム + 生成AI |
| コンテンツの役割 | 検索流入の受け皿 | AIの参照元・引用元となる信頼性の高い情報源 |
| 目指すべきゴール | 検索順位の上位表示 | AIによる回答での引用・言及、ブランド認知の向上 |
これからのオウンドメディアは、単に検索エンジンに評価されるだけでなく、AIに「信頼できる情報源」として認識され、引用・参照されることが極めて重要になります。それは、キーワードを詰め込むことではなく、専門性や独自性、そして経験に基づいた一次情報を提供することで実現されるのです。
SEOの世界を一変させるAIの登場
この章では、AI技術がSEO、ひいてはデジタルマーケティングの景色をどのように塗り替えようとしているのか、その核心に迫ります。特に、Googleが提唱する新しい検索体験と、コンテンツ制作の現場で急速に普及する生成AIという二つの側面から、マーケターが今まさに直面している変革の波を解説します。
Googleが示す未来 SGE(検索生成体験)とは
SGE(Search Generative Experience)とは、Googleが検索エンジンに生成AIを統合した新しい検索体験のことです。 ユーザーが何かを検索すると、従来のようなWebサイトへのリンクリストだけでなく、AIが生成した概要や回答が検索結果の最上部に表示されるようになります。 これにより、ユーザーは複数のサイトを訪れることなく、迅速に求める情報へたどり着けるようになると期待されています。 2024年5月には「AI Overviews」という名称で米国で正式にローンチされており、日本でも2024年8月に提供がスタートしました。
この変化は、オウンドメディア担当者にとって看過できない影響をもたらします。具体的には、検索結果ページでユーザーの疑問が解決してしまう「ゼロクリックサーチ」の増加が予測され、これまでのように検索順位で1位を獲得するだけでは、Webサイトへの流入が保証されなくなる可能性があるのです。
| SGE(AI Overviews/AIO)の主な特徴 | マーケターへの影響 |
|---|---|
| 検索結果上部へのAIによる要約表示 | Webサイトへのトラフィックが減少する可能性がある(ゼロクリックサーチの増加) |
| 対話形式での追加質問が可能 | ユーザーのより複雑で深い検索意図への対応が求められる |
| 複数の情報源を統合して回答を生成 | AIに情報源として引用されるような、信頼性の高いコンテンツの重要性が増す |
関連記事:オウンドメディア運用・SEO担当者必見!「AIO」の行方と最新AIO対策の戦略とは?
コンテンツ制作の常識を覆す生成AIの役割
SGEが検索の「出口」を変える技術だとすれば、生成AIはコンテンツ制作という「入口」を根底から変革します。ChatGPTやGoogle Geminiといった生成AIは、もはや単なる文章作成ツールではありません。 これらを活用することで、コンテンツ制作のプロセスを劇的に効率化し、これまで以上に戦略的な業務へ時間を割くことが可能になります。
例えば、キーワードリサーチからペルソナ設定、記事構成案の作成、さらにはターゲットに合わせた複数のコピー案の生成まで、これまで多大な時間を要していた作業をAIがサポートします。 これにより、マーケターはAIを戦略的パートナーとして位置づけ、より創造的で質の高いコンテンツの企画・編集に注力できるようになります。
しかし、重要なのはAIにすべてを委ねることではありません。生成AIが生み出すコンテンツには、情報の誤りや独自性の欠如といった課題も残されています。 最終的な品質を担保し、ブランドの個性を吹き込むのは、あくまで人間のマーケターの役割です。AIをいかに賢く「使いこなし」、その能力を最大限に引き出すかが、今後のコンテンツマーケティングの成否を分ける鍵となるでしょう。
関連記事:【2025年最新版】Geminiとは?Google AIの進化&企業の活用事例集|若手〜中堅マーケター必見
AI時代でSEOの役割はどう変わるのか
AI、特に生成AIの登場は、検索エンジンのあり方を根本から変えつつあります。これに伴い、私たちオウンドメディア担当者に求められるSEOの役割も、従来の「検索エンジンをハックする」ようなテクニカルな視点から、「ユーザーとAIの両方にとって最も価値ある情報源となる」という、より本質的なものへとシフトしています。この章では、AI時代におけるSEOの役割の変化と、その中で変わること、そして変わらずに重要であり続けることを具体的に解説していきます。
変化する検索行動とユーザー体験の重要性
Googleが提供するSGE(検索生成体験)に代表されるAI検索機能は、ユーザーの検索行動を大きく変えようとしています。 これまでユーザーはキーワードで検索し、表示されたWebサイトのリンクを一つひとつクリックして情報を探していました。しかしAI検索では、ユーザーが入力した質問に対して、AIが複数の情報源を要約・統合した回答を検索結果の最上部に直接提示します。
この変化は、Webサイトへのトラフィックの流れを大きく変える可能性があります。 ユーザーはAIの回答だけで満足し、Webサイトを訪れない「ゼロクリックサーチ」が増加することが予想されます。 そのため、これからのオウンドメディアは、単に検索結果で上位表示を目指すだけでなく、AIが生成する回答の情報源として引用・参照されることが新たな重要指標となります。 そのためには、ユーザーがどのような意図で検索し、どのような答えを求めているのかをこれまで以上に深く洞察し、検索体験全体の質を高める視点が不可欠です。
E-E-A-Tはより一層重要になる
AIが自動でコンテンツを生成できるようになったからこそ、その情報の「信頼性」がかつてなく問われています。生成AIには、事実と異なる情報を生成してしまう「ハルシネーション」のリスクが常に伴います。 そのためGoogleは、情報の品質を担保するために、コンテンツの信頼性を示すシグナルである「E-E-A-T」をこれまで以上に重視すると明言しています。 E-E-A-Tとは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字を取った、Googleの検索品質評価ガイドラインにおける非常に重要な概念です。
関連記事:AIの嘘を見破れ!「ハルシネーション」の核心に迫る:原因、防止策、RAG・プロンプト術まで
専門性と権威性の証明
専門性(Expertise)と権威性(Authoritativeness)は、「誰がその情報を発信しているのか」という点に関わります。 AI時代においては、情報の出所が不明確なコンテンツは信頼されにくくなります。そのため、著者情報や監修者情報を明確にし、その人物や組織がその分野の専門家であることを具体的に示すことが重要です。 例えば、記事ごとに専門家のプロフィールを掲載したり、企業として特定の分野でどのような実績があるのかを運営者情報ページで詳しく説明したりといった対策が求められます。
経験と信頼性のコンテンツへの反映
E-E-A-Tの中でも、特にAIとの差別化で重要になるのが「経験(Experience)」です。 AIには生成できない、一次情報や実体験に基づいた独自のコンテンツは、ユーザーにとってもAIにとっても価値の高い情報となります。 例えば、製品のレビュー記事であれば実際に使用した感想や独自の検証結果を盛り込む、ノウハウ記事であれば成功事例や失敗談といった具体的なエピソードを交えるといった工夫が考えられます。そして、これら全ての土台となるのが「信頼性(Trust)」です。 サイト全体の透明性を高め、ユーザーが安心して情報を利用できる環境を整えることが、最終的にGoogleからの高い評価につながります。
従来のSEO施策で通用しなくなること
AIの進化により、過去に効果があった小手先のSEOテクニックは通用しなくなります。 むしろ、ユーザー体験を損なうような施策はペナルティの対象となる可能性さえあります。これからのSEO担当者は、古い常識を捨て、本質的な価値提供へと舵を切る必要があります。具体的に通用しなくなる施策と、これから求められる考え方を以下の表にまとめました。
| 従来のSEO施策 | AI時代に求められる考え方 |
|---|---|
| キーワードの詰め込み・出現率の調整 | ユーザーの検索意図を深く理解し、その問いに対する包括的で分かりやすい回答を提供する |
| 低品質な被リンクの大量獲得 | 関連性の高い権威あるサイトから、文脈に沿った自然な形で引用・参照される(サイテーション) |
| 網羅性を謳っただけの量産型コンテンツ | 独自の経験や一次情報に基づいた、専門性と信頼性の高い高品質なコンテンツを継続的に発信する |
| 検索順位のみを追いかけるテクニカルSEO | サイトの使いやすさ(UI/UX)や表示速度も含めた、ユーザー体験全体の最適化を追求する |
AIや検索エンジンと関係した最新マーケティング用語
AI時代の検索・情報設計マーケティング用語を一度整理してみましょう。例えば、AIOには2つの意味があります。使われる文脈によって指すものが異なるため、見極めが必要です。文脈が混同しやすいですが、Google検索特有の「AI概要」表示ならAI Overview、それ以外のAI施策全般ならAI Optimizationと判断できます。
| 用語 | 対象 | 主な目的・特徴 |
|---|---|---|
| SGE | Googleの生成AI搭載検索(旧名) | 検索時にAIが複数情報を自動要約し、検索画面で直接回答する実験的機能 |
| AIO(AI Overviews) | Google検索AI要約サービス | 検索結果上部にAIが情報を統合し人間の自然な言葉で答える正式機能。旧SGEの進化版 |
| AIO (AI Optimization) | AI技術全般 | AIが情報を正しく認識し引用しやすくなるよう最適化する広義概念。AIを使った広告やパーソナライズなど広範な最適化 |
| GEO | Google SGE/AIO等の生成AI検索 | AI生成検索の「回答欄」に自社情報を載せるための特化型SEOアプローチ |
| LLMO | ChatGPTなどLLM(大規模言語モデル) | LLM各種AIに自社情報を覚えさせ、回答や引用として選ばれやすくする最適化手法 |
AIO(AI Overviews)はSGEの正式版・Google公式名称です。「GoogleのAIによる概要表示」「AIOが表示された」「AIO枠」などと使われます。
AIO(AI Optimization)は「AI最適化」の略。「AIO対策」とは、検索や広告、サイト運営などの分野で、AIに自社情報を正しく評価・引用されやすくするための総合的な工夫や戦略です。AI技術をマーケティング全体で活用する広い概念です。「AIO対策」「AIO最適化」などと使われます。
GEO・LLMOはそれぞれ生成AIや大規模言語モデルへの情報最適化を狙った具体的手法です。GEO(Generative Engine Optimization)は検索エンジンの生成AI(Google SGEやAIO)の「引用枠」に自社情報を載せるための最適化手法のことです。SEOの延長線上にあり、構造化データや一次情報を仕込み、生成AIが参照しやすくすることが中心となります。
LLMO(Large Language Model Optimization)はChatGPTやGoogle Geminiなど大規模言語モデル(LLM)に、自社の情報を引用・参照してもらうための最適化テクニックを指します。検索エンジン以外でも、様々なAIモデルに認識・露出されることを目指す点が特徴です。
関連記事
・GEOとは? AI時代に欠かせないマーケティング戦略としての生成エンジン最適化について解説
・注目の「LLMO」とは?SEOとの違いと具体的対策を徹底解説
オウンドメディア担当者が今すぐやるべき5つのこと
AIがSEOのあり方を根本から変えつつある今、オウンドメディア担当者はこれまで通りの運用を続けるだけでは、時代の変化に取り残されてしまう可能性があります。この章では、AI時代に適応し、成果を出し続けるために、担当者が今すぐ取り組むべき5つの具体的なアクションを解説します。
AI検索を意識したコンテンツ戦略の見直し
AIによる検索体験、特にSGE(検索生成体験)は、ユーザーが検索結果ページから離れることなく、直接的な答えを得られる世界を実現しつつあります。この変化に対応するためには、単一キーワードでの上位表示を目指す従来型の戦略から、ユーザーの持つ潜在的な課題や一連の疑問に包括的に応えるコンテンツ戦略へと転換する必要があります。具体的には、一つの大きなテーマを軸に、関連する様々なトピックを網羅的に解説する「トピッククラスターモデル」の考え方がより一層重要になります。情報の網羅性に加え、自社独自のデータや専門家による監修、顧客の成功事例といった一次情報や独自の見解を盛り込むことで、AIが生成する回答にはない付加価値を提供することが、これからのオウンドメディアの生命線となるでしょう。
AIライティングツールを導入し制作プロセスを効率化する
コンテンツ制作の現場では、AIライティングツールが強力なパートナーとなります。これらのツールを活用することで、記事構成案の作成、文章の生成、リライトといった作業を大幅に効率化できます。しかし、重要なのはAIに全てを委ねるのではなく、あくまでアシスタントとして活用し、最終的な品質担保は人間が行うというスタンスです。AIが生成した文章には、事実誤認や不自然な表現が含まれる可能性があるため、ファクトチェックやブランドイメージに沿ったトーンへの調整、そして読者の心に響く独自の視点の追加といった「編集者」としての役割が、担当者には強く求められます。 AIを使いこなすことで、担当者は単純作業から解放され、より戦略的な業務に時間を割くことが可能になります。
おすすめの国内向けAIライティングツール
現在、国内市場にはマーケティング担当者向けに特化したAIライティングツールが多数登場しています。ここでは代表的なツールをいくつかご紹介します。
| ツール名 | 主な特徴 | 公式サイト |
|---|---|---|
| Catchy | キャッチコピーや記事作成、広告文など100種類以上の豊富な生成ツールが魅力。 幅広い用途に対応可能です。 | |
| SAKUBUN | ペルソナ設定機能やAIエディターの操作性に定評があり、SEOに特化した高品質な記事作成を効率化できます。 | https://sakubun.ai/ |
| Transcope | 競合サイトの分析やキーワード分析機能も搭載しており、SEOに強いコンテンツ作成を一気通貫でサポートします。 | https://transcope.io/ |
AIを活用したキーワード分析と競合調査
AIは、キーワード分析や競合調査の領域にも革命をもたらします。 従来のツールでは見つけにくかった、ユーザーの検索意図の裏にある潜在的なニーズや、ニッチな関連キーワードを発掘することがAIによって容易になります。 また、競合サイトがどのようなトピックを、どのような切り口でコンテンツ化しているかをAIが分析し、自社が狙うべきコンテンツの穴場や差別化のポイントを特定する手助けとなります。これらの分析結果を基に、データドリブンなコンテンツ戦略を立案することが、AI時代のSEOにおいて極めて重要です。
AI時代に求められるスキルセットの習得
AIの台頭により、オウンドメディア担当者に求められるスキルセットも変化しています。 これまでのSEO知識や編集スキルに加え、今後は以下のような能力が不可欠となります。
-
プロンプトエンジニアリング:意図した通りのアウトプットをAIから引き出すための、的確な指示(プロンプト)を与えるスキル。
-
データリテラシー:AIが提示する分析データを正しく解釈し、次のアクションに繋げる分析能力。
-
クリティカルシンキング:AIの生成した情報や提案を鵜呑みにせず、その内容が本当に正しいか、自社の戦略に合致しているかを批判的に思考し、判断する能力。
これらのスキルを習得し、AIを「使いこなす」側になることが、これからのマーケターとしての価値を高める鍵となります。
関連記事:プロンプトの基本知識と最新の活用例を紹介
最新のAIと検索エンジンの動向を常に追う
AIと検索エンジンの世界は、まさに日進月歩で進化しています。昨日まで有効だった手法が、今日にはもう通用しなくなる可能性も十分にあります。Googleの公式発表や、国内外の信頼できるSEO専門家の情報を定期的にインプットし、常に知識を最新の状態に保つことが、担当者にとって不可欠な責務です。特に「Google検索セントラルブログ」や著名なSEO情報サイトなどを定期的にチェックし、アルゴリズムの変更や新しいツールの登場といった変化に迅速に対応できる体制を整えておきましょう。
関連記事:2025年10月の検索順位変動まとめ【JADE代表 伊東氏の最新SEOレポート】
まとめ
本記事では、SGEをはじめとするAIの登場がSEOの世界にどのような変革をもたらすのか、そしてオウンドメディア担当者が今すぐ取り組むべきことについて、具体的なアクションを交えながら解説してきました。
結論として、SEOがなくなるわけではなく、AIとの共存を前提とした新たなステージへと役割が変化していきます。AIによって誰もが簡単にコンテンツを生成できるようになったからこそ、専門性や経験に裏打ちされたE-E-A-Tの高い、独自性のあるコンテンツの価値がより一層高まるのです。
この変化の波は、決して脅威ではありません。AIをコンテンツ戦略の立案や制作プロセスの効率化に活用することで、担当者はより本質的な業務に集中できるようになります。ご紹介した5つのアクションプランを参考に、AI時代の新しいSEOへ向けた第一歩を今すぐ踏み出しましょう。