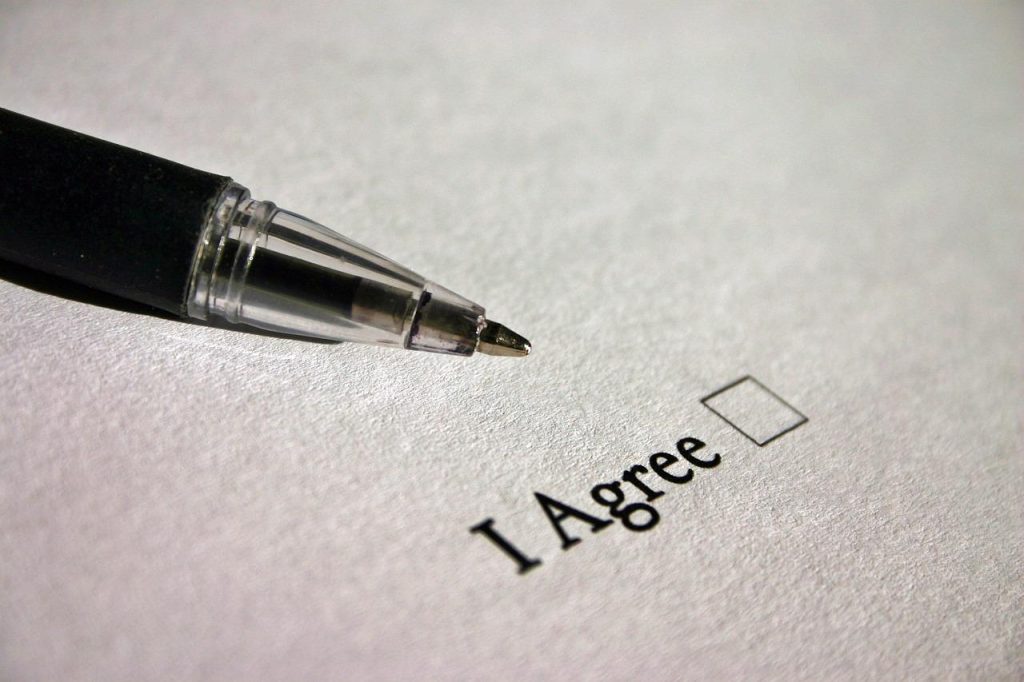SNSで誰もが気軽に情報を発信できる今、何気なく投稿した写真や動画が思わぬ「肖像権侵害」となり、トラブルに発展するケースが増えています。
特に企業の広報・マーケティング担当者にとっては、自社コンテンツが他者の権利を侵害していないかどうかが運営上の重要なリスク管理項目となります。
たとえば、社内イベントの様子をSNSに投稿する際、社員や来訪者の顔が明確に写っていると、本人の許可がなければ問題となる可能性があります。
本記事では目次として、肖像権の基本から、プライバシー権・パブリシティ権との違い、侵害とされる要素、過去の判例、そして万が一の際に発生しうる慰謝料の目安までを解説します。広報・マーケティング担当者にとっては、必読かつおすすめの内容となっておりますので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?
BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!
目次
肖像権とは
まずは肖像権の基本について整理しましょう。
「肖像権」の定義
肖像権とは、自分の容姿や姿態について許可なしに撮影・使用・公表されてしまうことを、明確に拒否できる権利のことです。
この権利は民法などに明文化されているわけではありませんが、判例の積み重ねにより、日本では確立された法的概念として広く認識されています。
たとえば、街中で撮影した写真をSNSに投稿し、そこに通行人の顔がはっきり映っていた場合、本人が「無断で撮られ、公にされた」と感じれば、肖像権侵害を主張される可能性があります。
これは個人・企業を問わず、他者の人格を尊重するという社会的ルールに関わる行為といえるでしょう。
▼以下の関連記事では、肖像権に加え著作権や特許権といった知的財産権など、様々な権利をまとめて解説しています。
著作権とは?制作担当者が知っておくべき保護の期限・期間や侵害しないための基礎知識&ミッキー事例も紹介
肖像権のベースは「幸福追求権」
肖像権の根拠とされるのは、日本国憲法第13条に規定された幸福追求権です。
この条文は、すべての国民に対し「個人として尊重される権利」と「幸福を追求する権利」を保障しています。
つまり、自分の顔や姿をどう扱うかは本人の自由であるため、それを他人が無断で利用することは、この自由を不当に侵害する行為と見なされます。
こうした法的思想を基盤として、肖像権は個人の尊厳を守る権利として社会に定着してきました。
肖像権は「プライバシー権」と「パブリシティ権」の2つで構成される
肖像権は、大きくプライバシー権とパブリシティ権の2つに分けて考えられます。
プライバシー権とは、本人の意思に反して容姿を撮影・公表されないようにするための人格的な(人格にとっての利益を保護する)権利です。
対してパブリシティ権は、肖像を通じて得られる経済的な利益を本人が管理・活用するための権利です。
これらの違いや具体的な内容については、次項で詳しく解説します。
「肖像権」と「プライバシー権(人格権)」「パブリシティ権(財産権)」との関係性
プライバシー権とは、個人の私的な情報や生活に対する不当な干渉を排除する権利です。
肖像(顔や姿態)も個人の人格の一部と捉えられるため、「勝手に撮られたくない」「自分の顔を他人に知られたくない」といった感情が、この権利によって保護されます。
たとえば、社員が社内で過ごしている様子を無断で撮影し、それをWebサイトやSNSに投稿した場合、本人の意に反していればプライバシー権の侵害にあたる可能性があります。
一方、パブリシティ権は、特に著名人などの肖像や氏名に経済的価値がある場合において、本人がその価値を管理・コントロールするための権利です。
たとえば、芸能人やスポーツ選手の顔写真を許可なく商品広告に使用すれば、本人が本来得られたはずの利益を奪う行為となります。
つまり、プライバシー権が「人格的利益」のほうを守るという目的であるのに対して、パブリシティ権は「経済的利益」のほうを守るための権利といえます。
実務上、これら2つの権利が同時に侵害されるケースも少なくありません。
タレントの自宅を無断で撮影・掲載した場合、私生活への不当な干渉(プライバシー権の侵害)であると同時に、肖像の商業的利用によるパブリシティ権の侵害にも該当します。
また、一般人であっても、撮影や公表の状況によっては、人格的・経済的の両面で不利益を被ることがあり、裁判で複数の権利侵害が争点となるケースもあります。
マーケティング活動においては、社員インタビュー、顧客事例、イベントレポートなどに人物写真を掲載する場面が多く、肖像の扱いには十分な注意が必要です。
● 本人の同意があるか
● 撮影・掲載の目的が妥当か
● 公開範囲が広すぎないか
これらを事前に確認し、必要に応じて書面で同意を得ておくことが、リスクヘッジにつながります。
関連記事
・リスクヘッジとは?ビジネスにおける意味とやり方
・戦国武将たちのリスクヘッジとは?現代のビジネスや個人にも通用する施策【歴史の偉人に学ぶマーケティング 連載第7回】
肖像権の侵害にあたる行為についての基本的な考え方
肖像権侵害とは、本人の許可なく顔や容姿などを撮影・使用・公表し、人格的または経済的な利益を不当に損なう行為を指します。
以下では、肖像権が侵害と判断される代表的なケース一覧を、判例の考え方を踏まえながら3つの視点から整理します。
撮影拒否権の侵害
1つ目は、「撮られたくない」という意思を無視して撮影された場合です。
特定の人物が「写真は撮らないでください」と明示していたにもかかわらず、無断で撮影すれば、撮影拒否権の侵害にあたります。
判例では、公共の場であっても「撮影が明らかに本人の意思に反している」場合、肖像権の侵害が成立する可能性があるとされています。そのため、公共の場所だからといって自由に撮影できるとは限りません。
この考え方は、ストリートスナップやVlog、SNSでのライブ配信など、日常的に行われる映像投稿にも影響します。
たとえ偶然の写り込みであっても、執拗だったり、本人が不快感を示していた場合は問題となる可能性があります。
使用・公表の拒絶権の侵害
2つ目は、撮影された肖像を無断で使用・公開する行為です。
具体的には、社員の顔写真を本人の同意なく企業のWebサイトに掲載したり、インタビュー動画に登場させたりするケースが該当します。
ここで重要なのは、「撮影されること」と「撮影されたものを公開されること」は別の行為であり、どちらについても本人の同意が必要だという点です。
たとえ業務中の姿であっても、それが個人の尊厳や私生活に関わる場面であれば、本人の意思に反する公開は肖像権の侵害となる可能性があります。
また、企業のSNS運用では、投稿が半永久的に残ることも多く、一度の無断掲載が長期的な侵害につながる恐れもあります。
関連記事
・ネットリテラシーとは!意味を分かりやすく解説!
・デジタルタトゥーの意味や企業事例、消し方を解説
財産的利益を保護する権利の侵害
3つ目は、肖像が本来持つ経済的価値を無断で利用し、パブリシティ権を侵害するケースです。
典型例は、タレントやインフルエンサーの顔写真を許可なく広告に使用する行為です。肖像は本人にとって収益を生む資産であり、その使用には正当な契約と対価が求められます。
近年では、著名人でなくともSNSで影響力を持つ個人が「顔写真が無断でビジネスに利用された」として弁護士に依頼や相談をしたり、訴訟を起こしたりする事例も多いです。
企業が肖像を使用する際は、「写っているかどうか」だけでなく、「その使用で誰が利益を得るか」という視点が欠かせません。
肖像権侵害の判断基準としておさえておきたいポイント
肖像権侵害か否かは、単純に「写っているかどうか」ではなく、撮影・公表の状況や意図、被写体の立場などを総合的に見て判断されます。
特に重要なのが、最高裁が平成17年11月10日に下した判決です。
この判例では、肖像権に関わる情報の「撮影および公表」が適法かどうかを判断する際に考慮すべき6つの要素が示されました。
以下、それぞれの要素を詳しく見ていきましょう。
「撮影された人」の社会的地位
公人(政治家・著名人)か私人(一般人)かによって、肖像の公表が許容される範囲は異なります。
社会的影響力のある人物は一定の公表が認められやすい一方、一般市民はより強く保護されます。
「撮影された人」の活動内容
被写体が公の場で発言・行動していた場合、注目を受ける立場と見なされ、撮影・公表が正当化されやすくなります。逆に私的な場面では保護の必要性が高まります。
撮影の場所
駅やイベント会場など公共の場ではある程度の撮影が許容されますが、自宅や個室などプライバシー性の高い場所では無断撮影が違法となる可能性があります。
撮影の目的
報道・教育・公益目的の撮影・公表は認められることがあります。一方で、営利目的や嫌がらせなど悪意ある目的は、侵害と判断されやすくなります。
撮影および公表の態様
過剰な撮影や侮辱的な編集・コメントがある場合は、肖像権だけでなく名誉毀損にもつながる可能性があります。SNSでの煽りやバズ狙いの投稿は特に注意が必要です。
撮影および公表の必要性
撮影や公表が本当に必要だったかも判断基準になります。
全体の様子を伝える目的は認められやすい一方、特定の人物を強調する必要が乏しい場合は侵害と見なされる恐れがあります。
肖像権侵害となりやすいケース
企業や個人がSNSやWebメディアを運用する際に注意すべき、肖像権侵害になりやすい典型的なケースを以下の表にまとめました。
| ケース | 内容 | 注意点・例 |
| 顔が明確に特定できる写真や動画 | 個人の顔がはっきり写っていて、誰であるかが特定できる画像や映像 | 例:社内イベントや店舗紹介のSNS投稿など。無断使用で侵害リスクあり |
| 被写体が主題となっている撮影 | 特定の個人をクローズアップして撮影・掲載するケース | 例:セミナー登壇者、社員インタビュー。本人の同意がなければ高リスク |
| プライバシー性の高い場所での撮影 | 自宅、社内の個室、医療機関などの私的空間での無断撮影 | 肖像権だけでなくプライバシー権侵害として問題になる可能性が高い |
| 拡散力の高いメディアでの公表 | SNSやYouTube、Webメディアなどでの公開 | 一時的でもスクショや引用で拡散され、後々の削除が困難になることも |
さらに、検索エンジンにインデックスされるWebメディアへの投稿は、削除してもキャッシュや引用などの痕跡が残りやすく、結果的に永続的な被害につながる恐れもあります。
関連記事
・スクリーンショットとは?スマホ、パソコンでの簡単なやり方と注意
・引用とは?参照・参考・転載との違いや意味、書き方について解説
・キャッシュとは?初心者でも分かる仕組みやキャッシュクリア(削除)の方法
肖像権侵害となりにくいケース
肖像権の侵害は、個人の同意なく肖像を撮影・使用・公表することで成立しますが、逆に「肖像権侵害に該当しにくいケース」も存在します。
これは、写っている人の特定が困難であるケース、状況から見て社会通念上許容されると判断されるケースなどです。
以下の表は、肖像権侵害のリスクが比較的低いとされる具体例をまとめたものです。
ただし、これらは絶対に問題がないという意味ではなく、「侵害とまでは評価されにくい」状況であることには注意をしてください。
| ケース | 内容 | 注意点・例 |
| 顔がはっきり特定できない写真や動画 | 後ろ姿、遠景、モザイク処理などで個人の特定が困難な場合 | 街並み・イベント風景など。顔が小さい・ぼやけている・写っていない写真なども含む |
| 集合写真の公開 | 数人〜数十人が写る集合写真で、特定の人物を強調していない場合 | 雰囲気記録目的ならリスクは低いが、ピントやキャプションで特定可能な場合は注意 |
| 公共の場での映り込み | 駅、商業施設、イベント会場などでの自然な背景写り込み | 一般的には許容されやすいが、意図的に個人を狙った撮影は侵害リスクあり |
| 屋外イベントでの映り込み | ライブやフェスなど大規模イベントの風景に観客が映り込む場合 | 全体の雰囲気を伝える目的なら肖像権侵害に該当しにくい |
| 被写体本人から同意を得ている場合 | 明示的な撮影・公表の同意がある場合 | 書面や電子的な同意の取得が望ましい。口頭同意だけでは後のトラブルに注意 |
| 撮影されることが予測できる状況 | セミナーや記者会見など、撮影が前提の場面 | 撮影禁止の指示がある場合や、本人の強い拒否がある場合は除く |
| 被写体が著名人・公人である場合 | 政治家、芸能人など社会的関心が高い人物 | 表現の自由が優先されやすいが、私生活や商用利用には別途配慮が必要 |
また、著名人であってもプライベートな空間での撮影や商用利用などになると、パブリシティ権やプライバシー権の問題が生じるため、慎重な判断が求められます。
肖像権侵害が起きてしまった場合、慰謝料の相場はどのくらい?
肖像権が侵害された場合、被害者は精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)を請求できます。
ただし金額は一律ではなく、侵害の態様や悪質性、被害の程度などを総合的に見て裁判所が判断します。
一般的な相場感としては、通常の肖像権侵害では、慰謝料は10万〜50万円程度が目安です。
執拗な撮影や長期拡散、本人の抗議を無視して継続した場合などは、100万円以上となることもあります。
以下のような場合、慰謝料が数百万円に達する可能性があります。
● 私生活や性的情報を含む無断撮影・公表(例:リベンジポルノ)
● 誹謗中傷や晒し行為など、明確な悪意を持った撮影・公表
● 組織的・継続的に違法行為を行った企業のケース
さらに、名誉毀損やプライバシー権、パブリシティ権などが同時に侵害されている場合は、慰謝料が加算される傾向にあります。
【参考】肖像権侵害の慰謝料請求の判例
以下に、肖像権侵害により慰謝料の支払いが命じられた実際の判例を紹介します。
■被告がSNS上で原告になりすまし、原告の顔写真を無断でプロフィール画像に使用した例
原告に酷似したアカウント名を用い、他の利用者に対して侮辱的な投稿を繰り返した事案です。これにより原告は、名誉権・肖像権・プライバシー権・アイデンティティ権の侵害を主張し、損害賠償を請求しました。
裁判所は、無断の顔写真使用が肖像権およびプライバシー権の侵害、なりすましによる侮辱的投稿が名誉権の侵害、人格的同一性の偽装がアイデンティティ権の侵害に該当すると判断。
被告に対し、慰謝料60万円、発信者情報開示費用58万6,000円、弁護士費用12万円、合計130万6,000円の支払いを命じました。
参考:大阪地方裁判所(平成29年(ワ)第1649号 損害賠償請求事件 平成29年8月30日)
まとめ:肖像権の侵害は不法行為! ネット運用においてくれぐれもご注意を
SNSやオウンドメディアの普及により、企業・個人を問わず写真や動画を発信する機会が増える一方で、肖像権侵害のリスクも確実に高まっています。
そのため、WebメディアやSNSの運用においては、コンテンツ制作のクリエイティブ性だけでなく、法的な視点を取り入れた対応が必要不可欠です。
▼Profutureのマーケティング支援サービスなら、安心したコンテンツ運用が可能です。企業のメディア運営を豊富に支援してきた実績をもとに、肖像権や著作権といった法的リスクへの配慮を含めた「安全かつ戦略的なコンテンツ設計」をサポート致します。
https://www.profuture.co.jp/mk/solution/248